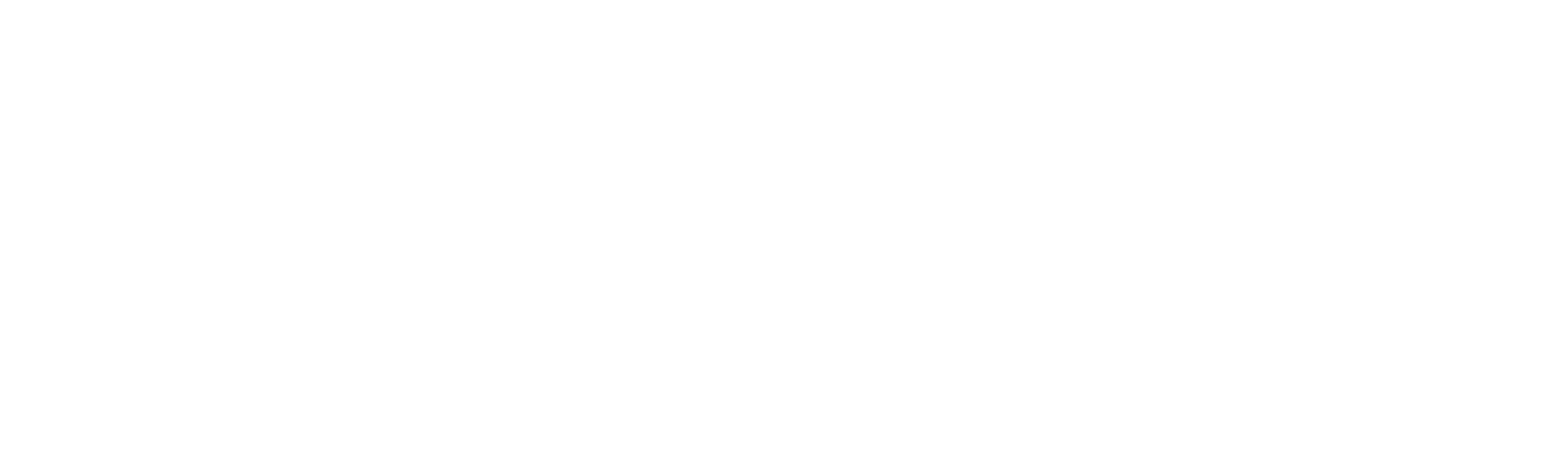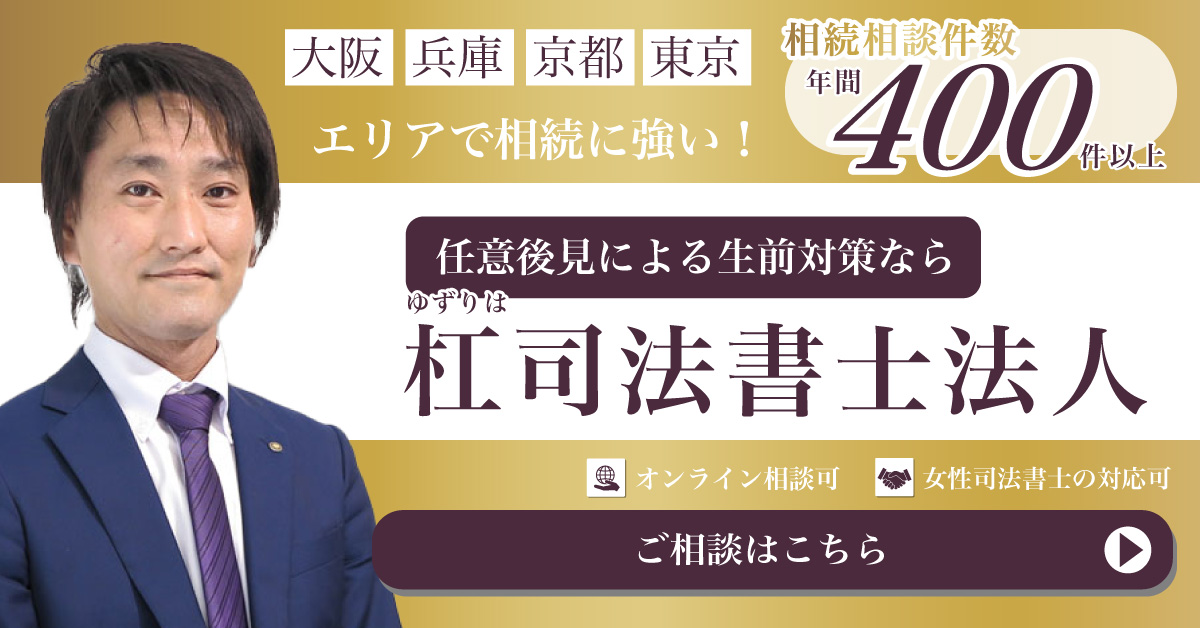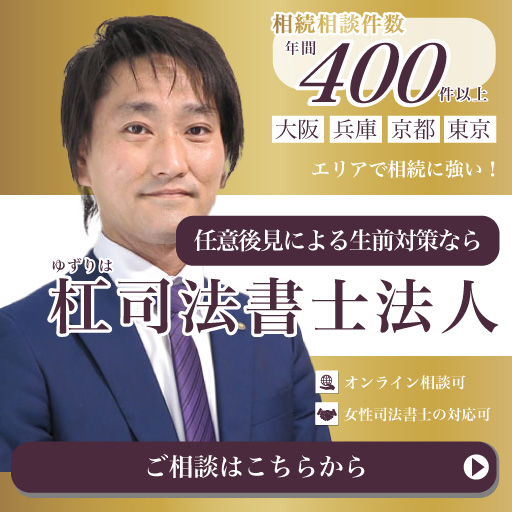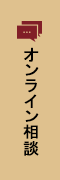任意後見契約を複数人と結ぶことは可能?知っておきたいポイントを解説
成年後見
投稿日:2025.04.14

任意後見契約は本人の判断能力が低下した際に備えて、財産管理などを行う後見人と契約する制度です。
複数人の任意後見人をつけることも可能ですが、どのような点に気をつければ良いか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、複数人と任意後見契約を結ぶ際に知っておきたいポイントや注意点について解説します。
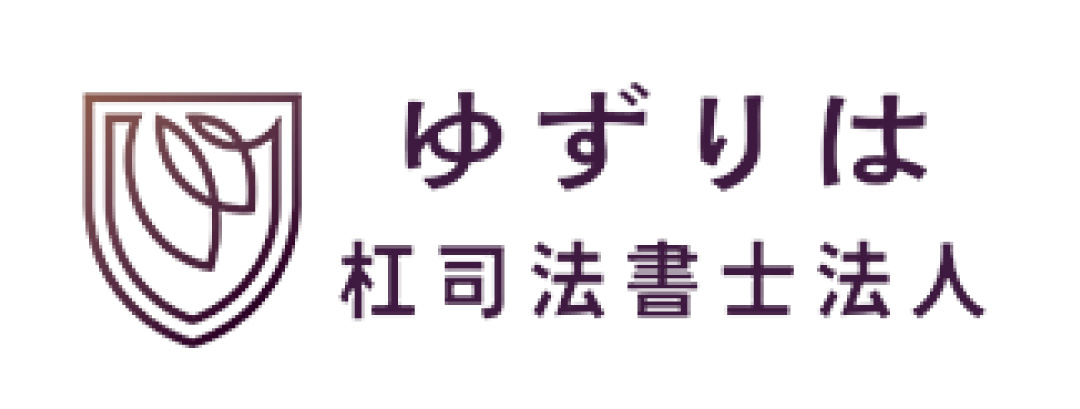
大阪・兵庫・京都・東京を拠点に、相続手続き・遺言書作成・家族信託契約などのサポートから企業法務まで、専門のチームで対応しております。税理士や他業種との連携により、相続問題をワンストップで解決!相続関連の相談件数は年間400件超。
目次
任意後見契約は本人の判断能力低下に備えて行う委任契約
任意後見契約とは成年後見制度の一つで、病気や障がい、認知症などで本人の判断能力が低下した際に、あらかじめ選んでおいた任意後見人に財産管理や身上監護を委任する契約のことです。
法定後見制度とよく似ていますが、本人が元気なうちに自らの意思で後見人や契約内容を決めているという点が大きく異なります。
制度の趣旨に沿ったものであれば委任内容や範囲も自由に設定できるため、より本人の意思を尊重した支援が可能になるのも特徴といえるでしょう。
任意後見人を複数つけることも可能
任意後見人を選ぶのは、必ずしも一人である必要はありません。
任意後見契約について定めた法律である後見登記等に関する法律では、任意後見人を複数契約することが可能だとされています。
そのため、「二人いる子どものどちらかだけを任意後見人にするのは不公平なので、両方と契約したい」「親族と専門職両方に任意後見人を引き受けてもらいたい」などのケースにも対応可能です。
ただし、任意後見人を複数つける場合、それぞれの代理権について考える必要があります。
任意後見人が複数いる場合の代理権の方式
任意後見人を複数契約している場合の代理権は「単独代理」と「共同代理」に分けられます。
以下では、それぞれの範囲や違いについて解説します。
単独代理
単独代理とは複数の任意後見人がそれぞれ単独で代理権を行使する方式で、各自代理方式とも呼ばれます。
複数ついている後見人全員が任意後見契約に関する全ての行為を行うのが基本ですが、条件を設定することで任意後見人ごとに代理権を分担することも可能です。
この条件設定によって「任意後見人Aは不動産を管理」「任意後見人Bは身上監護」「任意後見人Cは預貯金を管理」などの分担を行えるようになります。
逆に、分担されていない部分については、代理権を行使することができません。
単独代理の場合は、本人とそれぞれの任意後見人が個別で契約を結ぶことになります。
それぞれが分担している部分のみに対して、代理権を行使すると考えれば良いでしょう。
共同代理
共同代理とは、任意後見人全員が協議して代理権を行使する方式です。
この方式を選択するには「代理権の共同行使の特約目録」を作成し、任意後見契約書に添付しなければなりません。
任意契約と違い、本人と任意後見人全員が契約を結ぶことになります。
特約目録に記載されていない部分は単独代理となるため、以下のようなかたちで代理権を行使することもできます。
- 任意後見人Aが身上監護
- 任意後見人Bは預貯金の管理
- 有価証券と不動産の管理は共同代理
財産管理のうえで協議が必要な部分は共同代理にするなど、本人の意向に合わせて組み合わせられるのが特徴です。
任意後見契約を複数人と結ぶメリット
任意後見契約を複数人と結ぶメリットとして、以下の4つがあります。
- 一人当たりの負担が減る
- 相談しながら事務を行える
- 不正を未然に防止できる
- 安定した長期サポートが可能になる
それぞれについて詳しく解説します。
一人あたりの負担が減る
任意後見契約における財産管理と身上監護の仕事は幅広く、自分の生活や自身の仕事を抱えながら任意後見人としての事務も行う場合、後見人への負担はかなり大きくなります。
複数の任意後見人が作業を分担することで、一人あたりの負担を減らすことができるでしょう。
たとえば、日々の細かな支援や病院への支払いは近くに住んでいる後見人が担当し、金融資産や不動産の管理は専門家に任せるといった方法を取ることも可能です。
それぞれが得意とする分野や作業しやすい分野を受け持てるのも、複数の任意後見人をつけるメリットといえるでしょう。
相談しながら事務を行える
任意後見人は、本人に代わってさまざまな事柄を判断しなければなりません。
それだけに責任は重く、一人では対処に困ってしまうこともあります。
代理人が複数いれば相談しながら対応できるので、本人にとってよりベストな支援が行えるというのもメリットといえます。
不正を未然に防止できる
任意後見人は本人に代わって預貯金や不動産、有価証券を扱える代理権を有しています。
しかし、その権限の大きさゆえに、不適切な事務や横領といった不正が行われやすいという残念な側面もあります。
複数の任意後見人がいればお互いの後見事務をチェックしあえるので、不正が入り込む余地が少なく、より適正でクリアな後見事務を期待できるでしょう。
安定した長期サポートが可能になる
任意後見契約を結ぶうえで問題になるのが、任意後見人が何らかの事情で後見事務を続けられなくなったときの取り扱いです。
任意後見人が亡くなった時はもちろん、破産手続開始決定を受けたときや、後見人自身が後見開始の審判を受けると任意後見契約が終了するため、以後の支援を受けられなくなってしまいます。
そういった場合でも複数の任意後見人がいれば、後見人が欠けたとしても引き続き支援を受けることができます。
長期的な財産管理や資産運用が必要な方にとっては、心強いメリットといえるでしょう。
ただし、共同代理を選択していると、任意後見人の一人が死亡したり不正が発覚した場合、ほかの任意後見人に問題がなくても任意後見契約が終了してしまいます。
共同代理は本人と任意後見人全員が一通の公正証書で契約書を交わすため、このような問題が起こりうる可能性も覚えておかなければなりません。
長期的な支援を続けるためには、契約を交わす時点で専門家のアドバイスを受けることも大切です。
任意後見人を複数と結ぶデメリット
任意後見を複数人と結ぶのは、以下のようなデメリットも考えられます。
- 意見が対立する恐れがある
- 費用負担が大きくなる
- 代理権の付与が複雑になる
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
意見が対立するおそれがある
意見交換しながら力を合わせて後見事務を行えるのは、複数の任意後見人をつける利点ですが、ひとたび意見が対立してしまうと、デメリットにもなります。
任意後見契約は本人の意思を尊重して締結されるものですが、内容をどのように解釈するかは、本人との関係性や立場によって異なります。
そのため、不動産の売却や病院の選定といった重大な選択だけでなく、日々の細かい支援においても意見が対立するごとに後見事務が滞ってしまうというリスクがあるのです。
特に共同代理の場合は、一人でも反対すると代理権を行使できなくなります。
どこで折り合いをつけるのかよく話し合っておく、場合によっては単独代理を検討するなど、事前の制度設計をしっかり練っておくことが大切です。
費用負担が大きくなる
任意後見契約人に支払う報酬は人数分必要なため、複数人と契約すると、それだけ費用負担が大きくなります。
また、専門家を任意後見人にした場合、報酬はさらに高額になります。
任意後見人への報酬がかさみ、本人の希望する医療や介護に必要な費用が捻出できないのでは意味がありません。
本人の意向や財産の収支状況を踏まえたうえで、事前にしっかり試算することをおすすめします。
代理権の付与が複雑になる
複数の任意後見人と契約する場合、単独代理と共同代理を選択することになります。
代理権の付与内容によっては後見事務がスムーズに進まなくなるだけでなく、任意後見契約そのものが継続できなくなることもあります。
そのため、複数での任意後見を考える際はそれぞれの状況や得意分野、信頼関係まで考慮したうえで役割分担を決め、代理権を付与することが重要です。
専門家のアドバイスも受けながら、慎重に代理権の付与を決めることが求められます。
任意後見人をつけるまでの流れ
任意後見人をつけるまでの流れは、以下のステップで進めていきます。
- STEP1:任意後見人を選出する
- STEP2:任意後見契約を結ぶ
- STEP3:任意後見監督人の申し立てを行う
- STEP4:任意後見人の事務が開始される
それぞれ順番に解説します。
STEP1:任意後見人を選出する
財産管理や身上監護を行う任意後見人を決めて、指名を行います。
任意後見人を複数契約する場合は、この時点で決めておきましょう。
指名された人は「任意後見受任者」と呼ばれ、契約が締結されれば任意後見人となります。
任意後見人になれる人はほぼ制限がなく、家族や友人に加えて、弁護士や司法書士といった専門家を選ぶこともできます。
自分の財産や身上管理を行う重要な役割ということを踏まえ、本当に信頼できる人を選ぶことが大切です。
STEP2:任意後見契約を結ぶ
任意後見受任者が決まったら、支援内容とその範囲を決めていきます。
介護計画や施設への入所希望、不動産の売却方針などを中心に契約内容を考えましょう。
たとえば、「自宅介護が難しくなったらこの施設に入所したい」「医療費はこの不動産を売却してまかなってほしい」など、細かい意向を契約書に盛り込んでいきます。
単独代理にするか共同代理にするか、代理権の付与についてもこの時点で協議します。
代理権の付与は複数人の任意後見人をつけるうえで、重要な部分です。
本人や任意後見受任者の意向、財産の収支をよく確認し、専門家も交えて慎重に協議しましょう。
任意後見契約書は公正証書として作成され、公証人が登記申請を行ないます(「登記を嘱託する」といいますが、弁護士や司法書士ではなく役所などが職権で登記してくれることを嘱託登記と言います。)。
登記から2~3週間後に「登記事項証明書」が発行され、正式に任意後見受任者として認められます。
STEP3:任意後見監督人の申し立てを行う
契約後、本人の判断能力が低下した場合、任意後見を開始するために任意後見監督人の選任申し立てを行います。
申し立ては家庭裁判所に提出し、本人と任意後見受任者の面接や本人の精神鑑定などが行われ、問題がなければ任意後見監督人の選任に移ります。
任意後見監督人は家庭裁判所によって選出されますが、任意後見人の近い親族や配偶者の選任は認められていません。
一般的には弁護士や司法書士、福祉の専門家などが選任される傾向が強いようです。
STEP4:任意後見人の事務が開始
家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の情報が法務局で登記されると、任意後見契約が発効します。
任意後見人は登記事項証明書を提示することで、さまざまな代理事務を行うことができるようになります。
予備的任意後見人を指定することは可能?
任意後見人の死亡や不慮の事故など、後見事務の遂行ができなくなった場合に備えて、予備の任意後見人を契約しておくことは可能なのでしょうか。
現在の法律では、後見登記等に関する法律に任意後見人の順位に関する規定がないため、「Aが死亡した場合は、代わってBを任意後見人とする」といった契約を結ぶことはできません。
また、任意後見監督人の選任と任意後見契約の効力発生に時間差が生じるのも、制度の趣旨にそぐわないとされています。
万が一に備える方法として、本人とそれぞれの任意後見人が契約を締結し「Aが後見事務を行える間は、Bは後見事務を行わない」などの特約を付けるという方法もあります。
ただし、こういった特約を登記する方法はないので、家庭裁判所は特約には拘束されません。
現行の制度において、予備的任意後見人を確実に指定するのは難しいといえるでしょう。
相続対策なら杠(ゆずりは)司法書士法人までご相談ください
複数の任意後見人を置くのは一人あたりの負担が減り、協力して後見事務を行えるのがメリットです。
一方で代理権の付与が複雑になったり、任意後見人の意見が対立すると後見事務に支障をきたすリスクも伴います。
杠(ゆずりは)司法書士法人では、任意後見契約に関するご相談を受け付けています。
「子ども全員を任意後見人にしたい」「親子で任意後見人になるにはどうすれば良いか」「財産管理だけは専門家に任せたい」など、お客様の状況に応じて法律のプロが最適なプランをご提案いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
本記事に関する連絡先
TEL: 06-6253-7707
メールでのご相談はこちら >>