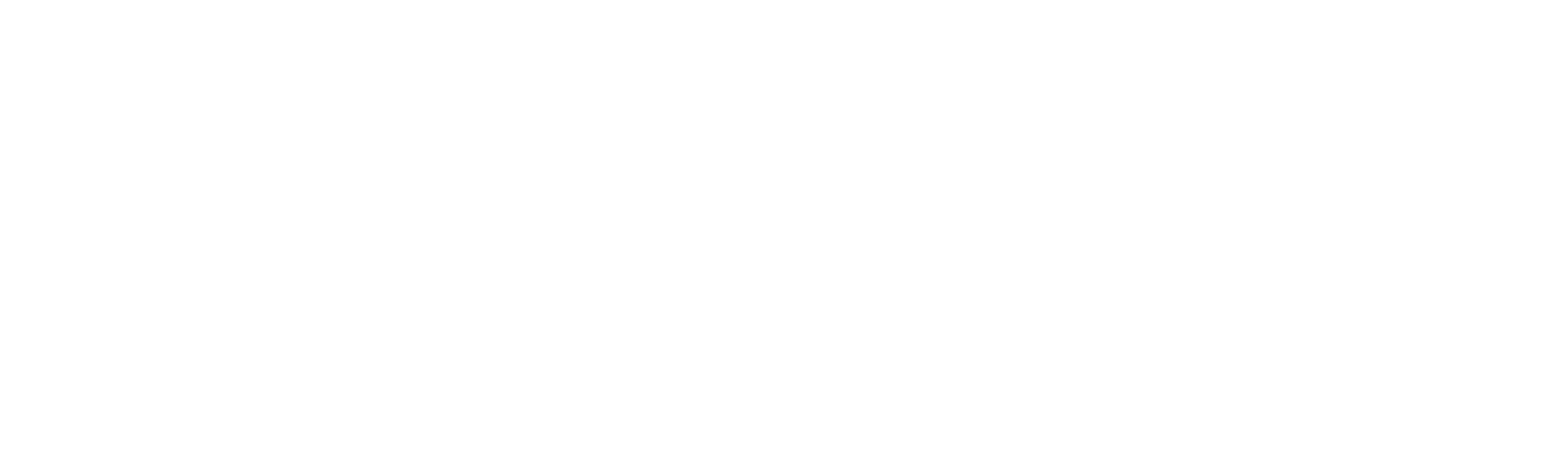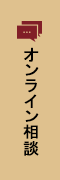知的資産の有効活用
その他
|更新日:2022.12.21
投稿日:2010.10.11
貴社の強みは何ですか?
このような質問をされたとき、何を思い浮かべますか?
ある方は、
- 土地や建物の保有数
- 純利益
- 流動比率が100%以上
- 固定長期適合率が100%未満
- 未収金が少ない
といったものを思い浮かべられると思います。
また、ある方は
- 技術力
- 社員教育システム
- 社長の人柄
- ブランド力
- 人材
- 営業ノウハウ
- 顧客とのネットワーク
といったものを思い浮かべられるかと思います。
それでは、今挙げられた「貴社の強み」を、適切に対外的にアピールしていらっしゃいますか?先程挙げた例のうち、前者は有形資産といわれるものです。
これらは貸借対照表や損益計算表に計上されるものですので、貸借対照表や損益計算表などを公表することで容易に対外的にアピールすることができます。
一方、後者は無形資産のうち知的資産といわれるものです。
これらは貸借対照表や損益計算表に計上されるものではありませんし、見えざる資産ですので対外的にアピールするためにはひと工夫が必要になります。
今回、これらの知的資産のアピール方法の一つとしてご紹介させていただきたいものは、経済産業省の「知的資産経営報告書」です。
「知的資産経営」とは、企業が自社の知的資産を認識し、それを有効利用することで収益につなげる経営方法のことです。
これにより、他社との差別化を図ることができるため、競争社会における優位性を確保することができるのです。
この方法であれば既に企業に内在する資源を利用するだけですので、新たに多額の資金を投じることなく経営改善・企業価値向上が可能となりうるのです。
そして、「知的資産経営報告書」とは、上記のような企業が有する技術、ノウハウ、人材など重要な知的資産の認識・評価を行い、それらをどのように活用して企業の価値創造につなげていくかを示す報告書です。
これは過去や現在における企業の価値創造過程を報告するだけでなく、 将来にわたっての価値創造の計画も示します。
企業の価値創造の流れを、将来的なものまで説明することによって、将来的な企業の価値を理解してもらうことができるため、有効なアピール方法となります。
従来の、財務諸表などを中心とした評価では、中小・ベンチャー企業の真の価値を知ってもらえないことがあると思います。
また、経営者にとっては周知のことであっても、取引先や金融機関、または社員などが必ずしもそれを知っているとは限りません。
「知的資産経営報告書」は、中小・ベンチャー企業が有する重要な知的資産を対外的に伝え、他社との差別化を図るためのツールとして大変有効なものなのです。
さらに、経済産業省によれば、「知的資産経営報告書」を作成することにより、
- 企業価値が増大する
- 経営資源が最適に配分される
- 従業員のモチベーションが向上する
- 知的資産への再投資が可能となる
- 資金調達が容易になる
というメリットがあるとされています。
さらに、各地方自治体の取り組みとして、たとえば京都府が「知恵の経営のススメ」として、「知恵の経営」報告書の作成による産業支援を行っています。
京都府では、京都「知恵の経営」ナビゲーターという支援スタッフを育成していたり、「知恵の経営」実践モデルの認証制度があったりと、積極的な活動が行われています。
ちなみに、認証を受けた企業や組合は、1企業につき8,000万円、利率2.0%といった融資制度を利用することができるようになっています。
今はまだ、一般的には知的資産についてそれほど認識されてはいません。しかし、一部の企業や金融機関ではすでに、有効活用を始めています。
競合他社が本格的な取り組みを始める前に、貴社の独自性をアピールする手法のひとつとして、あらためて現在の知的資産を認識しなおしてみるのも、企業の資産の有効活用につながると考えられます。
本記事に関する連絡先
TEL: 06-6253-7707
メールでのご相談はこちら >>