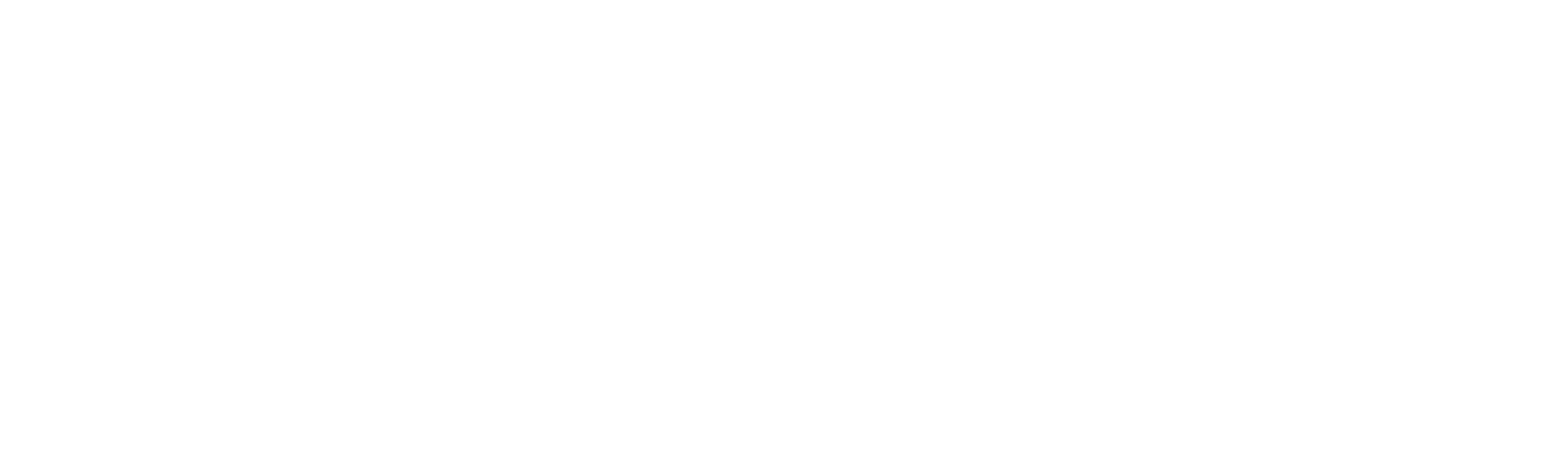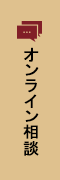<リスクマネジメント>下請法による規制と違反リスク
その他
|更新日:2022.12.1
投稿日:2011.10.04
下請法をご存知でしょうか
下請法とは、下請取引における親事業者の優越的な地位の濫用行為を規制するために制定された法律です。いわゆる親事業者による「下請いじめ」を禁止した法律です。
近年の景気低迷の中、親事業者が下請事業者に対して無理な要求をする事例が増えたことを背景に、規制の対象も広くなり、違反について公正取引委員会や中小企業庁による監視監督が強化されています。
下請法に違反すると
親事業者に故意や過失があった場合、民法上の不法行為による損害賠償責任も生じる可能性があります。
しかし、下請法違反の行為を公正取引委員会や中小企業庁が把握した場合には、故意や過失の有無を問わず、「勧告」や「指導」がなされます。
違反の程度が比較的軽い場合には、「指導」で済みますが、「勧告」がなされると、企業名や違反事実が公表され、これによる親事業者の社会的信用や評価低下という不利益を負います。
また、違反によって下請事業者に損害が生じた場合にはその損害を填補するというように違反前の状態に戻すことも勧告できるよう規定されており、措置は特に強化されています。
さらに罰則としては、最高50万円以下の罰金も規定されています。
調査のきっかけや今後の処分見込み
公正取引委員会や中小企業庁による調査や処分は、下請事業者からの申告のほか、下請取引に対して行っている定期的な書面調査の結果から違反が発見されるに至ったものが多いのが現状です。
監視監督はさらに強化され、これにより今後も下請法違反に対する処分が増えることが予想されます。
親事業者、子事業者どちらも、下請法においてどのような行為が規制されているのか、その内容を知ることで取引のリスクを低減する必要があります。
下請法の適用のある範囲とは
下請法の適用ある範囲は、第1に取引の種類によって区別され、第2に該当する種類に応じて下請法の規制の対象となる下請関係の事業者の規模が決められています。
その事業者の規模は、企業であれば資本金で判断されます。
役務提供委託では、あらゆる役務が対象となるので、注意が必要です。
製造委託(加工も含む)と修理委託
(親事業者)→(下請事業者)
資本金3億円超の企業 → 個人・資本金3億円以下の企業
資本金1千万円超
3億円以下の企業 → 個人・資本金1千万円以下の企業
情報成果物作成委託
(ソフトウェア開発委託や広告制作委託など)
役務提供委託
(自社が業として行う役務提供の委託)
(親事業者)→(下請事業者)
資本金5千万円の企業 → 個人・資本金5千万円以下の企業
資本金1千万円超
5千万円以下の企業 → 個人・資本金1千万円以下の企業
下請法による規制とは
下請法は、親事業者の行為について以下の規制をしています。
1.親事業者に義務づけていること
- 発注の際において法定書類の作成と交付
- 下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること
- 遅延した際の遅延利息の支払
- 法定の下請取引の内容を記載した書類の作成及び2年間の書類保存
2.親会社に禁止していること
- 受領拒否
- 支払遅延
- 下請代金の減額
- 返品
- 買いたたき
- 物の購入強制または役務の利用強制
- 報復措置
- 原材料などの代金の早期決済
- 割引困難な手形の交付
- 不当な経済的利益の提供の要請
- 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの強要
具体的な違反行為とは
実際になされている違反事例として多くみられるのは、下請代金減額です。具体的には以下のような事例です。
- 「早期決済奨励金」などという名目で、支払期日を早めたことを理由として下請代金に一定率を乗じた額を下請代金から減額すること
- 消費税を支払わない
- 下請代金の総額は変わらずに納入させる数量を増加
- 合意した引き下げ後の単価を、合意の前に遡って既に発注されているものまで新単価を適用
- 合理的な理由なく発注時に仮単価により発注し、後に正式単価を決定したことを理由に下請代金を減額
- 下請代金の端数を切り捨て
- 手形払から現金払に変更したによる減額
- 取引先からのキャンセルや市況変化等により不用品となったことによる減額
リスクマネジメントの対応策
下請法違反は、故意によって不当な下請取引を行った場合に限られません。故意や過失がなくても勧告や指導を受けるリスクはあります。
このようなリスクを避けるため、違反防止のためのコンプライアンス体制を確立することが必要と考えます。
具体的には、下請取引の際に下請法に適合した基本契約書を整備すること、下請法マニュアルやチェックリストの作成や配布をし、過程の整備を行うことなど、自社の規模と取引過程に応じた対応策を検討してみることがリスクマネジメントとして重要です。
本記事に関する連絡先
フリーダイヤル:0120-744-743
メールでのご相談はこちら >>