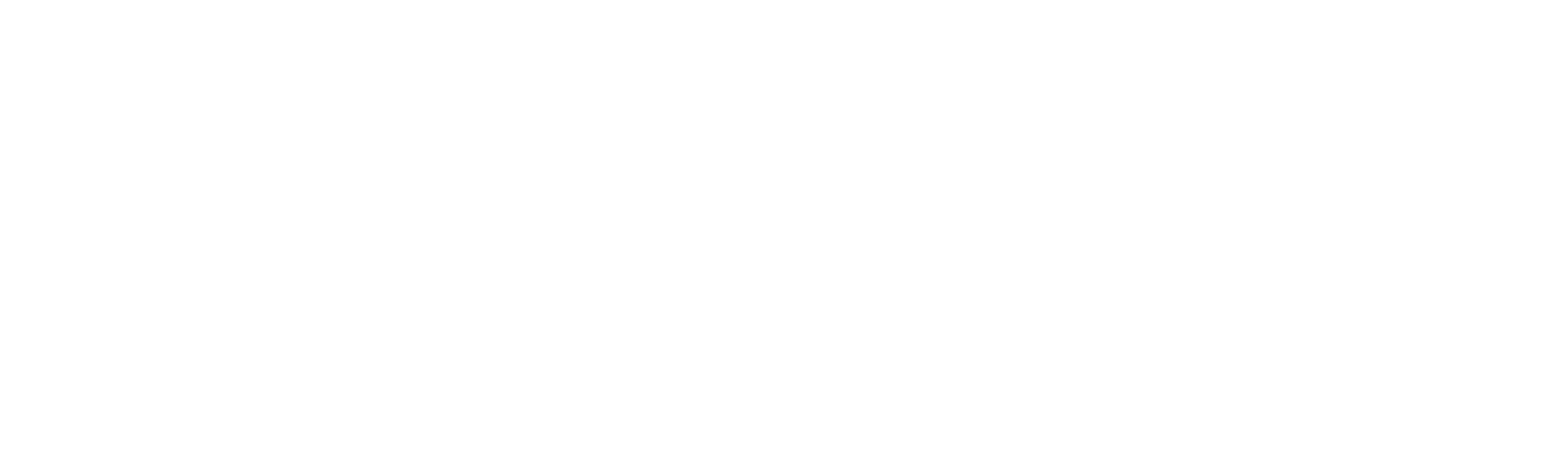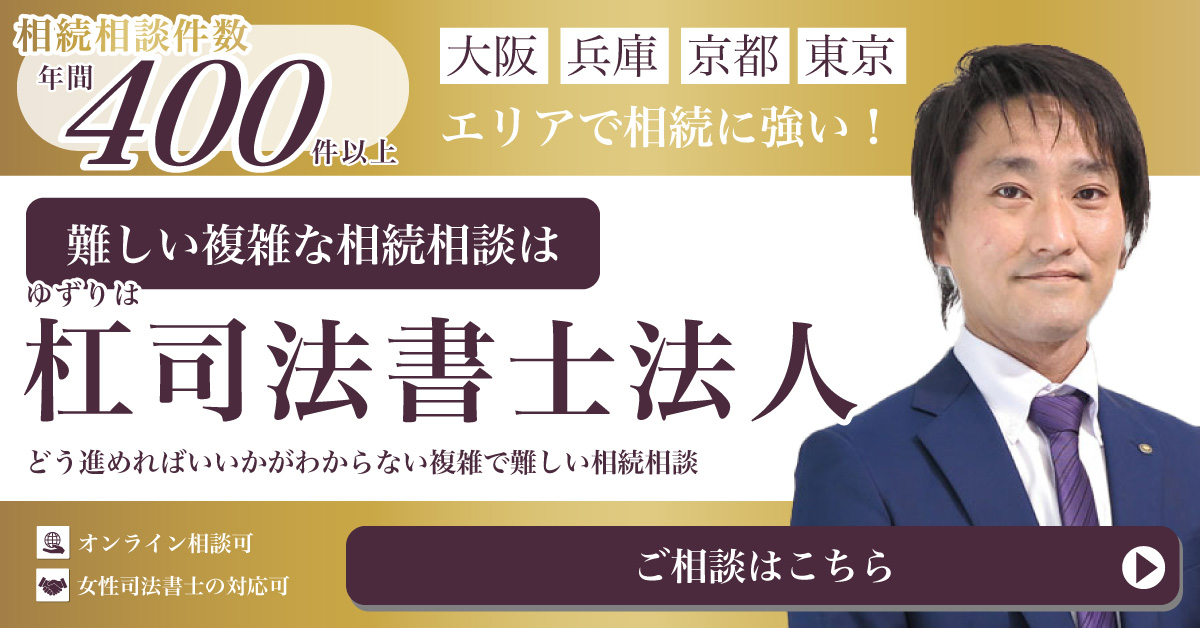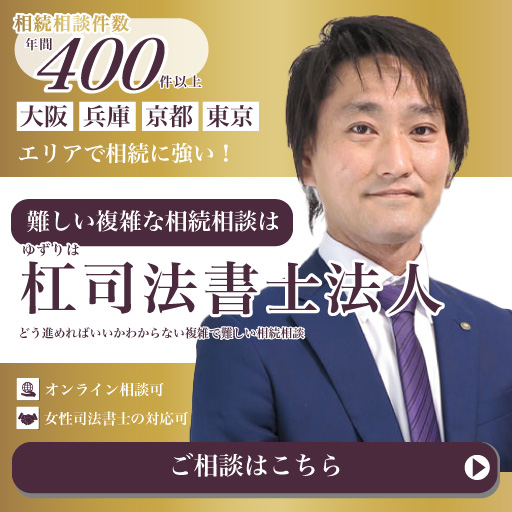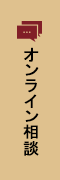兄弟姉妹が遺産相続することは可能?注意点やトラブル事例を解説
相続
投稿日:2025.04.28

亡くなった方に配偶者や子どもがいない場合、兄弟姉妹が遺産を相続することがあります。
しかし、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、必要な書類が多く、関係者も増えがちなため、一般的な相続よりも手間や時間がかかる傾向にあります。
また、血縁の薄さからトラブルが生じることも少なくありません。
この記事では、兄弟姉妹が遺産を相続する際に知っておきたい基本的なルールや注意すべきポイントなどをわかりやすく解説します。
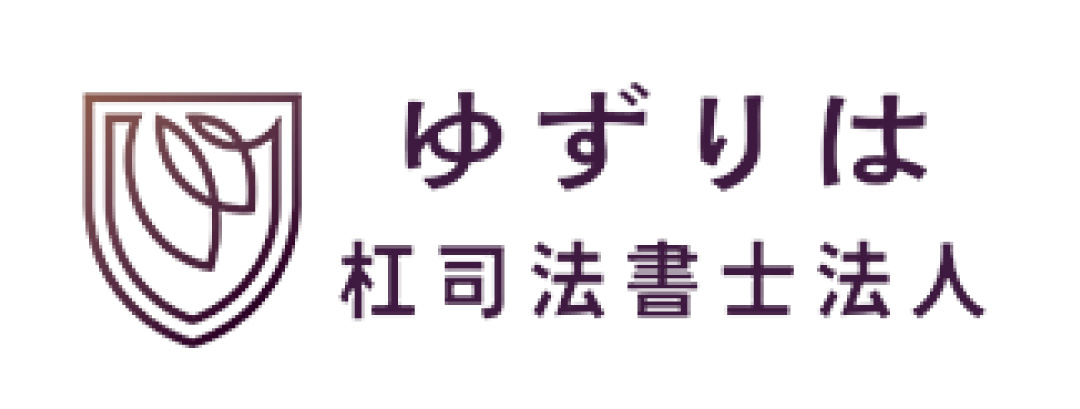
大阪・兵庫・京都・東京を拠点に、相続手続き・遺言書作成・家族信託契約などのサポートから企業法務まで、専門のチームで対応しております。税理士や他業種との連携により、相続問題をワンストップで解決!相続関連の相談件数は年間400件超。
目次
兄弟姉妹が遺産の相続人になるケース
亡くなった方(被相続人)の財産を誰が相続できるかは、民法により明確に定められています。
相続人として認められる人を「法定相続人」といい、血縁や婚姻関係の近さに応じて相続の優先順位が決まっています。
以下からは、法定相続人の範囲と順位について詳しく説明します。
法定相続人の範囲
法定相続人とは、民法で定められた遺産を引き継ぐ資格のある方です。
被相続人との関係性に応じて、以下の方々が該当します。
| 相続人 | 詳細 |
|---|---|
| 配偶者 | ・法律上の婚姻関係にある者 ・常に相続人になる |
| 子ども(直系卑属) | ・実子および養子 ・すでに亡くなっている場合は、その子(孫)が代襲相続する |
| 親(直系尊属) | ・父母または養親 ・子がいない場合に相続人になる |
| 兄弟姉妹 | ・子と親の両方がいない場合に限り相続人となる ・すでに亡くなっている場合、その子(甥や姪)が代襲相続する |
なお、内縁の配偶者(婚姻届を提出していない事実婚のパートナー)や離婚した元配偶者は、法律上の相続人とはなりません。
ただし、元配偶者との間の子は、実子として法定相続人となります。
このように、法定相続人の範囲には厳格なルールがあります。
法定相続人の順位
誰が先に相続するかという「相続の順位」も、法律によって以下の表のように定められています。
| 法定相続人 | 相続の順位 | 法定相続分の例(配偶者がいる場合) |
|---|---|---|
| 子ども(直系卑属) | 第1位 | ・配偶者:1/2 ・子ども:1/2(子が複数いる場合は均等に分ける) |
| 親(直系尊属) | 第2位 | ・配偶者:2/3 ・親:1/3 |
| 兄弟姉妹 | 第3位 | ・配偶者:3/4 ・兄弟姉妹:1/4(人数で均等に分ける) |
配偶者は常に法定相続人となりますが、それ以外の相続人(子、親、兄弟姉妹)は、相続の優先順位によって権利が発生しないことがあります。
たとえば、子どもがいる場合は親や兄弟姉妹に相続権はありません。
つまり、兄弟姉妹が相続人になるのは、「子どもも親もいない場合」に限られるということです。
これは兄弟姉妹が、相続の優先順位においてもっとも後ろに位置しているためです。
兄弟姉妹が遺産の相続人になる実例
兄弟姉妹が遺産を相続する立場になるケースとしては、以下のような状況が考えられます。
- ①相続人が兄弟姉妹しかいない
- ②相続人が配偶者と兄弟姉妹のみ
- ③兄弟以外の相続人がすべて相続放棄している
- ④兄弟姉妹に相続させると記載された遺言書が存在する
ここからは、被相続人が2,000万円の財産を遺して亡くなったケースを例に、各事例を詳しく解説します。
実例①:相続人が兄弟しかいない
被相続人に配偶者や子どもがなく、両親もすでに亡くなっている場合には、法定相続人は兄弟姉妹だけになります。
このような場合、兄弟姉妹の間で遺産を均等に分けることになります。
たとえば、相続人の兄弟姉妹が2人いる場合は、以下のように相続されます。
- 兄弟姉妹A:2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
- 兄弟姉妹B:2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
実例②:相続人が配偶者と兄弟のみ
被相続人に子どもがなく、親もすでに亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。
このケースでは、法定相続割合として配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合を取得し、兄弟姉妹の人数で均等に分ける形となります。
たとえば、兄弟姉妹が2人いる場合は以下のとおりです。
- 配偶者:2,000万円 × 3/4 = 1,500万円
- 兄弟姉妹A:2,000万円 × 1/4 × 1/2 = 250万円
- 兄弟姉妹B:2,000万円 × 1/4 × 1/2 = 250万円
実例③:兄弟以外の相続人がすべて相続放棄している
相続放棄をすると、その方は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、次に順位の低い相続人へと権利が移ります。
たとえば、被相続人に配偶者や子、親がいたとしても、そうした方々が全員相続放棄をした場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹が2人で、かつそれぞれ相続放棄をしていない場合の分配は以下のとおりです。
- 兄弟姉妹A:2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
- 兄弟姉妹B:2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
ここで注意したいのは、前提として、放棄の意思表示が家庭裁判所で正式に受理されていることです。
実例④:兄弟姉妹に相続させると遺言書に記載されている
遺言書が法的に有効であれば、その内容は相続手続きにおいて最も優先されます。
そのため、たとえ上位の法定相続人(配偶者や子など)が存在していたとしても、遺言書に「財産を兄弟姉妹に相続させる」と明記されていれば、兄弟姉妹が相続することが可能です。
ただし、配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)などには「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が法律で保障されています。
遺言書がその遺留分を侵害している場合、ほかの相続人から遺留分侵害額の請求(旧・減殺請求)がされる可能性があります。
そのため、遺言書を作成する際には、事前に専門家に相談し、遺留分に配慮した内容に整えることが大切です。
兄弟姉妹が遺産相続を行う流れ
兄弟姉妹が遺産相続を行う流れは、以下のようになっています。
- ①遺言書の有無を確認
- ②必要書類を収集する
- ③相続人を確定させる
- ④財産の調査
- ⑤遺産分割協議を行う
- ⑥相続登記を行う
- ⑦相続税の計算と支払い
以下からは、兄弟姉妹が遺産相続を行う際の基本的な7つのステップを詳しく解説します。
①遺言書の有無を確認
相続が発生したら、まず初めにすべきことは遺言書の有無の確認です。
遺言書は、被相続人(亡くなった方)の意思を反映する重要な法的文書であり、法定相続よりも優先される効力があります。
遺言書が存在するかどうかで、手続きや遺産分割の方法が変わるのです。
遺産分割が済んだ後に遺言書が発見されると、手続きが無効になる可能性や、やり直しを迫られるケースもあります。
そのため、相続が開始したら早い段階で、家族全体で遺言書の有無を調べることが重要です。
②必要書類を収集する
兄弟姉妹が相続人になる場合、ほかのケースと比べて書類収集が煩雑になります。
理由は、自分たちより相続順位が上の人物(子や親など)がすでに亡くなっていることを証明しなければならないからです。
たとえば、被相続人に結婚歴が複数ある、養子縁組をしているなど、家族構成が複雑な場合は、さらに多くの戸籍謄本が必要になることもあります。
以下は、代表的な必要書類の一覧を表にまとめたものです。
| 書類名 | 取得先 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本) | 本籍地の市区町村役場 | 生まれてから亡くなるまでのすべてが必要 |
| 住民票の除票 | 住所地の役所 | 除票は死亡後に取得でき、住所の証明になる |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 相続関係を証明するために必要 |
| 相続人全員の住民票 | 住所地の役所 | 財産の名義変更等に使用 |
| 父母・祖父母の戸籍謄本(除籍) | 本籍地の役所 | 直系尊属が既に亡くなっていることを証明する |
なお、兄弟姉妹が相続人となる場合には、10通以上の戸籍を集めることが必要になる場合もあります。
想定以上に時間がかかることがあるため、できるだけ早く収集を始めることが重要です。
③相続人を確定させる
必要書類をもとに、誰が法定相続人であるかを正確に確定します。
相続人の確認は、遺産分割や税金の計算にも影響するため、正確性が極めて重要です。
④財産の調査
被相続人が所有していた財産の内容をプラスの財産・マイナスの財産を含めて調査します。
プラスの財産の例は、以下の通りです。
- 預貯金
- 不動産(自宅・土地)
- 株式・投資信託などの金融資産
マイナスの財産の例は、以下の通りです。
- 借金
- ローン残債
- 未払いの税金・医療費等
マイナスの財産のほうが多い場合には、相続放棄という選択肢もあります。
相続放棄は原則として、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるため注意しましょう。
不動産が複数にまたがる場合や、所在不明な資産がある場合は、財産調査に数か月以上かかることもあります。
相続人同士で分担して調べたり、専門家に依頼したりするなどの対応がおすすめです。
⑤遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどう分けるか話し合う場です。
話し合いの内容がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・押印します。
なお、遺言書が存在し、内容に異論がなければ協議は不要なケースもありますが、遺言書の解釈を巡って争いになる場合もあるため、専門家に聞くなどして協議書を作成しておくと後々のトラブルを回避できます。
⑥相続登記や名義変更を行う
遺産の中に不動産や有価証券、銀行口座などが含まれている場合、それぞれの名義変更手続きが必要です。
特に不動産の場合、2024年4月1日から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければならないと法律で定められました。
これに違反すると、10万円以下の過料を科されることがあります。
そのため、不動産のある相続では、遺産分割協議後は速やかに登記手続きを進めることが重要です。
⑦相続税の計算と支払い
相続財産の金額が基礎控除額を超えている場合は、相続税の申告と納税が必要です。
基礎控除の計算式は、以下の通りです。
| 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
また、兄弟姉妹が相続人となる場合、相続税額が2割加算される規定があります。
これは、配偶者や直系の子・孫以外が財産を受け取るときに適用される措置です。
相続税の申告・納税には、「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」という明確な期限があります。
この期限を超えると、加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があるため注意しましょう。
兄弟姉妹が遺産を相続する際の注意点
兄弟姉妹が相続人となる場合、以下のように、一般的な相続とは異なる注意点が存在します。
- 兄弟姉妹の代襲相続は一代までしか適応できない
- 相続税が2割加算される
- 必要書類の収集に手間がかかる
ここからは、この3つのポイントについて詳しく見ていきましょう。
兄弟姉妹の代襲相続は一代までしか適応できない
代襲相続とは、本来相続人となるはずの方が先に亡くなっていた場合、その人の子どもが代わりに相続する制度です。
たとえば、被相続人の兄がすでに亡くなっている場合、その兄の子、つまり被相続人から見て甥や姪が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続が認められるのは甥・姪までで、それより下の世代には相続権が引き継がれません。
つまり、代襲は一代限りと定められており、再代襲相続(代襲のさらに代襲)はできないという点に注意が必要です。
相続税が2割加算される
兄弟姉妹が遺産を相続する場合、相続税が通常よりも2割多く課税される可能性があります。
これは、「相続税額の2割加算制度」と呼ばれ、被相続人の配偶者・直系血族(父母・子)以外の人が相続する場合に適用される制度です。
具体的には、以下のような人が対象になります。
- 被相続人の兄弟姉妹
- 被相続人の孫(ただし、子が健在なのに孫が養子として相続する場合)
- 内縁の配偶者や第三者
このため、たとえば遺産が同じ2,000万円でも、子が相続する場合と兄弟姉妹が相続する場合とでは、兄弟姉妹のほうが納める相続税が多くなるという結果になります。
節税対策を行う際には、この2割加算の制度を必ず考慮に入れておきましょう。
必要書類の収集に手間がかかる
兄弟姉妹が相続人となるには、被相続人に上位の法定相続人(配偶者・子・親など)がいないことを証明する必要があります。
この証明のために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集しなければならず、加えて親・祖父母・兄弟姉妹など、関係する全ての戸籍を揃える必要があるケースもあります。
特に、以下のような事情がある場合、必要書類の量と収集の難易度が高くなります。
- 被相続人に複数の婚姻歴がある
- 養子縁組が行われている
- 兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいる(その子への代襲相続が発生)
書類の取得には時間がかかるうえ、役所によっては郵送や委任状が必要なこともあるため、早めの対応が必要です。
もし、ご自身での収集に不安がある場合は、司法書士や行政書士といった専門家に依頼することも視野に入れましょう。
兄弟姉妹が遺産の相続人になる際によくあるトラブル事例
兄弟姉妹が遺産を相続する場面では、親子間の相続とは異なる特有のトラブルが起こりやすくなります。
実際によく見られるトラブル事例として、次の5つが挙げられます。
- 介護をしていた兄弟が取り分を要求してきた
- 絶縁している兄弟と連絡がつかない
- 分配しづらい財産が多い
- 知らない兄弟がいることが判明した
- 財産の全容が把握できない
ここからは、それぞれに対する注意点や対処方法について解説します。
介護をしていた兄弟が取り分を要求してきた
相続人の中に、長年にわたり被相続人の介護をしていた方がいる場合、「介護した分を多くもらいたい」と主張されることがあります。
法的には、「特別の寄与(寄与分)」として、相続分に上乗せされる制度もありますが、実際に認められるには要件が厳しく、必ずしも介護が寄与分として認められるとは限りません。
ただし、感情的な衝突や誤解を生まないよう、介護の実態や負担の程度を正確に共有し、ほかの相続人と丁寧に話し合うことが重要です。
必要に応じて、専門家を交えて協議しましょう。
絶縁している兄弟と連絡がつかない
長年交流のなかった兄弟姉妹が法定相続人となった場合、連絡が取れずに相続手続きが進められないケースがあります。
遺産分割には全相続人の参加と同意が必要なため、1人でも連絡がつかないと、手続き全体が停止してしまうことがあります。
そのような場合は、ほかの相続人の戸籍の附票(住所の履歴を記載した書類)を取得して所在を調査する、あるいは家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる方法があります。
ただし、対応を誤ると感情的な対立や法的紛争に発展する恐れもあるため、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けるのが望ましいです。
分配しづらい財産が多い
不動産や絵画・宝石といった「分けにくい財産」が遺産の大半を占めていると、兄弟姉妹間での分割方法をめぐって争いが起こることがあります。
法定相続分は「均等」と定められていますが、物理的に均等に分けられない場合、一部の相続人が不動産を相続し、ほかの相続人に「代償金(かわりの金銭)」を支払う方法などで調整することになります。
ただし、代償金の準備が難しいと、新たな問題に発展することも。
可能であれば不動産の売却を検討し、現金化して平等に分けるなど、現実的な選択肢も視野に入れましょう。
知らない兄弟がいることが判明した
戸籍をたどる過程で、存在を知らなかった異母(または異父)兄弟の存在が明らかになるケースもあります。
たとえば、被相続人に過去の婚姻歴があり、その際の配偶者との間に子どもがいた場合などが該当します。
このような兄弟姉妹も法律上の法定相続人として、当然に相続権を持つのです。
ただし、父母が共通していない「半血兄弟姉妹」の法定相続分は、両親が共通している兄弟姉妹の半分になります。
存在が知られていなかった兄弟と連絡を取り、相続の説明を行うには時間と労力がかかるため、可能であれば専門家に依頼するのが現実的です。
財産の全容が把握できない
遺産相続では、被相続人がどれだけの財産や負債を残していたかを正確に調べる必要があります。
しかし、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、日ごろから財産状況を把握していなかった可能性が高く、以下のような状況に陥りがちです。
- 銀行口座が複数あるが、通帳やキャッシュカードの所在が不明
- 不動産があるかどうか確証がない
- 借金・ローンの有無がわからない
- 生命保険や証券口座などが名義のまま放置されている
このように、財産の種類や範囲がわからないと、相続の手続きそのものが進まず、相続人間で疑念や不信感が生じるきっかけになります。
また、負債があった場合、それに気づかず相続を進めると、相続人が返済義務を負う可能性もあるでしょう。
そのため、被相続人の郵便物や通帳、証券会社・保険会社からの通知などを整理し、可能な限り情報を洗い出す必要があります。
財産調査が難航する場合は、司法書士などの専門家に依頼することで、漏れなく把握できることもあります。
遺産相続のご相談なら杠(ゆずりは)司法書士法人まで
今回は、兄弟姉妹が遺産相続の当事者になる場合の制度や注意点、トラブル事例について詳しく解説しました。
兄弟姉妹は法定相続人の中でも第三順位と定められています。
しかし、実際に相続が発生する場面では多くの手続きや確認事項が求められます。
初めて相続に関わる方にとっては、そうした複雑な作業を一つひとつ正確に進めていくのは大きな負担となります。
杠(ゆずりは)司法書士法人では、こうした相続にまつわるさまざまなお悩みに対し、豊富な経験と知識をもとに、丁寧かつ的確にサポートいたします。
「何から始めたらいいのかわからない」「手続きが煩雑で不安」といったお困りごとをお持ちの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
一人ひとりの状況に合わせて、最適な解決策をご提案させていただきます。
本記事に関する連絡先
TEL: 06-6253-7707
メールでのご相談はこちら >>