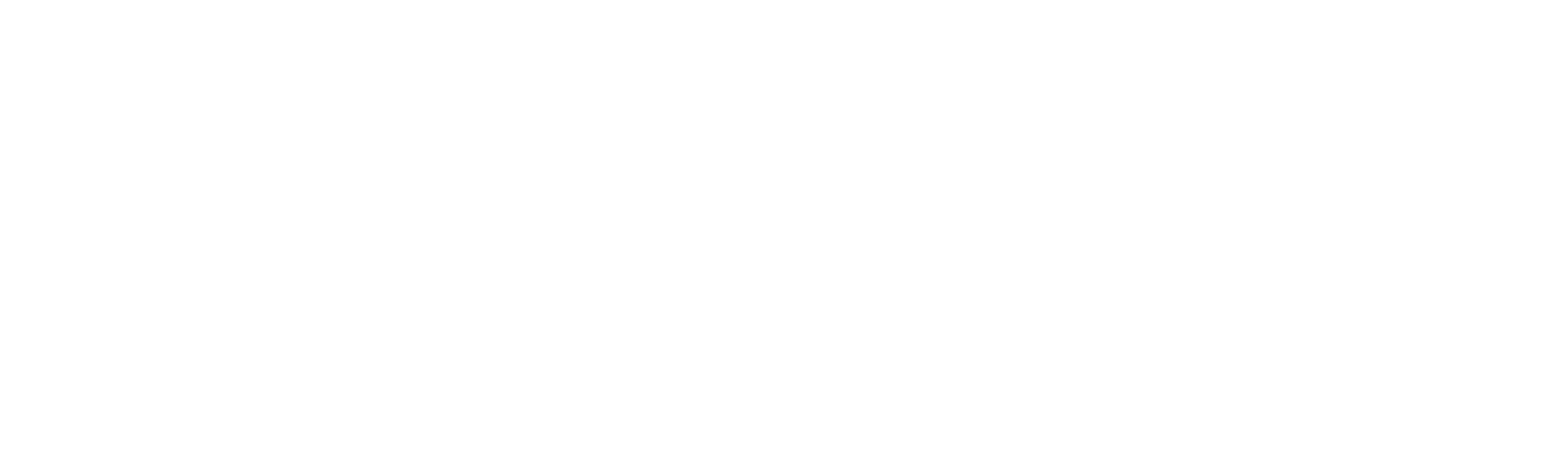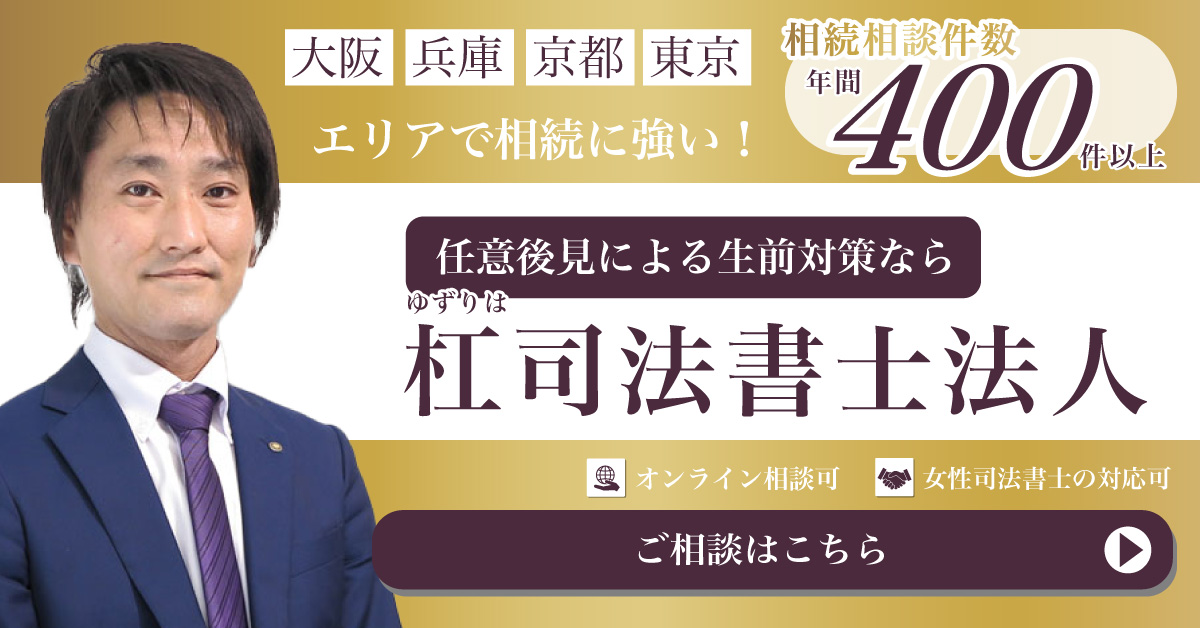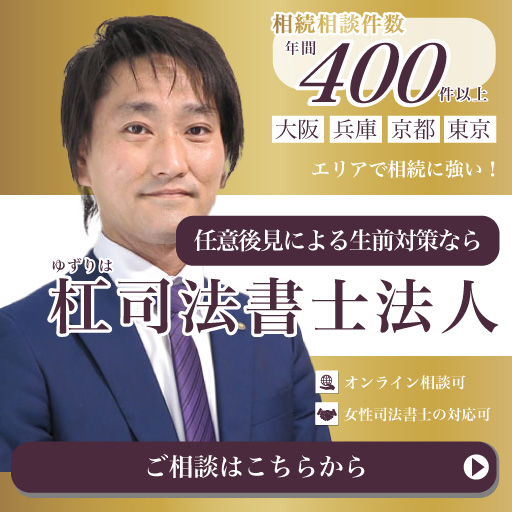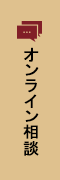任意後見契約を補う見守り契約|基本知識や報酬について解説
成年後見
投稿日:2025.02.27

将来、判断能力が低下したときのために、任意後見契約を結んでおこうと考えている方もいるでしょう。
しかし、任意後見契約だけでは、全ての状況に対応できるわけではありません。
そこで利用されるのが「見守り契約」です。見守り契約は、任意後見契約と併せて利用することで、より安心した老後を送ることができます。
この記事では、見守り契約の基礎知識からメリット、報酬まで詳しく解説します。
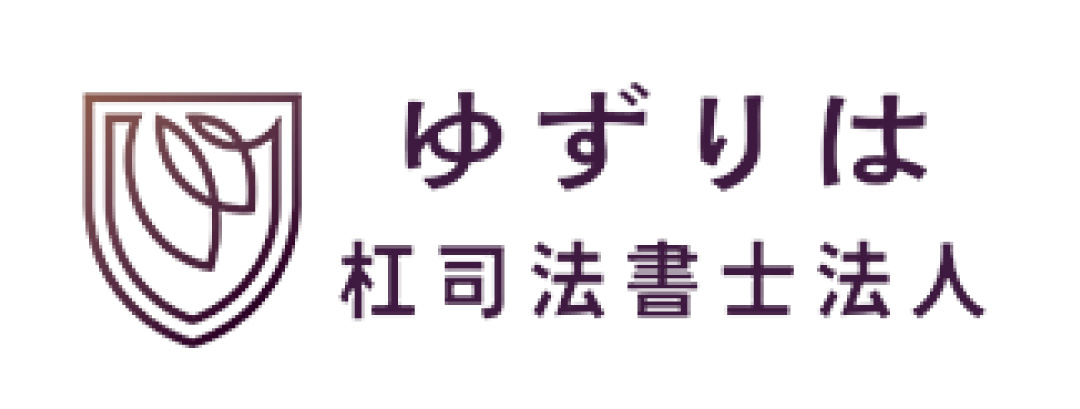
大阪・兵庫・京都・東京を拠点に、相続手続き・遺言書作成・家族信託契約などのサポートから企業法務まで、専門のチームで対応しております。税理士や他業種との連携により、相続問題をワンストップで解決!相続関連の相談件数は年間400件超。
目次
任意後見契約を補う「見守り契約」
見守り契約は、任意後見契約とセットで契約することで、将来起こり得るいろいろなトラブルを回避できる契約です。
特に、一人暮らしの高齢者を中心に活用されています。
契約当事者(高齢者)と司法書士などが契約を結び、対象者の心身を伴う健康状態や生活状態を見守りながら把握します。
今の世の中、何が起こるか予想できません。
年の経過とともに認知機能が衰え、若いころと同じような判断ができない可能性もあります。
見守り契約は識別力が衰えるまでの期間、本人の状態を見守り、任意後見契約へとスムーズに運ぶためのシステムです。
任意後見契約が始まるまでの間に利用するのが効果的です。
見守り契約の内容
「見守り契約のひな形ってあるの?」「見守り契約にかかる費用はいくら?」など気になっている方もいるでしょう。
しかし、見守り契約はオーダーメイドの契約であることが多く、基本的には契約内容を当事者が自由に決められます。
見守り契約では、以下のような内容を盛り込むことができます。
- どのような方法でどの程度の頻度で連絡を取り合うのか
- どこで会って話をするのか
- 契約者の健康状態を把握し、どのタイミングで任意後見管理人の申立てをするのか
- 緊急連絡先として任意後見受任者を指定するという取り決め
- 入院の手続きを任意後見受任者に依頼するという取り決め
希望する内容に伴って費用も変わってきます。
たとえば、月に直接会う場合や電話でやりとりする場合など、継続的にサポートするための労力の違いによって費用が異なります。
任意後見の申立ての時期の見計らいや、面談などの労力に応じて費用を決定するのが一般的です。
見守り契約を依頼できる人
見守り契約は、基本的に後見業務を行っている司法書士等の専門家に依頼するケースが多いです。
任意後見契約をスタートさせるまでの間、契約者の状況を見守りつつ、いつ契約を開始するか見極めるのが見守り契約です。
親族と一緒に生活している方や親族の方が近くにいる場合は、基本的に必要ないケースが多いでしょう。
もちろん、家族間でトラブルが起こるのを事前に防ぎたい場合は、信頼している親族の方に依頼することも可能です。
見守り契約が終了するとき
見守り契約が終了するタイミングは、下記の通りです。
- 任意後見契約が発動したとき
- 契約者本人が死亡したとき
- 法定後見・保佐・補助の審判を受けたとき
- 任意後見契約自体を解約したとき
- 見守り契約自体を解約したとき
見守り契約は、任意後見契約とセットで契約されるものです。
任意後見契約自体を解約したときや任意後見契約が発動した段階で、法的に終了するように設計されます。
また、本人が死亡したり、法定後見・保佐・補助の審判を受けたりするなどの自体が生じたときも見守り契約は終了します。
もちろん、見守り契約を結んだ後に親族と一緒に暮らすようになったなど状況が変わることもあるでしょう。
信頼できる親族が近くにいることで、見守り契約が必要なくなった場合は解約することも可能です。
見守り契約を利用するメリット
見守り契約は任意後見契約を考慮する際にセットで勧められることが多いため「見守り契約って本当に必要?」「見守り契約を利用すると何が良いの?」と考える方もいるでしょう。
見守り契約を利用することで、以下のようなメリットがあります。
- 将来に備えて信頼関係を築ける
- 健康状態や生活状況を定期的に確認してもらえる
- 困ったときに相談に乗ってもらえる
見守り契約を利用するメリットについて具体的に考えましょう。
将来に備えて信頼関係を築ける
見守り契約は、単なる契約手続きにとどまらず、将来に備えて信頼関係を築くための重要な機会です。
契約期間中、契約者と担当者(担当事務所)は、定期的な連絡や訪問を通じて、密接な関係を築くことができます。
判断能力が十分にある今のうちに担当者と直接コミュニケーションを取ることで、その人の能力や誠実さをしっかりと見極めることができるでしょう。
自分が認知症になった場合、死ぬまで関係が継続するので信頼関係はとても重要です。
将来的に自分の判断力が弱った場合でも「この人になら任せられる」「法律に基づいて、しっかりと仕事をしてくれる」など信頼関係があれば、安心して業務を任せられるでしょう。
健康状態や生活状況を定期的に確認してもらえる
見守り契約をすると、契約者の心身の健康状態や生活状況などを見守ってもらえます。
たとえば、いつも家をきれいに片付けていたのに、急に部屋が散らかってきたりゴミ屋敷になったりすることもあるでしょう。
また、聡明でテンポよく会話していた方や、博識があり興味深い会話を展開していた方が急に同じ内容を繰り返したり、会話が噛み合わなくなってきたりすることも出てきます。
さらに、一人暮らしの寂しさから心に影響が出ることも少なくありません。
見守り契約で、担当者に自分の生活スタイルを見てもらっていると、ちょっとした変化に気づいてもらいやすくスムーズな対応をしてもらえます。
誰かが見守ってくれていることが分かっていると、安心して穏やかな生活を送れるでしょう。
困ったときに相談に乗ってもらえる
見守り契約をしていると、担当者(担当事務所)と定期的にコンタクトを取ります。
自分の問題や悩み事がある場合、相談に乗ってもらえる機会が多いでしょう。
たとえば、「状況が変化したので、見守り契約や任意後見契約の見直しをしたい」「やっぱり見守り契約を終了したい」という場合でも、相談に乗ってもらえるため安心です。
また、一人暮らしをしていると、相談したいことがいろいろと出てくる可能性も否定できません。
見守り契約を通じて、担当者との信頼関係を築くことで、日々の生活に関する悩みや将来への不安などを気軽に相談できるようになります。
見守り契約の報酬
見守り契約の報酬は、契約内容によって異なります。
「どのような契約内容にしたのか」「公正証書として契約書を発行するのか」などによっても値段が変わってきます。
見守り契約の契約書の発行には5万円ほどかかりますが、公正証書として発行する場合、2〜3万円ほど契約書発行費用が別途で必要なケースも。
ただし、公正証書として発行した場合、契約の内容を変更するごとに公正証書を発行しなければなりません。
見守り契約の内容は、ライフスタイルの変化によって変更する可能性が高いことを考えると、変更するたびに再発行するのは面倒です。
手間も考慮に入れて、公正証書を発行するか決めましょう。
また、月々3,000円〜1万円ほどの継続費用もかかります。
見守り契約後、実際に電話をかけたり、訪問したりして連絡を取るのにかかる労力や時間に対する費用です。
見守り契約の内容によって費用が変動することを覚えておきましょう。
見守り契約でできないこと
一人暮らしをしている高齢者は、何かと不安がつきまとうもの。
「自分でも気づかないうちに認知症になっていたらどうしよう」「自分はこのまま一人暮らしをしても大丈夫なのだろうか?」「近くに家族がいないから不安」などと感じる方も少なくありません。
そのような方にとって、身守り契約の制度はとても心強いでしょう。
しかし、見守り契約でも対応できないことがあります。
できることとできないことの区別をしっかり理解しておくと、見守り契約の内容に満足しやすいはずです。
見守り契約でできないことについて見ていきましょう。
身の回りの世話
見守り契約の目的はあくまで、当事者が滞りなく生活できているかを見守ることです。
契約内では、本人と電話したり実際に訪問したりすることはできますが、身の回りの世話をすることはできません。
毎月コミュニケーションを取り、信頼関係が築けてくると、契約者からちょっとしたことを頼みたいと思う方もいるでしょう。
たとえば「自宅に訪問するついでにスーパーで買い物をしてきてほしい」「自分の代わりに銀行で手続きをしてきてほしい」などです。
特に、高齢者は体力の低下と共に歩くのも難しいと感じることも多く、スーパーや銀行に行ったりちょっとした用事を済ませたりするのが難しいと感じることも。
そのようなときに、自宅に来るついでに頼みたいと思うのもうなずけます。
しかし、このような依頼は見守り契約の範囲を超えているためできません。
特に銀行での手続きは委任状がなければ対応してもらえないので、財産管理等委任契約が別途必要です。
判断能力低下後の対応
見守り契約は当事者の判断力が低下するまでの間、生活を見守ることなので、実際に判断能力が低下した後の対応はできません。
判断力が低下した後は後見制度で対応します。
後見制度は法定後見と任意後見に分かれていますが、法定後見人は家庭裁判所が選任し、任意後見人は本人が前もって決めています。
後見人がその後の対応を行うので、見守り契約と任意後見契約はセットで契約することが多いです。
どちらにしても、見守り契約の担当者は自動的に後見人にはなれないことを理解しておきましょう。
亡くなった後の手続き
急な病気や事故などで、本人が亡くなる可能性もあります。
身守り契約では、本人が亡くなった後の手続きはできません。
人が亡くなった場合、死亡診断書の受取と提出・病院への支払い・葬儀と納骨・公共料金の支払いや解約などさまざまな手続きが必要です。
死後のさまざまな手続きを依頼したい場合は「死後事務委任契約」を結ぶと良いでしょう。
見守り契約以外の任意後見契約を補う契約
見守り契約では契約者本人の生活を見守ることしかできません。
もちろん、認知症になっていないか、心身ともに健康に暮らせているかを見守ることも大切です。
しかし、本当に助けが必要になった場合に行動してもらうためには「財産管理委任契約」や「死後事務委任契約」などを併用することも考えましょう。
2つの契約について具体的に解説します。
財産管理委任契約
財産管理委任契約を結んでいると、自分の財産の一部(もしくは全部)を、代理人に管理してもらうことが可能になります。
財産管理の一例は、次の通りです。
- 日常的な貯金の管理
- 収入支出の管理
- 賃貸物件の管理
- 銀行の手続き
- 公共料金の支払い
法的に、委任者のキャッシュカードを預けることができるようになります。
そうなれば、「年金の支払日に手続きしてきたいけど、足が痛いから歩いて行くのは難しい」「家に訪問するついでに銀行からお金を引き出してきてほしい」などの状況でも、対応が可能です。
見守ってもらうだけでなく、実際に必要なことを助けてもらえます。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、亡くなった後の手続きをしてもらうための契約です。
亡くなった方は自分で手続きができないので、誰かが代わりにしなければなりません。
家族が同居している場合は代わりに行いますが、一人暮らしの方で家族が近くにいない場合や疎遠になっている場合に有効な制度です。
人が亡くなった後は、市区町村役場へ届け出たり、医療費を支払ったり、遺品整理をしたり、家賃や高熱料金を停止したりとさまざまな手続きが必要です。
自分が亡くなる前に第三者に死後事務を依頼することで、死後の手続きが滞りなく進みます。
見守り契約や任意後見に関するご相談は杠(ゆずりは)司法書士法人まで
今回は見守り契約について考えました。
見守り契約は、契約者の判断力が低下するまでの間、滞りなく生活を送れているか見守るための制度です。
多くの場合、任意後見契約とセットで検討します。
見守り契約を結ぶことで、判断力がある間に担当者(担当事務所)との間に信頼関係を築けるので、より安心して生活ができるでしょう。
また、「財産管理委任契約」や「死後事務委任契約」を併用すれば、見守り契約と共に助けを得られたり、死亡した場合に備えたりすることが可能です。
杠司法書士法人は、豊富な知識と経験を持っています。
専門家としての対応はもちろん、人として契約者様と寄り添い「よりどころ」となるように心がけています。
コミュニケーションに重きを置き、ずっと続く安心をモットーに仕事をしていますので安心してお任せください。
フリーダイヤルでもお問い合わせフォームでも対応していますので、ご気軽にお問い合わせください。