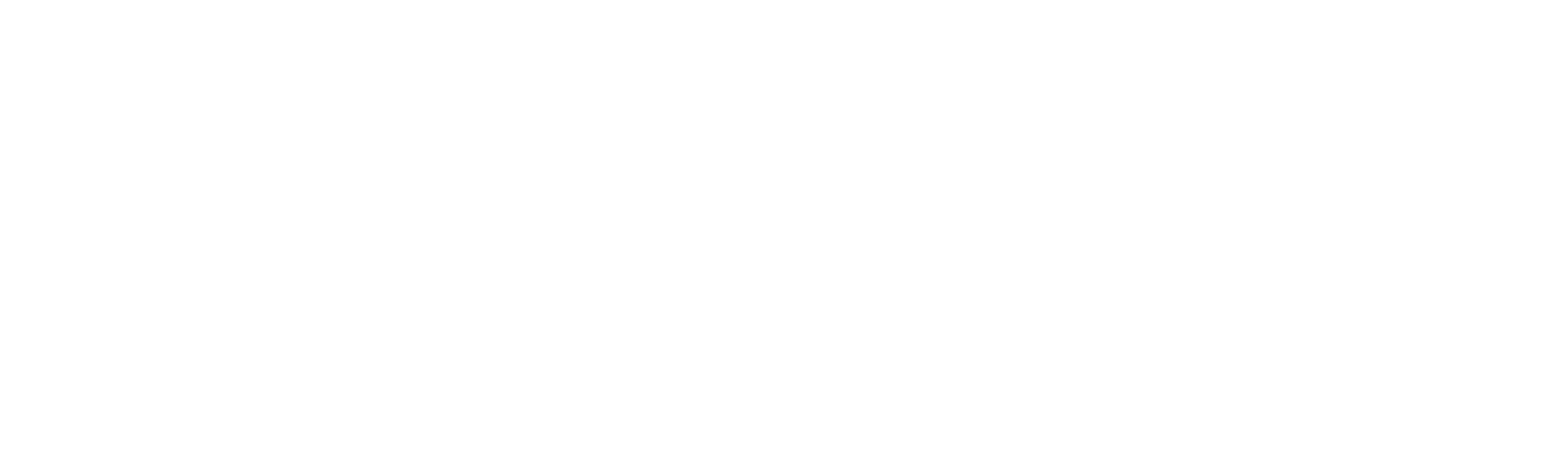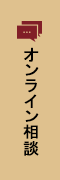任意後見を司法書士に依頼したときの費用は?手続きの流れも紹介
成年後見
投稿日:2025.02.27

将来、判断能力が低下した際に「自分の財産や生活のサポートを誰かにお願いしたい」と考える方は多いのではないでしょうか。
そのようなときに役立つのが、任意後見制度です。任意後見は、親族だけでなく司法書士といった専門家に依頼することもできます。
しかし、「費用はどのくらいかかるのだろう」「実際の手続きはどのように進むのだろう」と気になることも多いはず。
この記事では、任意後見を司法書士に依頼する際の費用や手続きの流れについて詳しく解説します。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人の判断力がまだしっかりしている間に自分の財産管理を任せたい人、いわゆる「後見人」を自分の意思で選んで任意後見契約を結ぶ制度です。
任意後見契約を締結しておけば、本人の判断力が低下した時点で直ちに後見が開始できます。
任意後見制度の主な特徴をピックアップしてみました。
- 判断力があるうちに自分の意思で後見人を決められる
- 家族や友人以外にも弁護士や司法書士、社会福祉士にも依頼できる
- 本人の判断能力低下が認められた後に任意後見監督人が選任されて契約がスタートする
- 任意後見人には取消権はない
- 任意後見人の解任を求めることができるのは本人、任意後見監督人、親族、検察官のみ
- 任意後見契約は公正証書にて締結される
任意後見契約を締結すると、本人の財産管理や法律上の代理人としての役割を果たすことになるため、老人ホームへの入所手続きなどの法律行為ができるようになるメリットがあります。
一方で、死後の財産管理ができないことや取消権が認められていないことなどがデメリットです。
ほかの制度と併せたフォローを考える必要があります。
任意後見制度のメリット
任意後見人制度を利用する主なメリットは、以下の通りです。
- 自分で後見人を指名できる
- どの範囲で支援してもらうかを決められる
- 任意後見人の業務内容をチェックしてもらえる
それぞれの内容について詳細を説明します。
自分で後見人を指名できる
任意後見制度では自分が元気なうちに信頼する人を後見人として指名できるというメリットがあります。
任意後見制度と法定後見制度の大きな違いは、自分で後見人を選べるか否かという点です。
法定後見制度では、家庭裁判所の判断の元に縁のない弁護士や司法書士が後見人に指定されるケースも多いです。
法定後見人は幅広い代理権を持っており、家族の同意なしに本人の財産を管理できます。
任意後見制度では本人が選んだ後見人と公正証書にて契約を締結し、家庭裁判所が後見人を変更できない仕組みになっています。
どの範囲で支援してもらうかを決められる
任意後見人の権限は任意後見契約を締結する際に、本人の意思で自由に決められます。
これは法定後見人にはない大きなメリットです。
将来利用することになるかもしれない介護施設や病院の選択から具体的な治療や介護サービスの内容、財産管理と保護に関すること、後見人の報酬まで全てにおいて制限はありません。
一方、法定後見の場合は民法にて権限内容が定められています。
補助する人の権限内容は本人の状態に応じて個別に設定できるところもありますが、基本的には家庭裁判所の判断が必要です。
任意後見人の業務内容をチェックしてもらえる
任意後見制度では、家庭裁判所によって任意後見監督人が選出されます。
任意後見監督人とは、任意後見人が契約の内容通りに業務を行っているか、チェックする役割を担う人です。
任意後見監督人は任意後見人から財産目録の提出を求めたり、定期的な報告を受けたりしながら後見制度の内容を細かく確認します。
任意後見人の状況次第では、任意後見監督人が任意後見人の代わりを務めることも可能です。
任意後見監督人によるチェック機能は、任意後見制度の大きなメリットの一つです。
任意後見制度のデメリット
任意後見人制度を利用するうえで考えられるデメリットを3つピックアップしました。
- 任意後見人に取消権はない
- 本人の判断能力が低下した後からでは利用できない
- 死後の事務を依頼できない
それぞれの項目について詳細を説明します。
任意後見人に取消権はない
任意後見制度では、本人の行動を取り消す取消権が与えられていません。
たとえば、本人の判断能力の低下によって思わぬ高額商品を購入してしまった場合でも、任意後見人には取り消す権利がないということです。
成年後見人は原則として取消権がありますが、任意後見制度は本人の自主性を重んじる制度ということもあり、簡単には取り消しできない決まりが定められています。
例外的に任意後見契約の代理権目録に取消権の行使に関する記載がある場合において、詐欺や脅迫に騙されて契約してしまったといった特定の状況下では、契約を無効にすることができます。
ただし、成年後見人ほどの権限は与えられていません。
本人の判断能力が低下した後からでは利用できない
任意後見契約が締結できるタイミングは、本人の判断能力があるときに限定されています。
そのため、認知症によって本人の判断能力が低下し始めた段階では、任意後見契約の締結は難しいです。
判断力の低下が始まった段階で、なんとかしてギリギリで任意後見契約を締結しようとしても、公証役場が医師の診断書を求めてくるケースがあります。
判断能力が正常である証拠を求められたら、任意後見契約の締結はかなり厳しくなるでしょう。
死後の事務を依頼できない
本人が亡くなると自動的に任意後見契約は終了となり、死後の事務処理や財産の管理は任意後見人では扱えなくなります。
身辺整理などの死後事務を任意後見人へ依頼することはできません。
任意後見契約が終わると本人の財産は法定相続人へ引き渡します。
特に、遺言がなければ、財産管理は相続人同士の遺産分割協議へと移っていく流れです。
本人の死後の財産管理や事務処理をスムーズに行いたい場合は、「死後事務委任契約」や「遺言」もしくは「家族信託」などをうまく活用することが求められます。
任意後見は親族以外にも依頼できる
信頼できる親族がいればそれほど迷うことなく任意後見人を頼むこともできますが、全ての人が身近に信頼できる親族がいるとは限りません。
「任意後見制度を利用したいけど、信頼できる人がいない」という場合は司法書士へ依頼することも可能です。
任意後見を司法書士に依頼するメリット
親族以外の第三者へ任意後見人を依頼するなら、司法書士など法律知識がある専門家へ依頼するのが安心です。
司法書士は契約などの法的な手続きを進める専門家です。
任意後見人の職務を遂行するにあたって大抵のことは心得ているため、手続きや事務処理などもスムーズに進めてくれるでしょう。
見守り契約や財産管理等委任契約、死後事務委任契約なども併せて契約することもできます。
また、遺言書の作成も相談できるため、老後に不安がある方は司法書士へ相談するのも一つの選択肢です。
任意後見を司法書士に依頼する流れ
任意後見人を司法書士へ依頼する際の基本的な流れは、次の通りです。
- STEP1:任意後見の相談をする
- STEP2:任意後見契約書の内容を検討する
- STEP3:任意後見契約の締結をする
- STEP4:任意後見監督人の選任申立てをする
- STEP5:任意後見が開始される
それぞれの段階ごとに詳細を説明します。
STEP1:任意後見の相談をする
まずは、司法書士に任意後見の相談をします。
基本的には任意後見制度を軸に話が進められますが、抱えている課題によっては多角的な視点で司法書士から提案されるケースも多いです。
今後の不安や課題を司法書士へ細かく相談してみましょう。
STEP2:任意後見契約書の内容を検討する
任意後見制度の利用を決めたら、契約内容を考える必要があります。
「誰に財産管理を任せるのか」「どの程度の権限を与えるのか」など、希望に沿った契約内容の検討を進めます。
STEP3:任意後見契約の締結をする
任意後見契約は公正証書で作成しなければいけません。
内容ができたら公正役場にて公正証書を作成します。
公正証書を作成するには、書類をそろえる必要があります。
必要な書類は次の通りです。
1 本人について
①印鑑登録証明書+実印(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印)
②戸籍謄本または抄本
③住民票
2 任意後見人となる人(任意後見受任者)について
①印鑑登録証明書+実印(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印)
②住民票
なお、受任者が法人の場合は、法人代表者の印鑑証明書+代表者印および資格証明書
※ 印鑑登録証明書または法人代表者の印鑑証明書および資格証明書については、発行後3か月以内のものに限ります。
STEP4:任意後見監督人の選任申立てをする
契約が締結された後、本人の判断能力が不十分と判断されたタイミングで任意後見受任者等が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。
特に問題がなければ家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見契約が効力を持ち始めるという流れです。
家庭裁判所が申立書を受理した後の流れは次の通りです。
- 家庭裁判所にて申立人と任意後見受任者の面接が行われる
- 本人の調査と精神鑑定が行われる
- 家庭裁判所から照会書が送られる
- 監督人を選任した後に任意後見人の仕事が始まる
STEP5:任意後見の開始
監督人が選任された後、任意後見人業務がスタートします。
公正証書で締結した任意後見契約の内容に基づいて支援がスタートし、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が任意後見人を監督する仕組みです。
契約期間中は、任意後見人は契約で定めた報酬額、任意後見監督人は家庭裁判所が決定した報酬額を受け取ります。
任意後見を司法書士に依頼したときの費用
任意後見の手続きを司法書士へ依頼した場合、以下の費用が発生します。
- 契約書作成費用
- 任意後見監督人選任の申し立て費用
- 任意後見人選任への報酬
それぞれの費用について、詳細を説明します。
なお、具体的な費用は司法書士事務所や契約内容によって異なるため、検討を進める際は詳細をよく確認するようにしましょう。
契約書作成費用
公証人に任意後見契約書を作成してもらう時に必要な手数料は、次の通りです。
| 作成に関する基本手数料 | 11,000円 |
|---|---|
| 嘱託登記の手数料 | 1,400円 |
| 法務局へ納付するための印紙代 | 2,600円 |
諸経費などを合わせて、自分で契約書を作成した場合の費用は2万円程度と考えておくと良いでしょう。
諸般の事情で外出が難しい場合は、公証人に出張してもらったうえで任意後見契約書を作成してもらうこともできます。
出張の際の報酬は日当1〜2万円と交通費がかかります。
任意後見監督人選任の申し立て費用
任意後見監督人選任の申し立てに必要な費用は、次の通りです。
| 申し立てに関する手数料 | 800円分の収入印紙 |
|---|---|
| 登記にかかる手数料 | 1,400円分の収入印紙 |
| 連絡用の切手代 | 3,000〜5,000円 |
自分で申し立ての手続きをした場合の費用は合計で1万円程度です。
そのほか、精神鑑定が必要と判断された場合には、さらに5〜10万円程度必要となるケースもあります。
連絡用の切手台には幅がありますので、詳細は申し立てをする家庭裁判所に確認するようにしましょう。
任意後見人への報酬
任意後見契約がスタートした後は、任意後見人と任意後見監督人それぞれに報酬を支払います。
親族が任意後見人になっている場合は話し合いの結果、無報酬に設定できるケースも多いです。
有償と無償、どちらにするのかはあらかじめ決めておきましょう。
第三者の弁護士や司法書士などの専門家へ依頼する場合、規定の報酬を支払う必要があります。
金額や支払い方法、支払い時期は契約書にて自由に取り決め可能です。
一般的な相場は、次の通りです。
| 親族など近しい人が任意後見人になる場合 | 無償〜3万円程度 |
|---|---|
| 弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合 | 3〜5万円程度 |
上記は一般的な相場の例ですが、専門家次第では報酬が高額になるケースもあるので、事前に金額の確認を行いましょう。
基本的に本人が所有する財産が多ければ多いほど管理業務や負担が増えることから、支払う報酬金額も多くなります。
任意後見は経験豊富な司法書士に依頼しよう
任意後見制度は本人の意思によって後見人を選ぶことができる制度です。
法定後見人のように、自分の意思とは無関係な人が選ばれることはありません。
信頼関係の元に契約を締結できる点はメリットですが、死後の財産管理ができない点や取消権がない点はデメリットです。
基本的に任意後見人は親族など信用できる人へ依頼するケースが多いですが、司法書士など専門家へ依頼することもできます。
司法書士へ依頼すると、任意後見契約の締結から監督人選任の申し立て、任意後見制度の不十分なところをカバーする、見守り契約や財産管理等委任契約、死後事務委任契約の締結や遺言書の作成まで対応可能です。
老後の心配事をトータルで解消したい人は、司法書士へ相談してみてはいかがでしょうか。
ゆずりは司法書士法人では、任意後見契約書や遺言書の作成、亡くなった後の葬儀やお墓のことなど、老後の心配ごとをトータルサポートできる体制が整っています。
ご相談内容に合わせてより良い方法の提案もできますので、ぜひ一度ご相談ください。
本記事に関する連絡先
TEL: 06-6253-7707
メールでのご相談はこちら >>