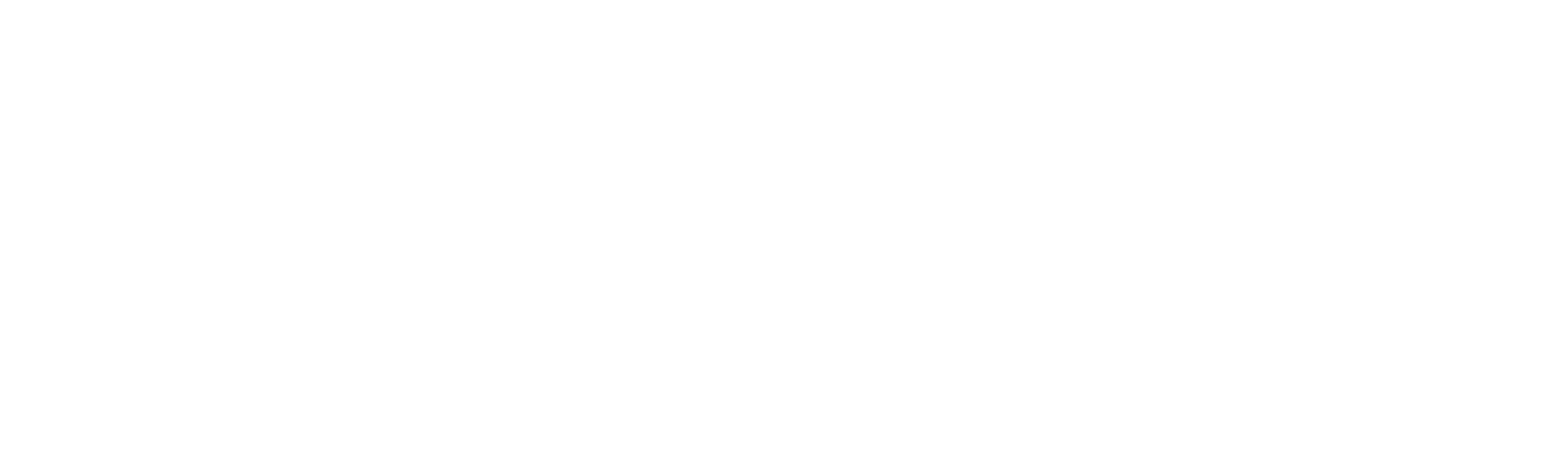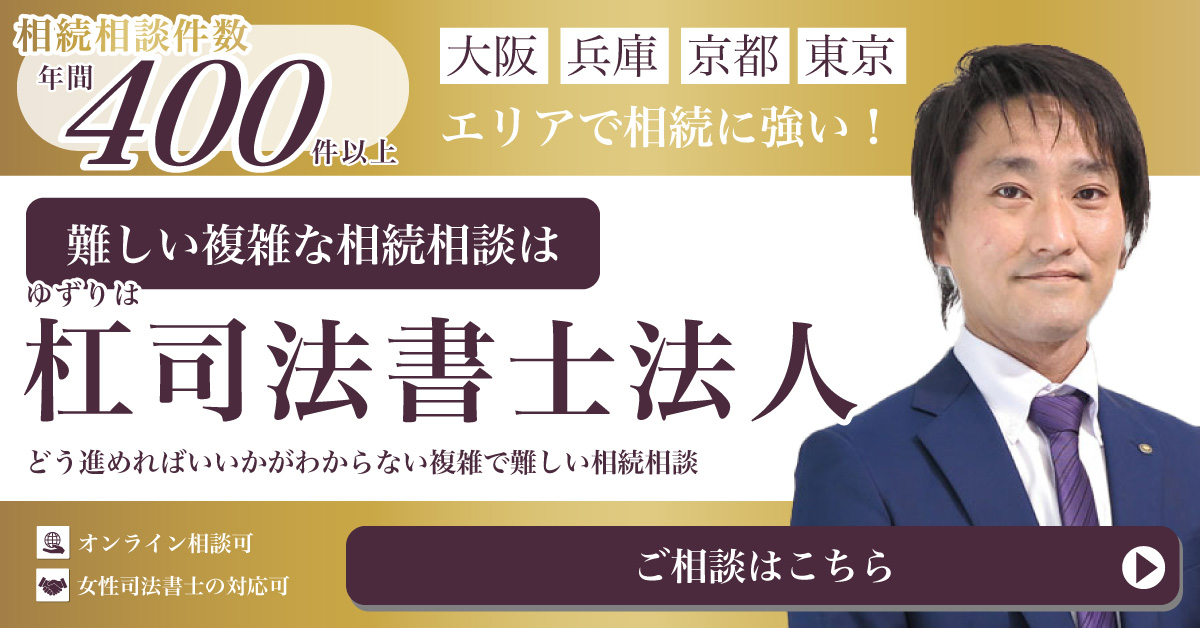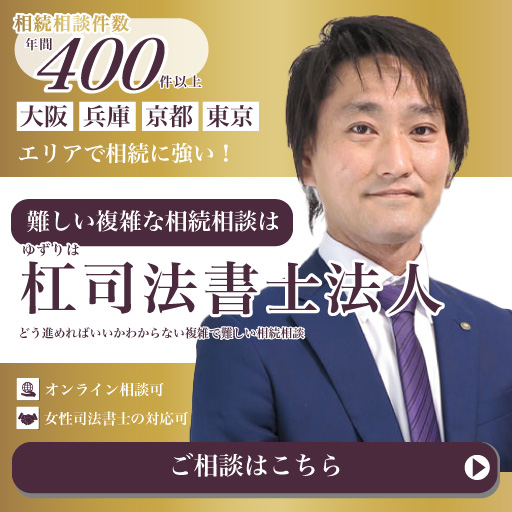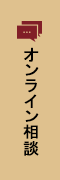孫に遺産を相続する方法|注意点や祖父母が生前にやるべきことも解説
相続
投稿日:2025.03.19

「かわいい孫に少しでも遺産を遺したい」と考える祖父母の方は多いのはないでしょうか。
しかし実は、相続におけるほとんどのケースで孫は相続人になれません。
そのため、孫に相続したいのであれば生前からの準備が必要になります。
本記事では、孫に相続する方法や注意点、祖父母が生前やっておきたいことを詳しく解説します。
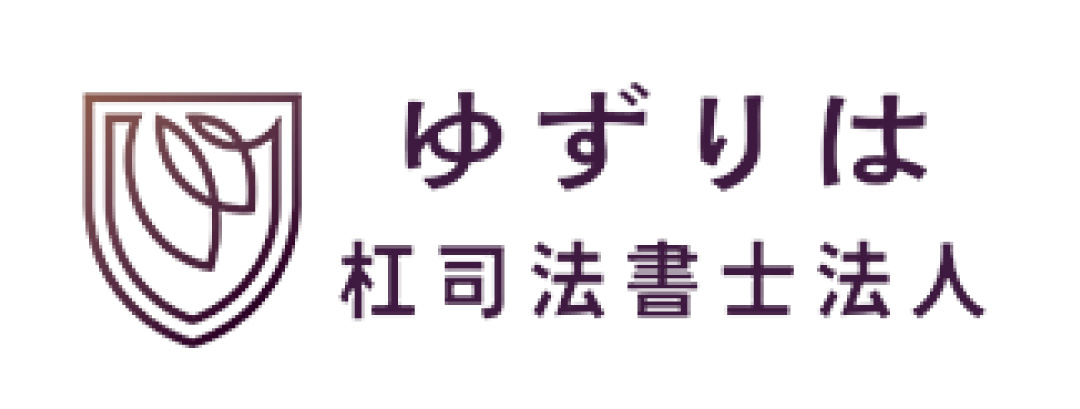
大阪・兵庫・京都・東京を拠点に、相続手続き・遺言書作成・家族信託契約などのサポートから企業法務まで、専門のチームで対応しております。税理士や他業種との連携により、相続問題をワンストップで解決!相続関連の相談件数は年間400件超。
目次
【注意】孫は法定相続人にならない
孫は法定相続人に該当しないため、特別な準備を行わない限り、基本的には財産を引き継ぐことができません。
法定相続人とは、民法で定められている「被相続人の財産を引き継ぐ権利を持つ人」を指します。
具体的には配偶者のほか、被相続人と血縁が近い子ども、父母、祖父母、兄弟姉妹などが法定相続人に該当し、孫は含まれません。
したがって、基本的に祖父母の遺産が孫に渡ることはないといえます。
もしも孫に財産を譲りたいと考えているのであれば、生前の準備が必要です。
孫に財産を相続させるための3つの方法
次の方法を用いることで、孫に財産を相続できます。
- 遺言書で遺贈する
- 養子縁組する
- 代襲相続が発生する
まずは、それぞれの方法について詳しく解説します。
1.遺言書で遺贈する
相続では遺言の内容が優先されるため、遺言書を作成しておくことが孫に財産を引き継ぐための有効な手段の一つです。
通常は、法定相続人のみで遺産分割協議を行い、被相続人の財産の分割方法を決定します。
しかし、遺言で指定すれば、法定相続人ではない孫にも財産を残すことが可能です。
遺言書を作成すると、預貯金や土地、建物など特定の財産を指定して孫に相続したり、遺産を譲り渡す割合を決めたりできます。
ただし、遺言書の内容や形式に問題があると法的効力が失われて、孫に財産を相続できなくなる点に注意が必要です。
2.養子縁組する
被相続人と孫が養子縁組すると法律上の親子関係が発生するため、孫も法定相続人として扱われるようになります。
相続において、被相続人の子どもは法定相続人の第1順位として、配偶者の次に遺産を引き継ぐ権利を持っています。
被相続人と孫が養子縁組すれば、孫も法定相続人の第1順位とみなされて、実子と同様の条件で相続が可能です。
ただし、養子縁組が明らかに節税目的であると判断されると、養子が相続人として認められないケースがあります。
また、法定相続人の人数が増えると相続税の基礎控除が増額されますが、養子の人数には制限があります。
被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は2人までが対象となる点に注意してください。
3.代襲相続が発生する
被相続人の子ども、つまり孫の親が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、親の権利を引き継いだ孫が法定相続人となります。
これは「代襲相続」と呼ばれ、孫は子どもと同様に第1順位の法定相続人として扱われます。
代襲相続は条件がそろっていれば認められるため、特別な手続きは不要です。
ただし、代襲相続は自然に発生するものであり、意図的に状況を作ることはできません。
また、孫に兄弟姉妹がいれば全員が代襲相続人になることから、特定の孫だけに相続したい場合に代襲相続は適しません。
相続以外で孫に財産を引き継ぐ5つの方法
相続以外で孫に財産を引き継ぐ方法には、次の5つが挙げられます。
- 生前贈与する
- 教育資金として贈与する
- 結婚・子育て資金として贈与する
- 住宅取得資金として贈与する
- 生命保険の受取人に指定する
それぞれの方法について解説します。
生前贈与する
生前贈与とは、存命中に自分の財産を他人へ無償で譲ることです。
相続では自分の死後に財産を引き継ぐことになりますが、生前贈与であれば自分が生きているうちに孫へ財産を引き渡せます。
ただし、生前贈与には贈与税がかかる場合があります。
税負担を抑えながら生前贈与するには、「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」をうまく利用することがポイントです。
暦年贈与とは、基礎控除の範囲内で毎年贈与を繰り返す方法です。
贈与税には基礎控除があり、1月1日から12月31日までの1年間に贈与した金額が110万円以内であれば、贈与税が課税されません。
この仕組みを利用すると節税が可能ですが、暦年贈与と認められず贈与税が発生するケースがあることに注意が必要です。
一方で、相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
ただし、この制度を利用すると贈与時点では2,500万円の限度額まで税金がかからないものの、祖父母が亡くなったときに相続税が課税されます。
また、相続時精算課税制度は年間110万円の基礎控除と併用できますが、暦年贈与とは併用できません。
教育資金として贈与する
30歳未満の孫に教育資金を一括贈与すると、1,500万円までは贈与税が非課税になる制度があります。
対象となる教育資金には、次のような費用が含まれます。
- 入学金
- 授業料
- 入園料
- 保育料
- 入学試験の検定料
- 学用品の購入費
- 給食費
- 部活動費
さらに、500万円までは次のような用途にも利用できます。
- 塾や習い事の月謝
- 通学にかかる交通費
- 留学渡航費
この制度を利用するためには、金融機関に専用口座を開設し、資金を一括で入金しなければなりません。
口座は金融機関が管理しており、出金時には領収書の提出が求められます。
なお、この制度は期限があり、2026年3月31日までに贈与が完了していなければなりません。
孫が30歳になった時点で学生ではなく、使いきれなかった資金が口座に残っていると、その残高に対して贈与税がかかる点にも注意しましょう。
結婚・子育て資金として贈与する
18歳以上50歳未満の孫に、結婚や子育てに関する資金を一括贈与すると、1,000万円までは贈与税が非課税になります。
ただし、結婚資金については300万円が上限です。
次のような費用が結婚資金に該当します。
- 挙式費用
- 結婚披露宴の費用
- 衣装代
- 家賃や敷金などの新居費用
- 引越し費用
この制度も、2025年3月31日までの期限があります。
これまでも税制改正により期限の延長が繰り返されてきたため、この期限も延びる可能性がありますが、利用を希望する場合は早めに手続きを進めましょう。
住宅取得資金として贈与する
18歳以上の孫に住宅取得資金を贈与すると、一定金額までは贈与税が非課税になります。
非課税限度額は、制度の適用を受ける住宅の種類により異なります。
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅 | 1,000万円 |
| 上記以外の住宅 | 500万円 |
住宅取得資金に該当するのは、次のような費用です。
- 住宅の新築費用
- 住宅の取得費用
- 住宅の増改築費用
この制度にも期限があり、2026年12月31日までの贈与が対象となります。
さらにこの制度には、取得する住宅の省エネ基準、耐震基準、床面積などに細かな要件が設定されています。
制度の対象となる人物にも要件が定められているため、制度を利用する場合は十分に確認したうえで申告しましょう。
生命保険の受取人に指定する
祖父母の生命保険金の受取人に孫を指定することも、財産を引き渡す方法の一つです。
生命保険金は相続財産とみなされず遺産分割の対象にならないため、孫以外の法定相続人が相続する心配はありません。
ただし、生命保険金には税負担が生じる場合があります。
孫が代襲相続人になるケースでは相続税控除が認められますが、孫が保険金を受け取ると相続税が課税される可能性があることに注意しましょう。
孫が相続できる遺産の割合
遺言がなく、孫が代襲相続人や養子として相続する場合は、法定相続分に基づいて財産を引き継ぎます。
法定相続分とは、民法で定められている、各法定相続人に割り当てられた相続の割合のことです。
代襲相続人や養子になった孫は、被相続人の子どもと同じ第1順位の法定相続人として扱われます。
相続において第1順位になる子どもの法定相続分は、次のとおりです。
| 相続人の組み合わせ | 相続割合 |
|---|---|
| 配偶者+子ども | 2分の1 |
| 子どものみ | 全て |
子ども(孫)が複数人いる場合は、法定相続分を子どもと孫全員で均等に分割します。
一方で、遺言に相続割合が指定されていれば、その内容に従って孫が相続します。
ただし、相続では遺言の内容が優先されるものの、後ほど解説する遺留分があるため、全てが遺言通りに分割されるとは限りません。
孫に相続するときの注意点
孫に相続するときには、いくつかの注意点があります。
以下では、注意すべきポイントを2つ解説します。
ほかの親族とトラブルになる可能性がある
法定相続人ではない孫に財産を引き継ぐと、法定相続人である親族との間でトラブルが起こる可能性があります。
相続人に孫が加わることで、ほかの親族の取り分が減ってしまうためです。
たとえば、子ども1人だけが相続する場合は、その子どもが全ての相続財産を受け取れます。
しかし、養子として孫が1人加わると、子どもの相続分は2分の1に減ってしまいます。
遺言で孫を相続人に指定すれば、ほかの親族が不満を抱き、親族同士の関係が悪化するかもしれません。
また、養子縁組により孫が法定相続人になると、不公平に感じた親族により遺産分割協議が進まなくなることも考えられます。
孫の相続税が2割加算される場合がある
孫に財産を引き継ぐと、孫が納める相続税が2割増えることがあります。
これは、被相続人の配偶者や父母、子ども以外の親族が相続すると、相続税が2割増しになると定められているためです。
遺言による遺贈や養子縁組による相続では、相続税の2割加算が適用されます。
一方で、孫が代襲相続人になる場合は2割加算の対象外となります。
孫に相続するために祖父母が生前にやっておきたいこと
孫に財産を引き継ぐ際のトラブルを防ぐためには、生前の準備が重要です。
以下では、孫が安心して相続できるように祖父母が取り組むべき生前の対策を紹介します。
親族と話し合っておく
孫に相続したい場合は、ほかの親族とも事前によく話し合っておくことが大切です。
突然、孫を養子縁組したり孫に遺贈したりすると、ほかの親族が不満を抱いてトラブルが生じやすくなります。
孫に相続する理由や必要性について事前に説明して理解を得ておくことで、相続手続きがスムーズに進み、親族関係の悪化も防げるでしょう。
遺留分に配慮する
孫に遺贈や生前贈与する際は、ほかの相続人の遺留分を侵害しないように配慮しましょう。
遺留分とは、民法により最低限保証されている遺産の取り分であり、兄弟姉妹以外の法定相続人にはこの権利が認められています。
そのため、たとえば全ての財産を孫に遺贈すると遺言で指定すると、ほかの相続人は遺留分を得られなくなってしまいます。
この場合、遺留分を侵害された相続人は、孫に対して遺留分に相当する金額の請求が可能です。
遺留分を侵害された相続人は気分を害するうえに、遺留分を請求された孫は金銭的だけでなく、精神的にも負担を感じるでしょう。
孫が遺留分の請求に応じなければ、調停や訴訟などさらなるトラブルに発展する可能性もあります。
そのため、遺贈や生前贈与する場合は遺留分に気を配ることが大切です。
贈与税・相続税を確認する
孫への相続や生前贈与にかかる税金を事前にシミュレーションし、できる限り負担が少なくなる方法を検討することも重要です。
孫へ財産を引き継ぐと相続税が2割加算される場合があります。
また、生前贈与には節税に利用できるさまざまな制度がありますが、適用されるには数多くの要件を満たさなければなりません。
思わぬ税金の負担が発生しないように、贈与税や相続税についてあらかじめ確認しておきましょう。
専門家に相談する
孫へ財産を引き継ぐには、専門家に相談することをおすすめします。
遺言により孫に相続する場合でも、正しい形式で遺言書を作成しなければ、遺言が無効になる可能性があります。
また、遺言は遺留分への配慮も必要です。
教育や結婚、住宅取得の資金として贈与する場合も、細かな要件を満たさなければ制度は適用されません。
このように、法定相続人でない孫に財産を引き渡すことは簡単ではありません。
しかし、相続や税金に精通した税理士や司法書士、弁護士などの専門家に依頼すれば、孫への財産継承を実現できる可能性があります。
相続に伴うトラブルを回避しながら孫に間違いなく遺産を引き継ぎたい方は、専門家に相談しましょう。
孫に相続するなら専門家に依頼しよう
孫は法定相続人に含まれないため、孫に財産を引き継ぎたい場合は生前の準備が重要です。
孫に財産を引き渡すには遺贈や養子縁組、生前贈与などの方法があります。
しかし、条件を満たさなければ税負担が増えたり、想定通りに財産を引き継げなかったりする可能性があります。
また、親族同士のトラブルが起きないように配慮することも大切です。
そこで、孫へ相続するなら、専門家に依頼することをおすすめします。
遺言書の作成や相続手続きなど、相続に関するご相談は杠(ゆずりは)司法書士法人にお任せください。
杠(ゆずりは)司法書士法人は、豊富な専門知識と経験を活かして、最適な解決策をご提案いたします。
相続に関する複雑な手続きや疑問点も丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
本記事に関する連絡先
TEL: 06-6253-7707
メールでのご相談はこちら >>