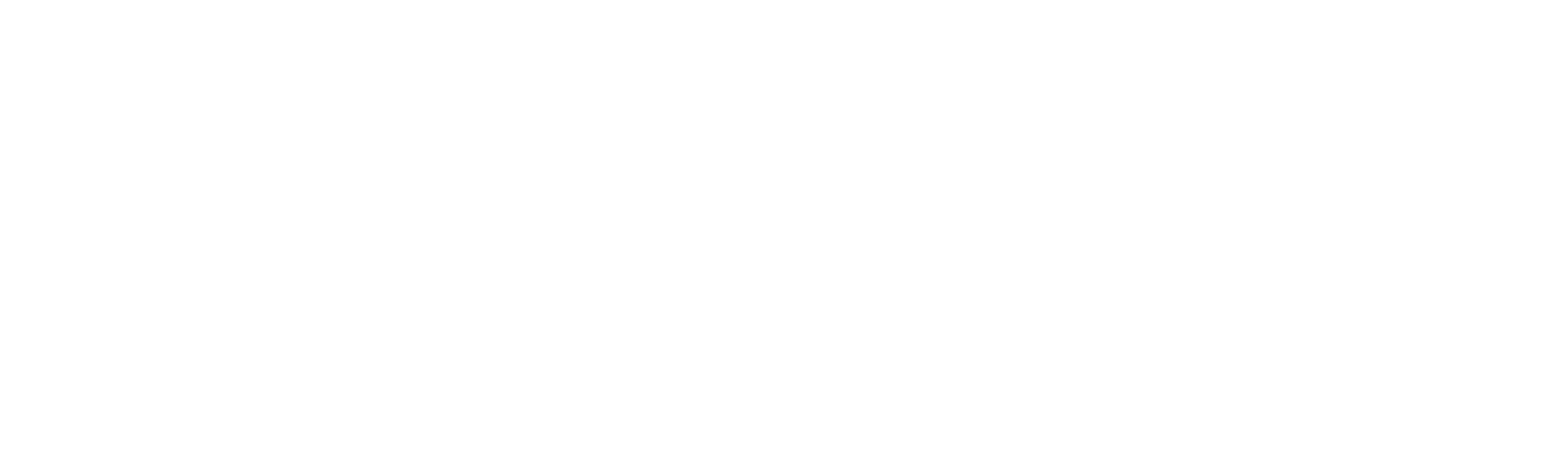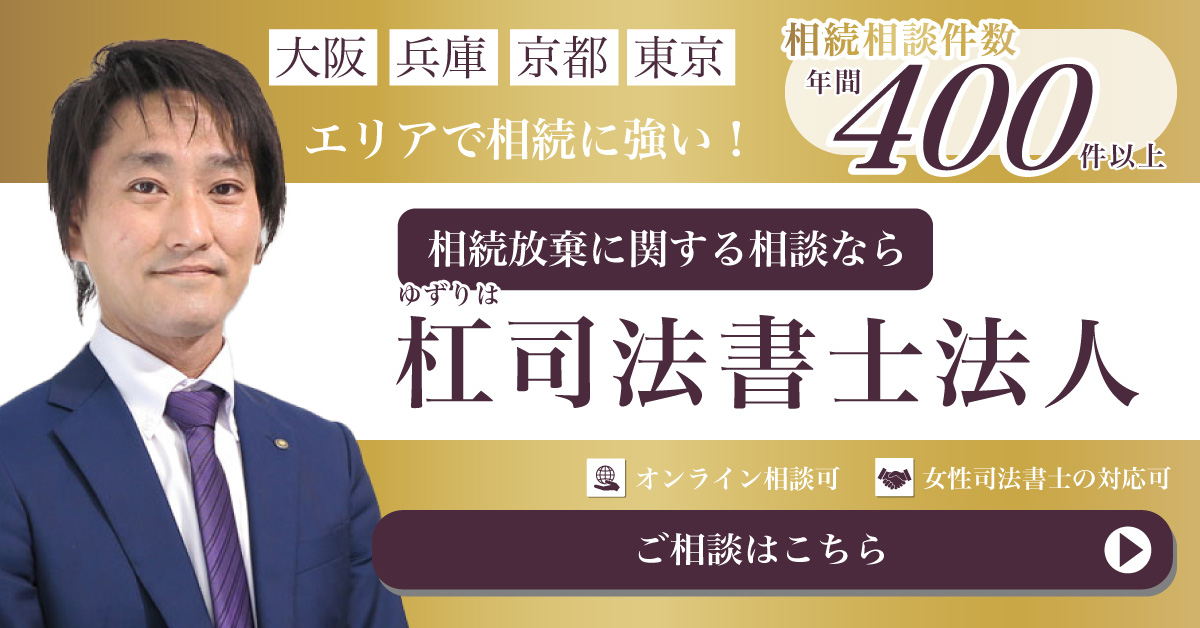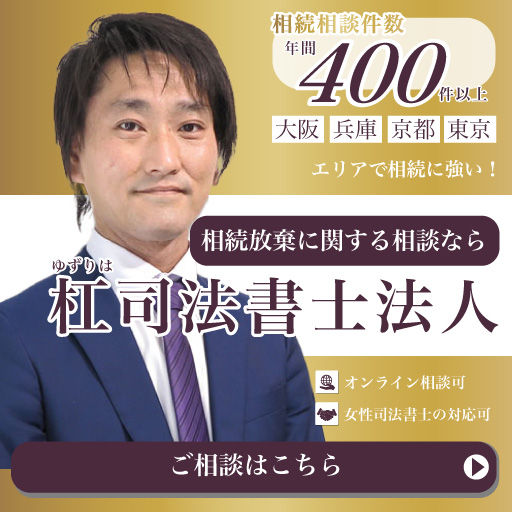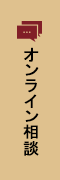相続放棄を兄弟まとめて行うことは可能?費用相場や注意点を解説
相続
投稿日:2025.03.25

相続が発生し、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続放棄という選択肢があります。
相続放棄は本来、相続人が個々で手続きをするものですが、相続順位が同じ兄弟姉妹であればまとめて相続放棄することが可能です。
この記事では、兄弟姉妹がまとめて相続放棄する際の手続きや費用について詳しく解説します。
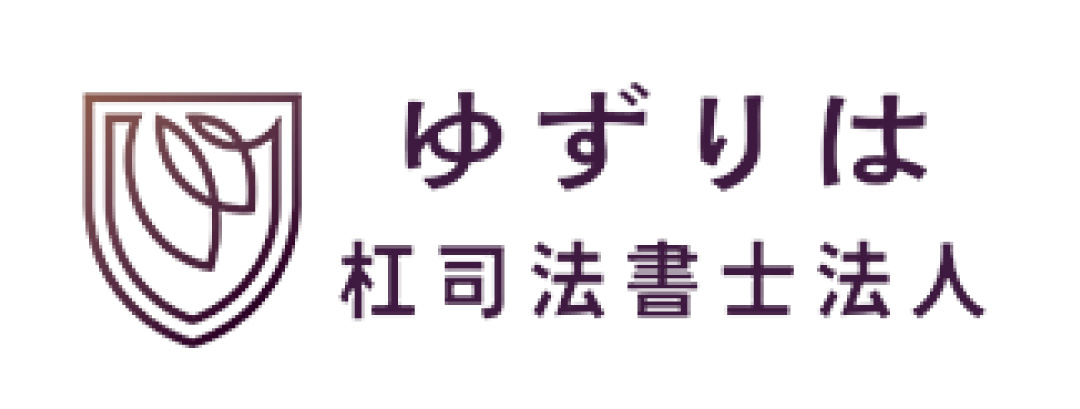
大阪・兵庫・京都・東京を拠点に、相続手続き・遺言書作成・家族信託契約などのサポートから企業法務まで、専門のチームで対応しております。税理士や他業種との連携により、相続問題をワンストップで解決!相続関連の相談件数は年間400件超。
目次
兄弟姉妹が相続放棄を検討するケース
亡くなった人の兄弟姉妹が相続放棄を検討するにあたり、まず法定相続人の順位と範囲を知っておく必要があります。
法定相続人の相続順位は、以下のとおりです。
| 配偶者 | 必ず相続人になる |
|---|---|
| 子 | 第一順位 |
| 親 | 第二順位 |
| 兄弟姉妹 | 第三順位 |
兄弟姉妹は第三順位ですが、先順位の人がいる場合は相続人にならないので、相続放棄を検討する必要はありません。
しかし、以下のようなケースは例外です。
- 配偶者、子、親が相続放棄をした
- 配偶者、子、親がいない、もしくは亡くなっている
いずれかの事情で兄弟姉妹に相続権が発生した場合は、相続放棄を検討する必要があります。
兄弟姉妹まとめて相続放棄することは可能?
相続手続きは相続人がそれぞれ行うものなので、相続放棄を行う際もほかの相続人に同意をとる必要はありません。
しかし、同じ相続順位の相続人が相続放棄を検討しているのであれば、まとめて手続きを行うことも可能です。
この場合、兄弟姉妹の相続順位は同じなので、まとめて相続放棄することができます。
ただし、先順位である配偶者や子、親の相続放棄が受理されてからでないと、後順位である兄弟姉妹は相続放棄を進められないという点に注意しましょう。
兄弟姉妹まとめて相続放棄をするメリット
兄弟姉妹がまとめて相続放棄を行うのは、費用や書類取得の面からもメリットがあります。
具体的なメリットは、以下のとおりです。
- 相続トラブルを回避できる
- 提出書類が少なくて済む
- 専門家に依頼する際の費用を抑えられる
それぞれについて詳しく解説します。
相続トラブルを回避できる
相続放棄を検討する理由として、借金やローン、扱いに困る山林や不動産といったマイナスの財産を引き継ぎたくないという方は少なくありません。
相続放棄をすると初めから相続人でなかったという扱いになるので、そのぶんほかの兄弟姉妹の相続分が増えることになります。
相続人が個々に相続放棄を行うのは法的に問題ない行為ですが、感情的な面で納得できないこともあるでしょう。
相続放棄をきっかけにトラブルへ発展するのを回避するには、相続放棄することをほかの兄弟姉妹へ伝え、足並みをそろえることが大切です。
提出書類が少なくて済む
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄するには、第一順位、第二順位の相続人がいないことを示す書類を用意しなければならず、書類収集に時間がかかります。
しかし、まとめて相続放棄をする場合、共通する書類は一通だけで済みます。
それぞれが個別に書類を収集しなくても済むので、手続きにかかる手間が大幅に節約できるのは大きなメリットといえるでしょう。
専門家に依頼する際の費用を抑えられる
相続放棄の手続きは自分でも行えますが、相続関係が複雑だったり、不動産が複数あったりするなどのケースは専門家に依頼するほうが確実です。
相続放棄の手続きを司法書士などの専門家に依頼すると費用がかかりますが、相続人が個々で依頼するよりもまとめて依頼するほうが割安になることが多いです。
専門家へ依頼する際は、同じ司法書士または弁護士に依頼することをおすすめします。
兄弟姉妹まとめて相続放棄する際の流れ
兄弟姉妹がまとめて相続放棄する際の流れは、以下のとおりです。
- ステップ1:相続財産と相続人の調査を行う
- ステップ2:必要な書類を集める
- ステップ3:家庭裁判所に申述書を提出する
- ステップ4:照会書に回答する
- ステップ5:相続放棄申述受理通知書を受け取る
それぞれのステップについて詳しく解説します。
ステップ1:相続財産と相続人の調査を行う
相続放棄を検討するには、まず被相続人が遺した財産がどのようなものなのか調査する必要があります。
遺言書や通帳、遺品に加えて、信用情報機関の情報開示請求なども活用しながら、プラスの財産とマイナスの財産を全て明らかにしましょう。
また、自分たちの知らない相続人が存在する可能性もあります。
被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本を調査して、相続人を確定させる作業も並行して行います。
ステップ2:必要な書類を集める
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄する際には、以下のような書類が必要です。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 裁判所のウェブサイトから書式をダウンロード |
| 被相続人の住民票除票 | – |
| 被相続人の戸籍謄本 | 出生から死亡まで記載されたもの |
| 被相続人の子(第一順位の相続人)の戸籍謄本 | 出生から死亡まで記載されたもの |
| 被相続人の親(第二順位の相続人)の戸籍謄本 | 出生から死亡まで記載されたもの |
| 相続放棄する人の戸籍謄本 | – |
| 収入印紙や切手 | 管轄の家庭裁判所によって異なる |
ここで気を付けなければならないのが、被相続人の兄弟姉妹は傍系相続人になるため、第一順位の相続人である被相続人の子どもの戸籍謄本は直接取得できないということです。
戸籍が必要な理由を示すことに加えて、親族関係が分かる書類を請求されることもあるので注意が必要です。
兄弟姉妹がまとめて相続放棄をするのであれば、重複する書類を省略できます。
どの書類が省略できるかはケースによって異なりますが、書類取得の手間を大幅に削減できるので、事前によく確認しておきましょう。
ステップ3:家庭裁判所に申述書を提出する
相続放棄申述書と必要書類を家庭裁判所に提出します。
相続放棄申述書の書式は、裁判所のウェブサイトからダウンロード可能です。
相続放棄する場合の記入例も用意されているので自分でも作成できますが、財産の種類が多かったり相続関係が複雑な場合は、専門家に作成を依頼するという選択肢もあります。
ステップ4:照会書に回答する
申述書と必要書類を提出後、10日~2週間程度で家庭裁判所から照会書が届きます。
これは、申述書の内容をもとに相続放棄の理由や状況を確認するためのもので、場合によっては電話や対面での確認が行われることもあります。
兄弟姉妹でまとめて相続放棄の手続きをしても審査は個々で行われ、事情によっては相続放棄を却下される可能性もあるので注意が必要です。
ステップ5:相続放棄申述受理通知書を受け取る
家庭裁判所からの照会で問題がなければ、相続放棄が受理されて「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
通知が届くまでの期間は、照会が行われてから10日~2週間後が多いです。
この通知をもって相続放棄が認められたことになり、相続人としての権利や義務を完全に失うことになります。
兄弟姉妹まとめて相続放棄する際の費用相場
兄弟姉妹まとめて相続放棄の手続きをする際の費用負担は、どのくらいになるのでしょうか。
以下では、自分たちで行う場合と、専門家に依頼した場合の2通りを解説します。
自分たちで行う場合
自分たちで相続放棄の手続きをする際に必要な費用は、主に書類の取得費用と収入印紙代です。
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄する際に必要な費用を、以下の表にまとめました。
| 被相続人の住民票除票 | 300円前後 |
|---|---|
| 被相続人の除籍(戸籍)謄本 | 750円(450円) |
| 被相続人の子(第一順位の相続人)の除籍(戸籍)謄本 | 750円(450円) |
| 被相続人の親(第二順位の相続人)の除籍(戸籍)謄本 | 750円(450円) |
| 相続放棄する人の戸籍謄本 | 450円 |
| 収入印紙 | 800円 |
| 切手 | 350円~500円前後 |
自治体によって多少の差はありますが、総額で一人あたり5,000円を目安に考えておけば良いでしょう。
なお、共通する書類は省略できるため、複数人で同時に相続放棄を行う場合は、一人あたりの負担がさらに抑えられる可能性があります。
専門家に依頼する場合
相続放棄は、司法書士または弁護士に依頼できます。
それぞれに依頼した場合にかかる費用目安は、以下のとおりです。
| 司法書士 | 3〜5万円 |
|---|---|
| 弁護士 | 5〜10万円 |
費用は弁護士のほうが高額ですが、法的トラブルの相談にも対応してもらえるというメリットがあります。
逆にトラブルがなく相続放棄だけを依頼したいのであれば、司法書士を選ぶほうが費用負担は少なく済むでしょう。
これに加えて、別途5,000円程度の必要書類の取得費がかかることが多いです。
兄弟姉妹まとめて相続放棄する際の注意点
兄弟姉妹がまとめて相続放棄する際の注意点として、以下が挙げられます。
- 熟慮期間の起算日が異なる可能性がある
- ほかの相続人に相続放棄したことを知らせる必要がある
- 相続放棄しても財産の保存義務が残る可能性がある
- 相続放棄が認められない可能性もある
それぞれの注意点について詳しく解説します。
熟慮期間の起算日が異なる可能性がある
熟慮期間とは相続を承認するか、それとも放棄するかを選択する期間のことで「被相続人の死亡と自分が相続人であることを知った翌日から3か月」と定められています。
兄弟姉妹間であまり付き合いがなく、被相続人が亡くなったことを知るタイミングがずれている場合は、熟慮期間の起算点が異なってくる可能性もあるのです。
兄弟姉妹とまとめて相続放棄をするのであれば、それぞれの熟慮期間の起算点をよく確認して、全員の期限に間に合うように手続きを進めることが大切です。
ほかの相続人に相続放棄したことを知らせる必要がある
相続人のうちの一人が相続放棄をしたとしても、裁判所からほかの相続人に対して自動で通知等が届くことはありません。
同じ順位の相続人に黙って手続きを進めても法的には問題ありませんが、「勝手に手続きを進められた」と感情がこじれてしまうケースも考えられます。
相続放棄を決めた時点で、ほかの相続人にすみやかに連絡しておくことをおすすめします。
相続放棄しても財産の保存義務が残る可能性がある
遺産に含まれている不動産を占有している状態で相続放棄をした場合は、相続財産清算人に引き渡すまで管理義務が発生することがあります。
管理義務とは、不動産を安全に管理することで、家屋の倒壊を防ぐためのメンテナンスなどが含まれています。
この場合の「占有」が、必ずしも居住している状態を指すとは限りません。
相続財産に不動産が含まれている場合は、専門家に相談してアドバイスを受けることも検討しましょう。
相続放棄が認められない可能性もある
相続放棄をまとめて手続きしても、家庭裁判所からの照会書は相続人それぞれのもとに届きます。
照会に対応しないと相続放棄が認められなくなってしまうため、全員が手続きについて把握しておくことが大切です。
また、相続放棄を認めるかどうかの判断は個別で行われるため、状況によっては一人だけ相続放棄を認められないケースも考えられます。
兄弟姉妹の相続放棄に関するよくある質問
ここまで、兄弟姉妹がまとめて相続放棄する際の手続きや費用について解説してきました。
以下では、兄弟姉妹がまとめて相続放棄する際によくある質問について回答します。
兄弟姉妹の一人だけが相続放棄することはできる?
相続放棄は本来個別で行うものなので、一人だけ相続放棄しても問題ありません。
ただし、まとめて行うことで書類を省略できるといったメリットがあり、相談なしに手続きを進めることでほかの相続人とトラブルになる可能性もあります。
できるだけ早めに相続放棄することを伝えておくほうが良いでしょう。
兄弟姉妹が相続放棄すると、相続権は甥や姪に移る?
相続放棄をすると初めから相続人でなかったと扱われるため、代襲相続は起きません。
相続人が死亡した場合とは扱いが違うので、注意が必要です。
兄弟姉妹が相続放棄する場合、期限はいつまでですか?
兄弟姉妹が相続放棄する場合も熟慮期間は変わらず、「被相続人の死亡と自分が相続人であることを知った翌日から3か月」です。
ただし、熟慮期間の終わりかけになってから借金が発覚したなど、やむを得ない事情がある場合は期限が繰り延べられることもあります。
この場合は自己判断で手続きを進めず、司法書士など相続のプロに相談するようにしましょう。
相続放棄のご相談は杠(ゆずりは)司法書士法人まで
兄弟姉妹がまとめて相続放棄を行うことで、必要書類を簡略化できたり、手続きにかかる費用を抑えられたりと、さまざまなメリットがあります。
その一方で、同順位の相続人同士でしっかり情報を共有することが欠かせません。
また、照会に対応しなかったり、書類に不備があったりすると相続放棄が認められなくなってしまうため、注意が必要です。
杠(ゆずりは)司法書士法人では、相続放棄に関するご相談を受け付けております。
豊富な専門知識と経験を持った相続のプロが、書類準備から提出手続きまでしっかりとサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
株式を相続する方法|手続きの流れや分割方法、注意点について解説
相続財産に株式が含まれるものの、どのように手続きを進めれば良いかわからない方は多いのではないでしょうか。
株式の相続には、評価額の算定や相続人同士での分割、名義変更など、いくつかの重要なステップがあります。
場合によっては、税負担が大きくなったり損失を被ったりする可能性もあるため、慎重な対応が必要です。
この記事では、株式を相続する流れや分割方法、評価の仕方などについて詳しく解説します。
株式を相続する流れ4ステップ
株式は、次のような流れで相続の手続きを進めます。
- 相続人や相続財産を把握する
- 遺産分割協議を行う
- 株式の名義変更を行う
- 相続税を申告・納付する
それぞれの手続きについて詳しく解説します。
ステップ1:相続人や相続財産を把握する
まずは、株式などの遺産を引き継ぐ権利をもつ相続人と、被相続人が所有していた財産を明らかにします。
相続人を知るためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しましょう。
被相続人が所有していた株式は、被相続人の郵便物や通帳の履歴などから推察し、取引していたと考えられる証券会社に問い合わせて確認します。
証券会社に必要書類を提出すると発行してもらえる「残高証明書」を確認すれば、被相続人が保有していた株式や残高がわかります。
以下の書類を提出して、残高証明書を取得しましょう。
- 被相続人が亡くなったことがわかる書類(戸籍謄本、除籍謄本)
- 申請者が相続人であることがわかる書類(戸籍謄本など)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 申請者の実印と印鑑証明書
- 金融機関所定の残高証明書発行依頼書
また、被相続人が取引していた証券会社が分からない場合は、「証券保管振替機構(ほふり)」に問い合わせる方法があります。
証券保管振替機構とは、証券会社から預かった株式などの有価証券を管理する機関です。
この機関に登録済加入者情報の開示請求を行うと、取引していた証券会社を特定できます。
ステップ2:遺産分割協議を行う
遺言書があれば、その内容に従って相続を行います。
しかし、遺言書がない場合は遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議とは、相続人全員が集まって行う、遺産の分け方や割合を決める話し合いです。
協議の内容に全員が合意したら遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名、押印します。
ステップ3:株式の名義変更を行う
株式を相続する人が決まれば、株式の名義変更手続きを行います。
相続人が証券口座を持っていない場合、まずは口座を開設しましょう。
口座を開設したら、以下のような書類を用意して、証券会社で株式の名義変更を行います。
- 証券会社所定の名義変更依頼書
- 被相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図
- 相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図
- 遺言書または遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
必要書類は証券会社により異なるため、事前に問い合わせて確認してください。
なお、書類を提出してから株式の名義変更が完了するまでは約1か月程度かかります。
ステップ4:相続税を申告・納付する
相続税の申告と納付の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
被相続人が亡くなった時点での住所地を管轄する税務署に、申告書を提出します。
また、原則として現金で一括して納付します。
相続税の納付方法は、次のとおりです。
- 銀行などの金融機関や郵便局
- 税務署
- クレジットカード
- コンビニエンスストア
- ダイレクト納付
- インターネットバンキング
- キャッシュレス決済
ダイレクト納付とは、e-Taxを利用して納付する方法です。
相続税申告にe-Taxを利用する場合は便利ですが、使用開始には手続きが必要です。
少額であれば、クレジットカードやコンビニエンスストア、キャッシュレス決済でも手軽に納付できるので、利用を検討してみましょう。
相続した株式を分割する方法
株式の分割方法には、次の3種類があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
それぞれの分割方法を理解して、適したものを選びましょう。
現物分割
現物分割とは、株式を換金せずにそのまま相続する方法です。
たとえば、3種類の株式を種類ごとに3人で分けたり、1,500株の株式を3人で500株ずつ分けたりする方法があります。
1,500株をAさんが600株、Bさんが500株、Cさんが400株と分けてもかまいませんが、後のトラブルを避けるため、できる限り数で平等に分けるのが一般的です。
代償分割
代償分割とは、株式を1人の相続人が引き継ぎ、その人がほかの相続人に代償金を支払う方法です。
たとえば、3人の兄弟がいて1,500万円分の株式を長男が引き継ぐ場合、弟2人に500万円ずつの代償金を支払います。
このとき3人は500万円ずつ、公平に相続できることになります。
代償分割のメリットは、将来の値上がりが期待できる株式を保有し続けられることですが、一方で、代償金の支払いに多額の現金が必要になることがデメリットです。
換価分割
換価分割とは、株式を売却し、その代金を相続人の間で分ける方法です。
売却代金の分け方は遺産分割協議により自由に決められますが、一般的には法定相続分に従って分けられます。
相続人全員が株式の所有に関心がない場合や、株式を現金化して相続をスムーズに進めたい場合には、換価分割がおすすめです。
相続した株式の評価方法
株式を相続する際はその評価額を把握する必要がありますが、株式は常に価格が変動するため、相続における評価方法が定められています。
ここでは、相続した株式を評価する方法について解説します。
上場株式の場合
上場株式は次の4つの価格のうち、最も低いもので評価されます。
- 被相続人が亡くなった日の終値(最終価格)
- 被相続人が亡くなった月の毎日の終値の平均額
- 被相続人が亡くなった前月の毎日の終値の平均額
- 被相続人が亡くなった前々月の毎日の終値の平均額
証券会社で残高証明書を発行してもらう際に、相続が発生したことを伝えると、上記の価格を提示してくれる場合があります。
また、東京証券取引所のウェブサイトなど、インターネットで確認することも可能です。
相続した株式に複数の銘柄があれば、銘柄ごとに評価を行います。
非上場株式の場合
非上場株式は証券取引所に上場されていないため、客観的な評価が難しいことが特徴です。
したがって、次の3種類の方法のいずれかで価格を評価します。
- 純資産価額方式
- 類似業種比準方式
- 配当還元方式
どの方式を選ぶかは、企業の規模により異なります。
非上場株式の評価方法は複雑であるため、専門家に確認するのがおすすめです。
株を相続する際に株式と現金はどちらがお得?
相続した株式を株のままで相続する場合と、売却して現金で受け取る場合では、どちらの方が得になるかは状況により変わります。
株式のままで相続すると、将来的に株価が上がり資産価値が増える可能性があり、さらに配当金を受け取れることがメリットです。
しかし、株式は常に値動きしており、値下がりすると資産価値が減少するリスクがあります。
一方で、現金で受け取るとすぐに活用できて、遺産分割しやすくなることがメリットです。
ただし、株式の売却時には譲渡所得税がかかる点に注意が必要です。
一概にどちらが得になるとはいえませんが、投資の知識や経験が豊富な人は、株式におけるリスクを軽減できる可能性があります。
反対に、投資に慣れていない人は、現金化して安定した資産運用をするほうが良いでしょう。
相続した株式を売却する方法
相続した株式を現金化したい場合は、株式を売却しなければなりません。
株式を売却する方法は以下のようなケースによって異なります。
- 相続人が個別に株式を売却する場合
- 株式を一括売却する場合
- 非上場株式を売却する場合
それぞれ詳しく解説します。
相続人が個別に株式を売却する場合
相続した株式を売却するには、株式の名義変更が必要です。
証券口座を開設し、証券会社に必要書類を提出して、株式の移管手続きを行います。
手続きが完了すれば、株式の所有権は各相続人に移るため、それぞれが自由に株を売却できるようになります。
株式を一括売却する場合
株式を相続しても全員がすぐに売却するのであれば、一括で売却し、現金を分割する方法もあります。
まずは代表となる相続人を決め、ほかの相続人はその人に委任状を提出して、株式売却を委任しましょう。
次に代表相続人が相続した株式の移管手続きを行い、名義変更した後に株式を売却します。
遺産分割協議では、この売却代金の分割方法も話し合っておきましょう。
非上場株式を売却する場合
非上場株式は証券取引所で売買できないため、相続人が買い手を探さなければなりません。
ただし、非上場株式は譲渡制限により、自由に売却できない場合が多くあります。
譲渡制限の有無や詳細は、株式を発行している会社に問い合わせることが大切です。
また、企業によっては相続などにより株式の保有者が変更されたときに、発行会社に株式を売り渡すように定めている場合もあります。
このような規定があれば、それに従って企業に株式を買い取ってもらいましょう。
相続した株式の注意点
株式を相続する際は、以下のような注意点があります。
- 利益が発生している場合、準確定申告が必要になることがある
- 未受領配当金には時効がある
- 売却のタイミングによって損をする可能性がある
- 売却益に税金がかかる
思わぬ不利益を被らないように、事前に把握しておきましょう。
利益が発生している場合、準確定申告が必要になることがある
被相続人の生前の株取引で利益が発生していた場合、「準確定申告」を行わなければなりません。
準確定申告とは、被相続人の代わりに行う確定申告のことです。
準確定申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から4か月以内であるため、早めに手続きを進める必要があります。
未受領配当金には時効がある
被相続人が生前に受け取っていない配当金がある場合、相続手続きを行うことで、相続人はその「未受領配当金」を受け取れます。
ただし、未受領配当金には受け取り期限があります。
期限は企業ごとに設定されており、3〜5年と定められていることがほとんどです。
期限を過ぎると配当金を請求できなくなるため、早めに受け取り手続きを行いましょう。
売却のタイミングによって損をする可能性がある
株式の価格は常に変動しているため、「早く現金化したい」との考えから焦って売却すると、損をする可能性があります。
できるだけ損をせずに売却するには、企業の業績や株価の動向を分析したり、市場の状況を確認したりして、適切な時期を選ぶことが大切です。
売却益に税金がかかる
相続した株式を売却して利益が発生すると、相続税とは別に利益に対して譲渡所得税がかかります。
この利益は、次の計算式で求められます。
売却益=売却金額ー売却手数料ー取得費
取得費は、被相続人が株式を取得した金額であり、相続人が取得した時点の評価額ではないことに注意してください。
納税額は、上記の売却益に譲渡所得税の税率である20.315%をかけて算出します。
なお、相続税の申告期限から3年以内に株式を売却すると、相続税を取得費に加算できる「取得費加算の特例」を利用できます。
株式の売却益にかかる譲渡所得税の負担を抑えられる制度なので、適用できる場合はぜひ活用しましょう。
株式の相続に関するよくある質問
ここからは、株式の相続に関してよくある質問に回答します。
場合によっては税負担が増えたり、損をしたりすることもあるため、よく確認しておきましょう。
株式を相続した場合の名義変更はいつまでに行う必要がある?
相続により取得した株式の名義変更には、明確な期限がありません。
ただし、相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限が定められています。
相続税の申告期限を過ぎると「無申告加算税」が、納付が遅れると「延滞税」が加算される可能性があります。
相続税の申告と納付が期限内に完了するように、株式の名義変更手続きも早めに進めましょう。
相続後数年経ってから株券が見つかった場合、相続税の申告は必要?
原則として、相続税申告の時効は5年とされています。
したがって、相続税の申告期限から5年以上経過していれば、相続税を申告しなくてもペナルティが課されることはありません。
ただし、財産を隠したり虚偽申告をしたりと脱税行為があった場合、時効は7年に延長されます。
一方で、株券が見つかったのが相続税の申告期限から5年以内であれば、相続税の申告が必要です。
通常は、相続税の申告が本来の税額よりも少なければ「過少申告加算税」の対象になります。
しかし、税務署に指摘される前に申告すれば、過少申告加算税の対象にはならないため、早めに申告しましょう。
株式の相続手続きを行わずに放置すると?
被相続人が所有していた株式をそのまま放置した場合、最終的に株式の権利が消滅する可能性があります。
株式を放置して、株式の名義が被相続人のまま変更されなければ、相続人は配当金を受け取れません。
さらに、配当金が受け取られない株式は「株主所在不明」として扱われ、株式が競売で売却されたり、企業に買い取られたりすることがあります。
所定の手続きを行えば売却代金を取り戻せますが、そのまま放置すると売却代金も請求できなくなり、株式の権利が消滅します。
被相続人が遺した資産を無駄にしないためにも、きちんと相続手続きを行いましょう。
株式の相続に関するお悩みは専門家に相談しよう
株式を相続する際には、名義変更や相続税の申告など、さまざまな手続きが必要です。
また準確定申告や未受理配当金など、株式ならではの注意点もあります。
株式は預貯金とは異なり、価格が常に変動するため、評価方法や分割方法で悩むこともあるでしょう。
株式の相続にお困りの方は、専門家に相談するのがおすすめです。
杠(ゆずりは)司法書士法人は相続の専門家として、相続に関するあらゆるお悩みの解決をサポートしています。
株式の相続に関するお悩みについても最適な解決策を提案いたしますので、ぜひ一度、杠(ゆずりは)司法書士法人にご相談ください。
相続放棄の手続きは司法書士に依頼すべき?費用や弁護士との違いを解説
相続放棄は、故人の負債を引き継ぐリスクを回避するための重要な手段です。
しかし、相続放棄の手続きは複雑で期限も定められており、一般の方が自分で申述するのは難しい場合があります。
相続放棄の手続きをスムーズに進めて確実に遺産を手放すなら、司法書士に依頼するのがおすすめです。
本記事では、相続放棄を司法書士に依頼するメリットや費用相場、具体的な手続きの流れなどについて詳しく解説します。
相続放棄を司法書士に依頼する費用相場
相続放棄を司法書士に依頼する場合、費用の相場は3〜5万円程度です。
これは司法書士への報酬であり、手続きに必要な書類の取得費用が別途発生します。
相続放棄を自分で行えば書類の取得費用だけで済むため、コストを抑えられるでしょう。
一方で、司法書士に依頼すれば、書類の取得や作成にかかる時間と手間を省けます。
相続放棄の手続きには期限があるため、忙しくて時間が取れない方や書類の準備に不安がある方は、司法書士への依頼をおすすめします。
費用の内訳
相続放棄の手続きにかかる費用の内訳は、次のとおりです。
| 収入印紙 | 800円 |
|---|---|
| 郵便切手 | 400〜500円程度 |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票(1通あたり) | 200〜300円 |
| 戸籍謄本(1通あたり) | 450円 |
| 除籍謄本または改製原戸籍謄本(1通あたり) | 750円 |
収入印紙と郵便切手は家庭裁判所に納付する費用で、それ以外は提出書類の取得にかかる費用です。
必要書類の数にもよりますが、3,000〜5,000円程度に収まることがほとんどです。
自分で相続放棄をする場合は、この実費のみがかかります。
また、司法書士に支払う依頼費用の内訳は、次のとおりです。
| 相談料(1時間あたり) | 0〜5,000円 |
|---|---|
| 申述書作成費 | 3,000〜6,000円 |
| 代理手数料 | 2〜3万円 |
上記の金額は目安なので、事前に司法書士に問い合わせて確認する必要があります。
費用が高くなる場合もある
以下のケースでは、相場以上の費用が発生する可能性があります。
- 相続放棄が可能な期限を過ぎている
- 相続財産の調査を依頼する
- 相続財産清算人を選任する
相続放棄には、相続開始を知った日から3か月以内という期限があります。
この期限を過ぎた場合、原則として相続放棄は認められません。
ただし、上申書を家庭裁判所に提出し、期限が過ぎた理由や事情が認められれば、相続放棄ができることがあります。
上申書の作成も司法書士に依頼できますが、追加で費用が発生します。
また、被相続人が所有する財産の全容を把握するために司法書士に財産調査を依頼する場合も、追加費用が必要です。
さらに、相続人全員が相続放棄をするようなケースでは、相続財産清算人を選任しなければなりません。
相続財産清算人は相続人の代わりに相続財産を管理する役割を担う人であり、必要書類を用意して家庭裁判所に申し立てを行うことで、選任手続きが可能です。
この手続きも司法書士に依頼できますが、追加費用が加算されます。
相続放棄は司法書士と弁護士、どちらに依頼すべき?
相続放棄は司法書士だけでなく、弁護士にも依頼可能です。
以下では、それぞれの専門家に依頼すべきケースについて解説します。
費用を抑えたい場合は司法書士
相続放棄を司法書士に依頼する場合の費用相場は3〜5万円程度である一方、弁護士の場合は5〜10万円程度かかります。
したがって、費用を抑えたい場合は司法書士がおすすめです。
ただし、司法書士が対応できる範囲には制限があります。
司法書士は、必要書類の取得や作成などは代行できますが、依頼者の代理人として相続放棄の手続きを進めることはできません。
そのため、家庭裁判所に申述したり照会書を受け取って返答したりするのは、依頼者が行う必要があります。
相続トラブルが起きる可能性がある場合は弁護士
弁護士は、必要書類の収集や作成だけでなく、依頼者の代理人として相続放棄の手続きを行うことが可能です。
また、訴訟にも対応できるため、相続放棄によりほかの相続人とトラブルが発生した場合でも、適切に事態を収めてもらえます。
相続人とのトラブルが不安な場合は弁護士への依頼を検討すると良いでしょう。
相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄を司法書士に依頼するメリットは、依頼費用を抑えられることだけではありません。
ほかにも、以下のようなメリットがあります。
- 必要書類の収集や作成を任せられる
- 不動産を含む遺産の相続放棄をスムーズに進められる
- 照会書に対する回答のサポートを受けられる
- 相続放棄のスケジュールを管理してもらえる
- 債権者への通知についてアドバイスを受けられる
- 手続き期限が過ぎても相続放棄できる可能性がある
- 相続放棄以外の解決策も検討してくれる
それぞれ詳しく解説します。
必要書類の収集や作成を任せられる
相続放棄を司法書士に依頼した際の中心となる業務は、必要書類の収集と作成です。
相続放棄の手続きには、次のような書類を取得して家庭裁判所へ提出する必要があります。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 親族の死亡が分かる戸籍謄本(該当する場合のみ)
戸籍謄本の取得範囲はケースによって異なり、多くの書類を集めなければならないこともあります。
司法書士に依頼すれば、必要な戸籍謄本の判断も含めて、書類の取得を代行してもらえます。
また、書類の取得だけでなく「相続放棄申述書」の作成も必要です。
相続放棄申述書は家庭裁判所に提出する申請書であり、書式が決められています。
不備のない申請書を作成するなら、法的書類の作成に詳しい司法書士に任せるのが安心です。
不動産を含む遺産の相続放棄をスムーズに進められる
相続財産に土地や建物などの不動産が含まれる場合は、相続放棄を司法書士に依頼するのがおすすめです。
相続放棄をすると、遺された不動産について管理責任や名義変更の問題が生じることがあります。
不動産登記の専門家である司法書士に依頼すれば、相続放棄後の不動産に関する対応についても的確なアドバイスを受けられます。
照会書に対する回答のサポートを受けられる
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出すると、相続放棄する人のもとに照会書が届きます。
照会書には相続放棄する人に対する質問事項が記載されており、その質問に回答して返送しなければ、相続放棄は認められません。
回答に不備があると相続放棄が認められない可能性もあるため、慎重に記入する必要があります。
照会書の回答は相続放棄する人が記入して返送する必要がありますが、回答の内容や書き方については司法書士からアドバイスを受けられます。
司法書士のサポートがあれば、自信をもって照会書に回答できるでしょう。
相続放棄のスケジュールを管理してもらえる
相続放棄の手続きには3か月以内という期限があります。
自分で相続放棄の手続きを進めていると、仕事などで忙しくて書類の収集が進まず、期限が過ぎてしまうことも少なくありません。
しかし、司法書士に依頼すれば、期限内に相続放棄が完了できるようにスケジュールを管理しながら手続きを進めてもらえます。
3か月は意外とすぐに過ぎてしまうものですが、司法書士に依頼することで期限切れのリスクを回避できます。
債権者への通知についてアドバイスを受けられる
相続放棄の手続きを進めている最中に、被相続人の債権者から借金の返済を求める連絡が届くことがあります。
この際、被相続人に代わって少額でも返済すると、借金を引き継いだと判断されて相続放棄が認められなくなる可能性があります。
とはいえ、債権者からの連絡が繰り返されると、不安やストレスを感じるでしょう。
基本的には、債権者へ相続放棄をする旨を伝える必要はありませんが、連絡を止めてほしいといった場合は相続放棄することを知らせる必要があります。
司法書士に相談すれば、債権者への対応についてもサポートを受けられるので、適切に対処することが可能です。
手続き期限が過ぎても相続放棄できる可能性がある
基本的に、相続放棄の手続き期限は3か月以内ですが、特別な事情がある場合は期限を過ぎても相続放棄が認められることがあります。
ただし、上申書を家庭裁判所へ提出して、手続き期間の延長を申し立てる必要があります。
上申書の作成には専門的な知識が必要であり、一般の方が作成しても期間の延長が認められる可能性は高くありません。
司法書士には上申書の作成も依頼できるため、3か月の期限が過ぎた方も一度相談してみると良いでしょう。
相続放棄以外の解決策も検討してくれる
相続放棄は、必ずしも最良の選択肢であるとは限りません。
司法書士は相続の専門家であるため、依頼者の状況に応じて相続放棄以外の手段も提案できます。
たとえば、被相続人には負債があると思っていたのに、実際にはプラスの資産の方が多かった、というケースもあるでしょう。
ほかにも、プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。
安易に相続放棄をすると、本来受け取れるはずの財産を失う可能性があります。
司法書士に相談して、自分にとって最適な選択肢を見つけることが重要です。
司法書士に依頼して相続放棄する流れ
司法書士に依頼した場合、次のような流れで相続放棄の手続きを進めます。
- 相続放棄するかどうかを決める
- 必要書類の収集と作成を依頼する
- 家庭裁判所に相続放棄を申述する
- 照会書に回答する
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
それぞれの内容について解説します。
相続放棄するかどうかを決める
まずは相続放棄の必要性があるのか、司法書士に相談しましょう。
前述のように、相続放棄以外の解決策を提案してもらえるかもしれません。
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。
どちらの財産が多いか分からない場合は、被相続人の財産を全て洗い出す「財産調査」を司法書士に依頼することも可能です。
司法書士と話し合い、相続放棄が本当に必要か判断しましょう。
必要書類の収集と作成を依頼する
相続放棄を行うことが決まれば、家庭裁判所に提出する書類を収集し、相続放棄申述書を作成する必要があります。
司法書士に相続放棄を依頼すれば、この作業をまるごと任せられます。
書類が不足していたり申述書に不備があったりすると、相続放棄が却下されるかもしれません。
しかし、公的証明書の収集や法的書類の作成に精通している司法書士であれば、確実に手続きを進められます。
家庭裁判所に相続放棄を申述する
用意した書類を家庭裁判所へ提出し、相続放棄を申述します。
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄の期限である3か月以内に相続放棄申述書を提出できれば、ひとまず手続きを進められます。
司法書士に依頼すると、余裕をもったスケジュールで申述できるため、期限を過ぎる心配はありません。
照会書に回答する
申述書を提出してから約1〜2週間後に、相続放棄する人のもとに照会書が届きます。
照会書には、以下のような質問が記載されています。
- 被相続人が亡くなったことをいつ知ったか
- 相続財産を使ったか
- 相続放棄をする理由は何か
- 遺産分割を行ったか
これらの質問に正しく回答しなければ、相続放棄が認められない可能性があります。
「回答の書き方が分からない」「回答の内容に不安がある」といった場合でも、司法書士に相談するとアドバイスを受けられます。
ただし、回答の記入と返送は、相続放棄する本人が行う必要があることに注意しましょう。
相続放棄申述受理通知書を受け取る
照会書の回答を返送して問題がなければ、約1〜2週間後に裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これは、相続放棄が正式に認められたことを知らせる書類です。
この通知書が届けば、相続放棄の手続きは完了となります。
司法書士に相談してから相続放棄の手続きが完了するまでの期間は、1〜2か月程度が目安です。
相続放棄と司法書士に関するよくある質問
ここでは、司法書士に相続放棄の手続きを依頼する際によくある質問に回答します。
司法書士への依頼前に知っておきたいポイントを解説するので、確認しておきましょう。
司法書士への依頼費用を抑える方法はある?
相続放棄を希望する相続人が複数いる場合、同じ司法書士にまとめて依頼すると、一人あたりの依頼費用を抑えられる可能性があります。
必要書類の収集などの作業を一括で行えば、司法書士の負担が軽減されるためです。
被相続人の負債が多く、遺産総額がマイナスであれば、相続人全員が相続放棄を選択することは珍しくありません。
このような場合は、同じ司法書士への依頼を検討してみましょう。
司法書士に費用を支払うのはいつ?
司法書士事務所によって異なりますが、書類の収集や作成が完了した時点で支払うケースが一般的です。
ただし、業務開始前に着手金の支払いが求められたり、実費のみを先に請求されたりする場合があるため、事前に確認しておきましょう。
相続放棄の手続きをスムーズに進めるなら専門家に依頼しよう
相続放棄を司法書士に依頼すると、費用を抑えられる可能性があります。
さらに、不動産の相続放棄をスムーズに進められる、照会書の回答や債権者の通知などについてアドバイスを受けられるなどの数多くのメリットがあります。
専門知識をもつ司法書士のサポートがあれば、安心して相続放棄の手続きを進められるでしょう。
相続放棄について専門家に相談したい方は、杠(ゆずりは)司法書士法人までお問い合わせください。
杠(ゆずりは)司法書士法人では、相続に関する豊富な知識と経験を活かし、相続放棄をはじめとするさまざまなご相談に対応しています。
相続放棄に関するお悩みの解決もお手伝いいたしますので、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
本記事に関する連絡先
TEL: 06-6253-7707
メールでのご相談はこちら >>