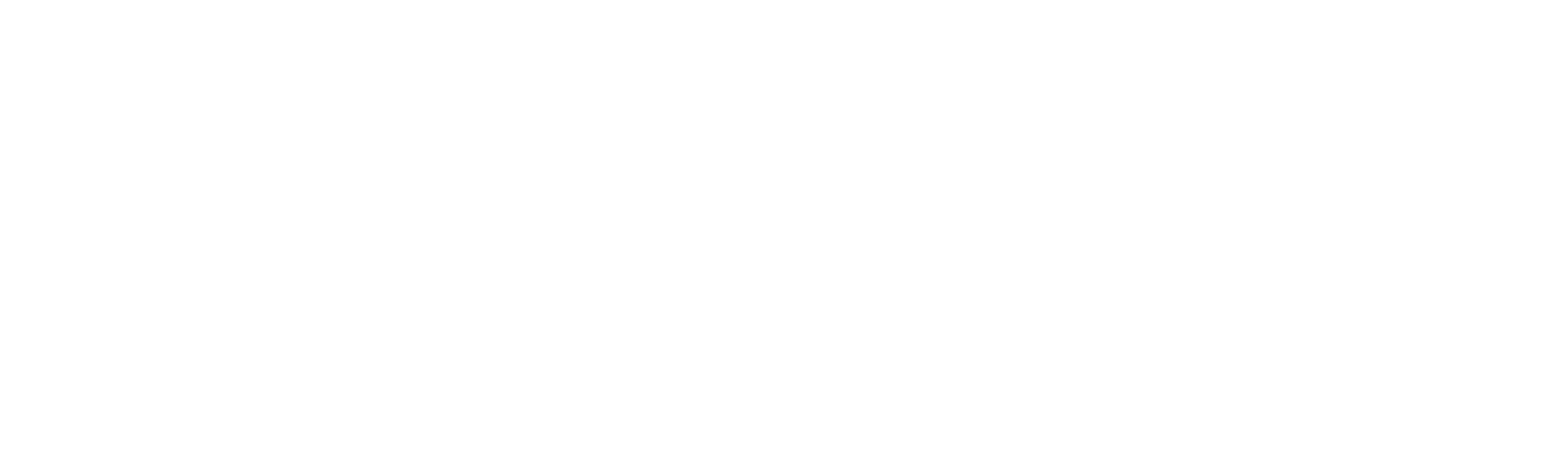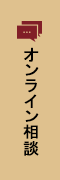相続財産調査の依頼費用は?調査方法やどの専門家に依頼するべきかについて解説
投稿日:2025.01.08

家族が亡くなり、相続が発生したら相続手続きを行わなければなりません。
そのなかでも、相続財産調査は遺産分割や相続税申告など、後の手続きをスムーズに進めるために重要な役割を果たします。
しかし、「相続財産調査」という言葉自体に馴染みがない方も多く、どこから手をつければ良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続財産調査の依頼費用や具体的な調査方法、そしてどの専門家に依頼するのが最適かについて詳しく解説します。
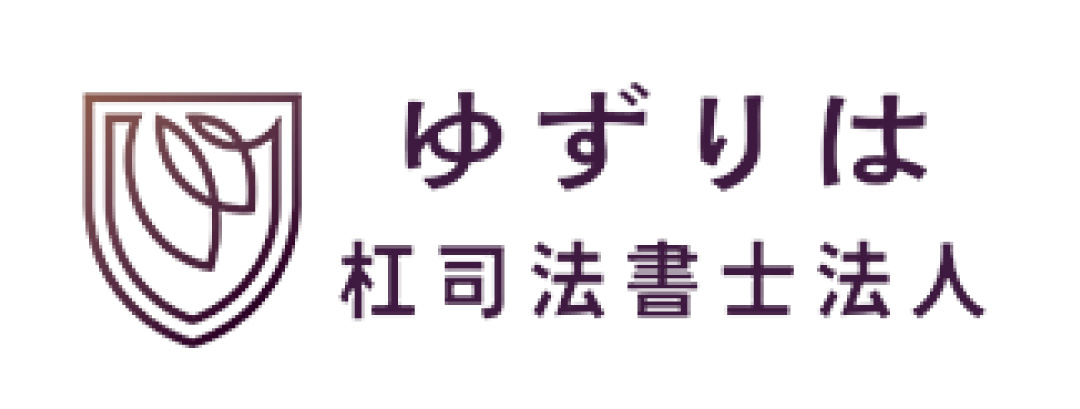
大阪・兵庫・京都・東京を拠点に、相続手続き・遺言書作成・家族信託契約などのサポートから企業法務まで、専門のチームで対応しております。税理士や他業種との連携により、相続問題をワンストップで解決!相続関連の相談件数は年間400件超。
目次
専門家に相続財産調査を依頼する費用
相続財産調査が必要になったとき、専門家に依頼しようと考える方が多いのではないでしょうか。
依頼する専門家や調査の範囲によって、費用は大きく異なります。
専門家によって対応できる内容が変わるので、費用だけではなく、自分の目的にあった内容を依頼できるかも見ておくと良いでしょう。
専門家ごとに対応できる範囲と費用は以下の通りです。
| 専門家 | 費用 | 対応範囲 | 調査期間 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 20~60万円程度 | 相続手続きのほぼすべてを代行可能 | 1~2ヵ月 |
| 司法書士 | 10~30万円程度 | 各種調査も可能 | 1~2ヵ月 |
| 税理士 | 財産額のおよそ0.5~1% | 相続税の申告業務 | 2ヵ月 |
| 行政書士 | およそ数万円~ | 不動産業務を含まない代行業務 | 1ヵ月 |
| 信託銀行 | およそ100万円~ | 必要に応じてそれぞれの専門家への橋渡し | 遺産整理全体として10ヵ月 |
弁護士|20〜60万円程度
弁護士に支払う費用の相場は、20~60万円程度です。
法律問題に強い専門家で、ほぼすべての手続きを代行できます。
複雑で難しい相続内容や訴訟問題も取り扱えます。
相続人の間でトラブルが起きて訴訟に発展したとき、交渉権限がある専門家は弁護士だけです。
トラブルになるのが予測できるときには、最初から弁護士に依頼するのが賢明です。
ほかの専門家に比べて依頼できる内容が多く、法律全般でオールマイティに対応できます。
ただし、その分費用が高額になることは覚えておきましょう。
費用を気にしないのなら、「どの専門家に頼めば良いかわからない」というときにもおすすめです。
司法書士|10〜30万円程度
司法書士に支払う費用の相場は、10~30万円程度です。
登記手続きの専門家なので、不動産登記や遺産分割協議書の作成など、相続に関わる手続き全般を得意とします。
相続では不動産を相続するケースも多いので、司法書士の出番が多いです。
不動産以外にも相続関連の書類作成など、関連する手続きを請け負ってくれます。
弁護士のように訴訟への対応はできませんが、話し合いが相続人同士でスムーズにできるなら、司法書士に依頼するほうが費用を抑えられます。
訴訟を依頼するなら弁護士、依頼しないなら司法書士と、状況に応じて選ぶと良いでしょう。
税理士|遺産総額の0.5%〜1.0%
税理士に支払う費用の相場は、遺産総額の0.5~1%です。
税金に関する専門家で、相続税の申告や節税対策など、税務に関する業務が得意です。
遺産総額が基礎控除額を超えた場合には、相続税を納めなければなりません。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の数」です。
相続人が1人なら3,600万円、2人以上なら人数に合わせて増えていきます。
相続税があまりにも高額なら、節税ができないかを税理士に相談するのもよいでしょう。
行政書士|5万円程度
行政書士に支払う費用の相場は、5万円程度です。
行政手続きの専門家で、官公署に提出するための書類作成や比較的簡単な手続きの依頼に適しています。
依頼する内容は相続財産調査と書類作成のみとなるので、費用は抑えられる傾向にあります。
ほかの専門家に比べると対応できる範囲が狭くなりますが、不動産の相続や訴訟の可能性もなく、相続手続きが複雑化しないのであれば、行政書士へ依頼しても良いでしょう。
ただし、相続財産調査を行った結果、把握していなかった不動産が見つかることもあります。
その場合は、不動産の相続登記が必要になるので、改めて司法書士や弁護士に依頼をし直すことになります。
信託銀行|100万円程度
信託銀行に支払う費用の相場は、100万円程度です。
遺産全体を管理・運用するサービスを提供しています。
全ての手続きを信託銀行が窓口となって引き受けるので、窓口の一本化ができるところがメリットです。
どの専門家にどの手続きを依頼するかを熟知したプロが、相続人に代わって判断し手配します。
相続人は一切を信託銀行に任せれば良いので、それぞれの専門家に相談しに行く手間も省け、最も楽な方法といえるでしょう。
ただし、費用は自分で専門家を見つけるよりも高額になります。
「費用はかかっても良いから、時間と手間を最大限に省きたい」という方に向いています。
信託銀行と普段から付き合いのある方なら、安心して任せられるでしょう。
相続財産の調査方法
相続する財産には、以下のものがあります。
- 預貯金
- 不動産
- 有価証券
- 借金
相続手続きでは、これらの財産全てを正確に把握しなければなりません。
それぞれに必要な書類や調査内容は、以下の通りです。
預貯金
相続財産の調査として、まずは預金通帳から探していくのが近道です。
預金通帳が見つかればお金の取引履歴が分かり、不動産収入やローンの支出も見つけやすくなります。
手がかりになるものは次の通りです。
- 通帳
- キャッシュカード
- 銀行からの郵便物
- 銀行のパンフレットやノベルティ
- スマホやパソコンの中身
通帳のないネットバンクもあるので、スマホやパソコンの中身が確認できるなら、検索履歴やアプリ、メールなどもチェックしていくと良いでしょう。
銀行の資料や関連のありそうなメモも見逃してはいけません。
少しでも手がかりがあれば、金融機関に残高証明書を請求して確認しましょう。
取り引き履歴を知るために、履歴のわかるものも一緒に請求しておくと良いです。
不動産
所有している不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得すれば記載されています。
取得するには、相続する不動産の「地番」や「家屋番号」が必要です。
「地番」や「家屋番号」は住所と異なっている場合もあり、1つの土地に見えても2つに分割されていることもあります。
見ただけでは判断が難しいので、不動産のある役所から、固定資産税評価証明書や名寄帳を取り寄せて確認をします。
役所から送られてくる固定資産税課税明細書でも所有不動産が記載されていますが、課税対象にならない不動産は記載されません。
漏れがないよう、登記事項証明書(登記簿謄本)で確実に把握しましょう。
有価証券
有価証券は、紙の証券が発行されないので、書類やメールなどから手がかりを探します。
手がかりになるものは、次の通りです。
- 口座開設の書類や関連書類
- 証券会社からの郵便物
- 証券会社のパンフレットやノベルティ
- スマホやパソコンの中身
まずは、証券会社からの郵便物や口座開設の書類などから関連する書類を探します。
預貯金の調査と同じように、スマホやパソコンにログインできれば、メールやアプリを中心に取引がないかをチェックしましょう。
取引の可能性がある証券会社がわかったら、残高証明書を発行してもらうことで、有価証券の把握ができます。
あるはずなのに見つからず、調査が難航してしまうなら、証券保管振替機構に問い合わせをしてみましょう。
情報を開示してくれます。
借金
借金やローンなど、マイナスの財産も相続の対象になります。
手がかりになるものは、次の通りです。
- 貸金業者からの督促状
- 返済の明細書
- 消費者金融のキャッシュカード
- パソコンやスマホの中身
見つけたらすぐに借入先に連絡を取り、返済金額の確認をしましょう。
調査が難しいなら、信用情報機関に情報開示を求められます。
情報機関は3つに分かれるので、心配なら3つ全てに問い合わせれば、大体の借入を洗いだせます。
プラスよりもマイナスの財産のほうが多くなってしまう場合は、相続放棄を考える方が多いでしょう。
相続放棄は、自分が相続人になったと知った日から3ヶ月以内に申請をしなければならないので、借金の把握は急務といえます。
「調査が不十分で、あとから思いもよらない借金が出てきてしまった」ということにならないよう漏れなく調査をしましょう。
相続財産調査の必要性
相続財産調査は、単に故人の財産を把握するだけでなく、相続手続きをスムーズに進めるために不可欠です。
調査をしておかないと、どのような支障があるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
遺産の分割を正しく行うために必要
相続する財産が正しく把握できなければ、正しい遺産分割もできません。
故人の全ての財産を洗いだすのは膨大な労力と時間がかかりますが、まずは正しく調査することが重要です。
相続手続きの出発点ともいえる調査なので、ここでつまづいてはあとから行う手続き全てに支障が出ます。
正確に把握できてはじめて、間違いのない遺産分割が始められるのです。
「調査に漏れがあり、正しく遺産分割できていなかった」という事態にならないようにしましょう。
遺産分割を円滑に進めるために必要
相続財産の調査が不十分で、あとから把握していない財産が見つかるのは、避けたい事態です。
せっかく相続人の間で遺産分割の話がまとまったとしても、もう一度やり直さなければなりません。
それぞれが遠方から集まらなければならないのなら、手間も時間もより一層かかります。
訴訟に発展して終結を迎えたようなケースでは、やり直しとなれば心の疲れも尋常ではないでしょう。
円滑に進めるためには最初から十分な相続財産調査を行うことが大切です。
相続放棄を判断するために必要
相続財産調査は、所有している財産を把握するためだけのものではありません。
借金やローンなど、マイナスの財産がないかを調べる目的もあります。
プラスの財産ばかりに目が行きがちですが、マイナスの財産をすべて把握しなければ、相続放棄の判断ができません。
相続放棄は3ヶ月以内に手続きが必要と期限が決まっています。
最初に正確に調査をして、マイナスの財産を知っておくのは非常に重要です。
相続人が損をしないためにも、調査は漏れなく迅速に行いましょう。
相続財産調査はどの専門家に依頼する?
「相続財産調査をどの専門家に依頼すれば良いかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
相続の状況によって、どの専門家が適しているかは変わります。
それぞれの専門家が対応できる相続財産調査の範囲は、以下の通りです。
| 弁護士 | 司法書士 | 税理士 | 行政書士 | |
|---|---|---|---|---|
| 相続財産調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 戸籍収集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 不動産の相続登記 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 相続放棄 | 〇 | △ | △ | △ |
| 遺産分割協議書の作成 | 〇 | △ | △ | △ |
| 相続トラブルの解決 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 相続税の申告 | △ | ✕ | 〇 | ✕ |
どのようなときにどの専門家に依頼すればよいのか、具体的に例をあげて見ていきましょう。
弁護士|相続トラブルがある場合
弁護士の強みは、訴訟問題を扱えることです。
相続トラブルに対応してほしいなら、弁護士に依頼するのが適しています。
相続人が複数いると、遺産分割でトラブルになり訴訟に発展するケースがあります。
自分たちで最後まで話し合う方法もありますが、間に第三者が入ってほしい場合には、弁護士に介入を依頼するのが一般的です。
専門家のなかでも交渉の権限をもっているのは弁護士だけです。
費用は高額になりますが、自分で交渉する自信がなければ弁護士に相談しましょう。
司法書士|財産に不動産が含まれている場合
司法書士は不動産登記を得意としています。
相続する財産に不動産がある場合は、司法書士に依頼するのがおすすめです。
不動産の相続登記の手続きは、税理士や行政書士には対応できない範囲なので、弁護士か司法書士に依頼することになります。
ただし、弁護士は費用が高くつく傾向にあるので、訴訟なしで不動産を相続する場合なら司法書士に依頼するのがおすすめです。
税理士|相続税の申告が必要になる場合
相続税がかかり、申告手続きや節税対策を任せたいなら税理士に相談するのがおすすめです。
ほかの専門家ではカバーしきれない豊富な税金の知識があり、相談することで節税できる可能性があります。
ただし、ほかの専門家とは業務内容が大きく異なり、税務に特化しています。
相続税に関しては税理士に依頼して、対応できない相続登記は司法書士へ依頼するなど、内容ごとに依頼先を分けるのが良いでしょう。
行政書士|書類作成のみを代行してもらいたい場合
相続財産調査と書類作成のみを依頼したいなら、行政書士に任せても良いでしょう。
対応できる範囲が限られるので、自分の相続の内容に合っているかは先に確かめなければなりません。
不動産の相続登記が必要だったり、訴訟に発展したりするような複雑なケースでは、行政書士の対応範囲外となってしまいます。
そのような場合は、ほかの専門家を探さなければなりません。
最低限の書類作成だけで済ませられる場合は、行政書士に依頼しましょう。
目的に合わせて相続財産調査を専門家に依頼しよう!
この記事では、相続財産調査にかかる費用や必要性、どの専門家に依頼するのが最適かについて解説してきました。
相続財産調査は相続手続きのスタート地点であり、調査が正しくできていないと全ての手続きに影響を及ぼします。
手続きのやり直しや、相続人の金銭的損失につながることのないよう、漏れなく正確に行うことが重要です。
杠(ゆずりは)司法書士法人では、随時相談を受け付けています。
次のような方は特に相談をおすすめします。
- 相続遺産調査を自分で正確にできる自信のない方
- 相続遺産調査でミスをしたくない方
- 手続きに十分な時間が取れない方
- 不動産を相続する可能性のある方
- 相続遺産調査以外にも相続手続き全般を依頼したい方
当てはまるものがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
本記事に関する連絡先
TEL: 06-6253-7707
メールでのご相談はこちら >>