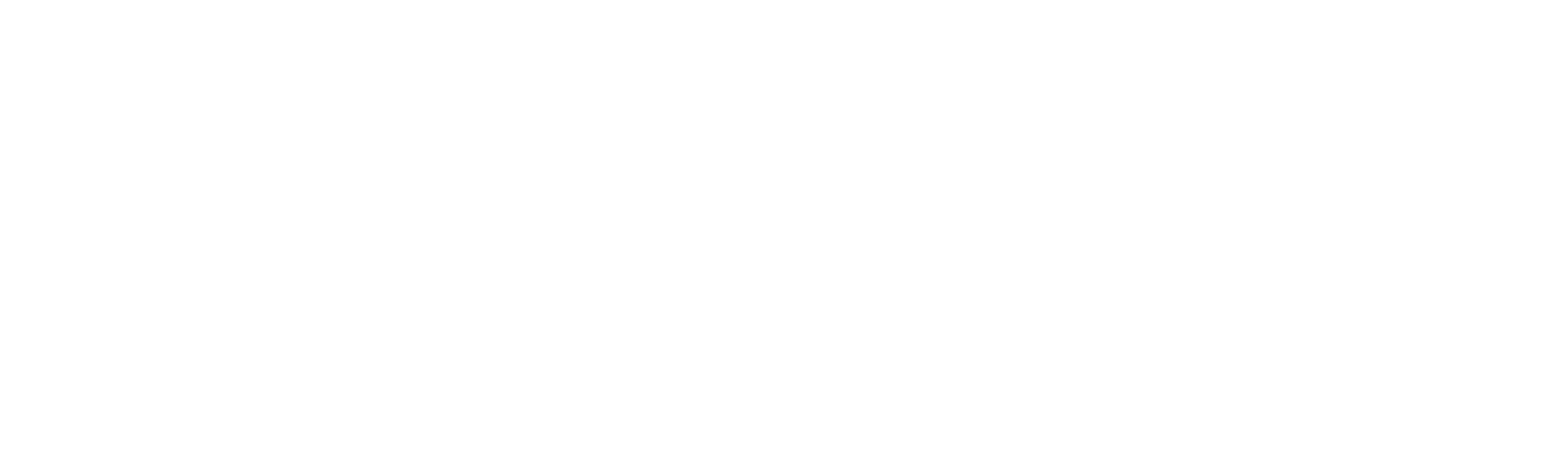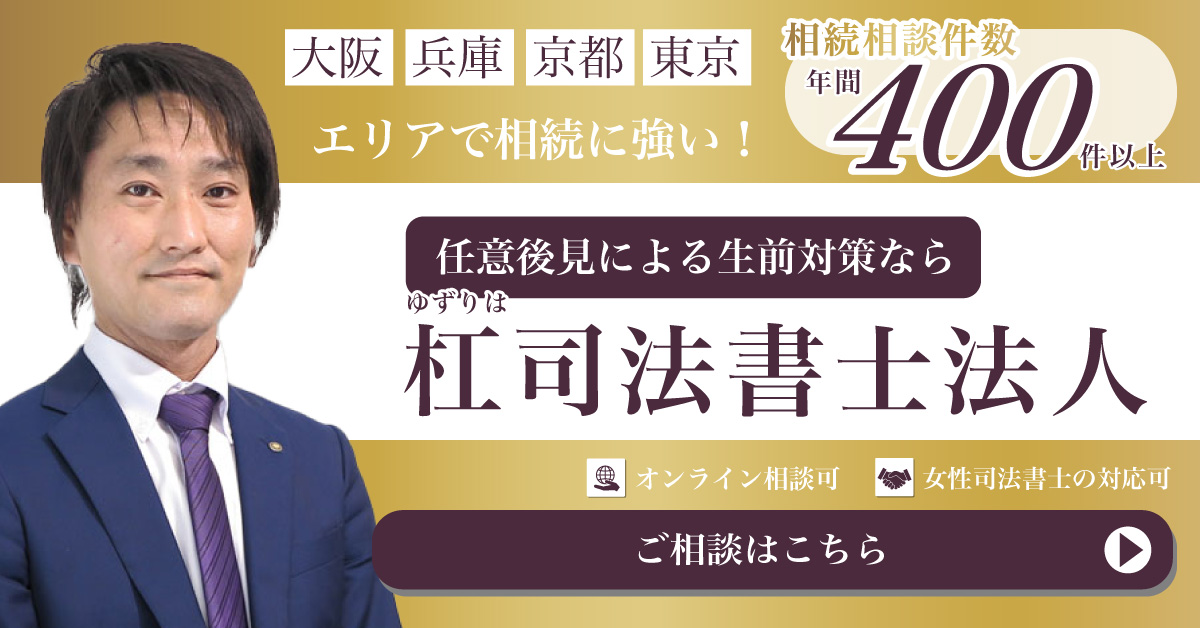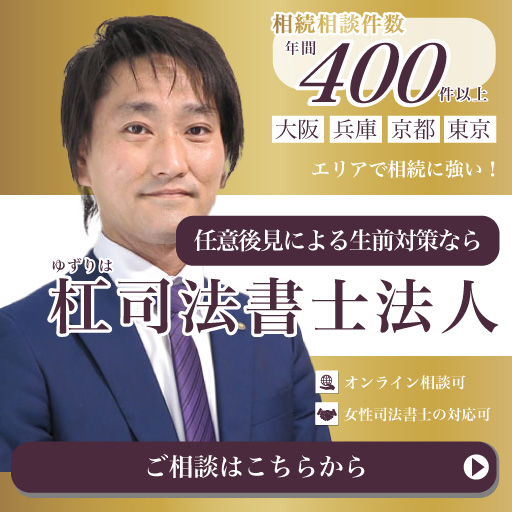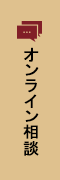任意後見で相続対策できる?活用するメリットや注意点を解説
成年後見
投稿日:2025.04.14

任意後見制度とは判断能力が低下した本人に代わって、財産管理や身上監護などを行う後見人を選ぶ制度のことです。
相続対策の一つとしても注目されていますが、「どのような流れで行うのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、任意後見制度を活用する流れや相続対策、制度を利用することで生じるメリット・デメリットについて解説します。
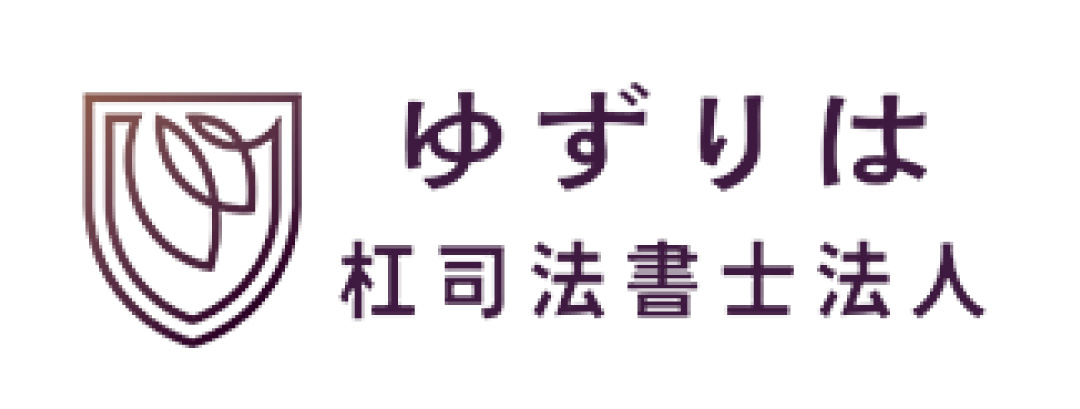
大阪・兵庫・京都・東京を拠点に、相続手続き・遺言書作成・家族信託契約などのサポートから企業法務まで、専門のチームで対応しております。税理士や他業種との連携により、相続問題をワンストップで解決!相続関連の相談件数は年間400件超。
目次
任意後見人は本人に代わって財産管理や身上監護を行う
任意後見人とは成年後見制度の一つで、任意後見制度に基づいて契約するものです。
認知症や病気、障がいなどで本人の判断能力が低下した場合に備えて、本人に代わって財産管理や身上管理を委任する人を選び、あらかじめ契約を結んでおきます。
この契約を「任意後見契約」、契約を結んだ人のことを「任意後見人」と呼びます。
任意後見人にできることの範囲は後ほど詳しく解説しますが、制度の趣旨に沿ったものであれば委任内容や範囲については、個々の状況に合わせて自由に決めることが可能です。
任意後見と法定後見の違い
任意後見は判断能力が低下した人をサポートする制度ですが、よく似たものとして「法定後見」があります。
任意後見は、本人と後見人が契約を結ぶことで開始されるのに対し、法定後見は法律に基づいて権限が与えられる点が大きな違いです。
任意後見法定後見の主な違いとして、以下が挙げられます。
| 任意後見 | 法定後見 | |
|---|---|---|
| 利用できる人 | 判断能力がある人 | 判断能力が不十分、もしくは全くない人 |
| 後見人の選出 | 本人が決める | 家庭裁判所が選任する |
| 利用方法 | 本人と任意後見人が公正証書により契約 | 家庭裁判所に申し立て |
| 代理権 | あらかじめ契約で定めた行為の範囲のみ代理権あり | 本人が行うすべての法理行為について代理権あり |
| 取消権 | なし | あり (日常生活に関する行為を除く) |
| 本人の同意 | 基本的には必要 | 基本的には不要 |
| 開始時期 | 本人の判断能力が低下した時 | 後見人が選任された二週間後に審判が確定した時 |
| 終了時期 | 本人の死亡 | 本人の死亡 |
財産管理や身上監護について代理権を持つという点は同じですが、任意後見人には取消権がありません。
一方で、相続税対策や資産運用を行える可能性があるのは任意後見人だけであるという点に注意しましょう。
任意後見人にできること
任意後見人は契約内容に基づき、本人の生活をサポートするためのさまざまな契約や、財産を管理するための手続きを行います。
以下では、任意後見人が行える財産管理と身上監護の具体例を紹介します。
財産管理
任意後見人が対応できる財産管理の内容は、以下があります。
- 預貯金の管理や金融機関での手続き
- 光熱費や税金、保険料などの支払い
- 生活必需品などの購入
- 税金や保険料などの還付手続き
- 債権の回収
- 年金の受領
ほかにも本人の兄弟姉妹や子どもが亡くなり、相続が発生した場合の遺産分割も財産管理にあたります。
ただし、本人と任意後見人がどちらも相続人になっている場合は、利益相反が生じるので遺産分割に参加することはできません。
その場合は、任意後見監督人が代わって遺産分割協議に参加することになります。
任意後見人は本人の不利益にならないよう財産を適切に管理するのはもちろん、収支や理由を明確にすることが求められます。
身上監護
任意後見人が対応できる身上監護の内容は、以下のとおりです。
- 介護契約や福祉サービスの契約手続き
- 介護施設入所の契約手続き
- 通院や入院などの契約や諸手続き
- 賃貸借契約の締結
身上監護は本人の心身状態に合わせて、最適な支援を行う必要があります。
そのため、対応可能な支援範囲は広いですが、本人の意思や利益を最優先に考え、支援方針を決めることが大切です。
任意後見を利用すれば相続対策できる?
後見制度は本人の財産価値を保全し、日々の生活をサポートすることを目的としています。
そのため、相続対策のように本人ではなく相続人のためになる支援は、原則として行うことができません。
特に法定後見制度は支援できる範囲が狭く、生前贈与や寄付、投資、不動産の売却なども支援の対象外になるので、実質的には資産が凍結することになります。
一方、任意後見制度では、契約の段階で特定の相続対策を任意後見人に託すことが可能です。
契約書に具体的な内容を記載することで、以下のような資産管理や相続対策を実行できます。
- 判断能力が残っているうちに生前贈与をする
- 施設入所にあたって、居住用不動産を売却する
- 株式や投資信託の運用を継続する
任意後見契約書に明記することで、自分の意思に沿った相続対策や資産運用を後見人に委ねることが可能となります。
任意後見を相続対策に活用するメリット
任意後見を相続対策に活用するメリットとして、以下の5点が挙げられます。
- 認知症による財産凍結を防ぐ
- 必要に応じた財産の保全・運用ができる
- 遺産の分割準備がしやすい
- 認知症の発症後でも財産管理を継続できる
- 家族・親族間のトラブル防止につながる
それぞれの項目について詳しく解説します。
認知症による財産凍結を防ぐ
近年、認知症に伴う資産の凍結リスクが問題になっています。
預貯金をはじめとする資産を動かすには本人の意思確認が大前提です。
しかし、認知症などで判断能力が低下して意思確認ができないと、まとまった額を動かせず、実質的に財産が凍結されてしまいます。
そこで活用できるのが任意後見制度です。
任意後見人が本人の意思に基づいて財産を管理するので、判断能力が低下したあとも財産の凍結を防ぐことができます。
必要に応じた財産の保全・運用ができる
任意後見制度においては、任意後見契約であらかじめ委任された内容の運用や、財産保全のための事務を行うことができます。
また、法定後見制度に比べて契約の自由度も高いので、本人の意思をきめ細かく反映した資産運用や柔軟な対応ができるのも特徴です。
遺産の分割準備がしやすい
相続においてトラブルの原因になりやすい資産として、不動産や金融資産が挙げられます。
額が大きくなりやすいことに加えて、分割して引き継ぐことが難しいため、不動産が複数あると相続は複雑になりがちです。
遺産の分割準備として、たとえば「不動産を売却して介護費用や医療費に充てる」「不動産や金融資産は売却して預貯金にする」などの契約を結ぶことができます。
任意後見契約はあくまで本人のためのものなので、財産管理の延長線上であるという認識は必要です。
しかし、分割が難しい資産を計画的に整理できるという点は、いずれやってくる遺産の分割においてもプラスに働くでしょう。
認知症の発症後でも財産管理を継続できる
任意後見契約では本人の判断能力が低下したあとも、契約内容にしたがって財産管理を継続することが可能です。
財産管理や運用は長期的な計画になることも多いですが、認知症の発症で計画が頓挫したり、本人にとって不利な結果になってしまうことも考えられます。
任意後見契約では、本人が元気なうちに計画した財産の管理方法や方針を任意後見人が実行します。
認知症の発症後でも本人の意思を反映した長期的な財産管理が行えるのは、大きなメリットです。
家族・親族間のトラブル防止につながる
家族や親族間のトラブルは、口約束や思い込みが原因で発生しやすいものです。
しかし、任意後見契約では、本人の意思が明確に契約に盛り込まれるため、誤解や争いを未然に防ぐことが期待できます。
また、任意後見人の事務が適正に行われているかについては、任意後見監督人がチェックする仕組みがあり、勝手な運用を防ぐことができます。
任意後見制度を利用する際の流れ
任意後見制度を利用する際には、どのような手順で進めるのでしょうか。
一般的な流れは、以下のステップで行います。
- STEP1:信頼できる任意後見人を選ぶ
- STEP2:任意後見契約を結ぶ
- STEP3:家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てる
- STEP4:任意後見人による後見業務を開始する
4つのステップを紹介します。
STEP1:信頼できる任意後見人を選ぶ
本人の判断能力が低下したあと財産管理や身上監護を担う、任意後見人になる人を指名します。
任意後見人になれる人の範囲は幅広く、家族や友人だけでなく、弁護士や司法書士といった専門家を選ぶことも可能です。
指名された人は「任意後見受任者」となり、契約が発効した時点から任意後見人となります。
財産や身上といった重要な事柄を任せられる人柄や信頼関係、必要な知識を持った人を選ぶことが大切です。
STEP2:任意後見契約を結ぶ
任意後見人に委任する支援内容や希望、その範囲を決めていきます。
「入院が必要になったら、〇〇銀行の定期預金を解約して賄ってほしい」「所有している株式を一定のタイミングで売却してほしい」など、ライフプランに応じた支援内容を契約書に細かく盛り込んでいきます。
場合によっては専門家のアドバイスも受けつつ、さまざまな場面を想定した詳細な内容を記載することが大切です。
任意後見契約書は公正証書として作成され、公証人が登記申請を行ないます(「登記を嘱託する」といいますが、弁護士や司法書士ではなく役所などが職権で登記してくれることを嘱託登記と言います。)。
登記から2~3週間後に「登記事項証明書」が発行され、正式に任意後見受任者として認められます。
STEP3:家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てる
本人の判断能力が低下してきて支援が必要な段階になったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てを行います。
面談や精神鑑定を経て、問題がなければ任意後見監督人が選任されます。
任意後見監督人の候補希望を本人側から出すこともできますが、必ずしも考慮されるとは限りません。
特に希望がなければ弁護士や司法書士、福祉の専門家などが選任される傾向が強いようです。
STEP4:任意後見人による後見業務を開始する
将来、もし本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てることになります。問題がなければ、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約が発効します。
任意後見人が後見事務を行うには、登記事項証明書を提示することが必要です。
任意後見を利用する際の注意点
任意後見を利用する際の注意点として、以下のようなものが挙げられます。
- 報酬が必要になる
- 亡くなったあとの事務は依頼できない
- 任意後見監督人の解任は原則できない
それぞれ詳しく解説します。
報酬が必要になる
任意後見人と任意後見監督人には、本人の財産から報酬を支払う必要があります。
任意後見人の報酬は契約書の作成時に取り決めますが、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所によって決定されます。
任意後見監督人の報酬相場は、以下のとおりです。
| 財産の総計 | 月額費用 |
|---|---|
| 5,000万円以下 | 5,000円~2万円 |
| 5,000万円以上 | 2万5,000円~3万円 |
専門家に依頼した場合は、さらに高額になることもあります。
任意後見制度を利用する限り必ず必要になるコストではありますが、年単位で考えるとそれなりに大きな出費です。
本人の財産や必要になる費用とあわせて、慎重に検討することが大切です。
亡くなったあとの事務は依頼できない
任意後見制度は本人の存命中に行われるもので、本人が死亡した時点で任意後見契約は終了します。
そのため、本人が亡くなったあとの葬儀や埋葬、死後事務などを任意後見契約で委託することはできません。
これらの事務を依頼するには、死後事務委任契約を別途締結する必要があります。
実際に、亡くなったあとのことを考え、任意後見契約と死後事務委任契約をセットで締結する方も少なくありません。
どのようなかたちがベストなのかは、本人の状況や財産、収支などによって異なるので、専門家のアドバイスを受けながら進めていくことをおすすめします。
任意後見監督人の解任は原則できない
任意後見監督人は家庭裁判所によって選任されるため、任意後見契約書に候補者を記載しておいたとしても、そのとおりになるとは限りません。
もし意に沿わない人が任意後見監督人になったとしても「自分の望んだ人でないから」「なんとなく合わないから」などの理由で、解任や選任のやり直しを要求することはできません。
任意後見監督人を解任できるのは、適切に業務を行っていない場合や不正行為などにより、監督人としてふさわしくないと家庭裁判所が判断した場合のみです。
本人や任意後見人の意向だけで解任はできない点に注意しましょう。
相続対策なら杠(ゆずりは)司法書士法人までご相談ください
任意後見制度は本人の意向に基づいて、判断能力が低下したあとも安全に自分らしく生活できるよう支援する制度です。
相続目的のみでの利用は認められていませんが、財産を適切に管理・保全することで相続をスムーズに進める効果を期待できます。
杠(ゆずりは)司法書士法人では、任意後見制度や相続に関するご相談を受け付けています。
任意後見制度を利用したいが後見人を依頼できそうな人がいない、亡くなったあとのことも含めて支援を受けたいなど、ご依頼主様の状況に合わせて、法律のプロがサポートいたします。
将来に備えて任意後見制度の利用を検討している方は、どうぞお気軽にご相談ください。
本記事に関する連絡先
TEL: 06-6253-7707
メールでのご相談はこちら >>