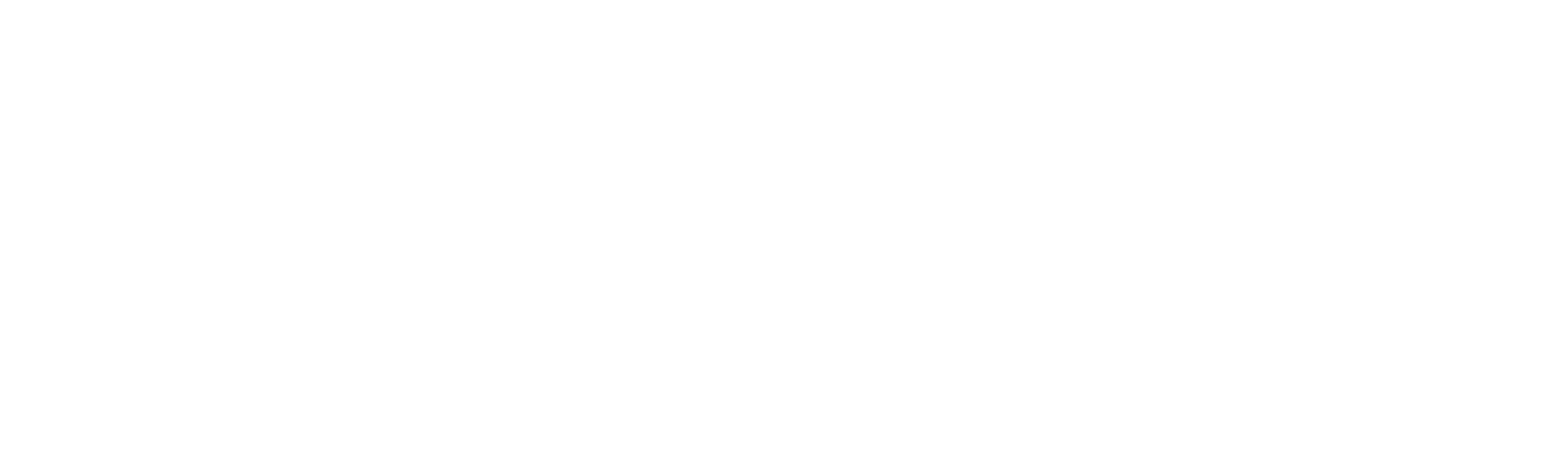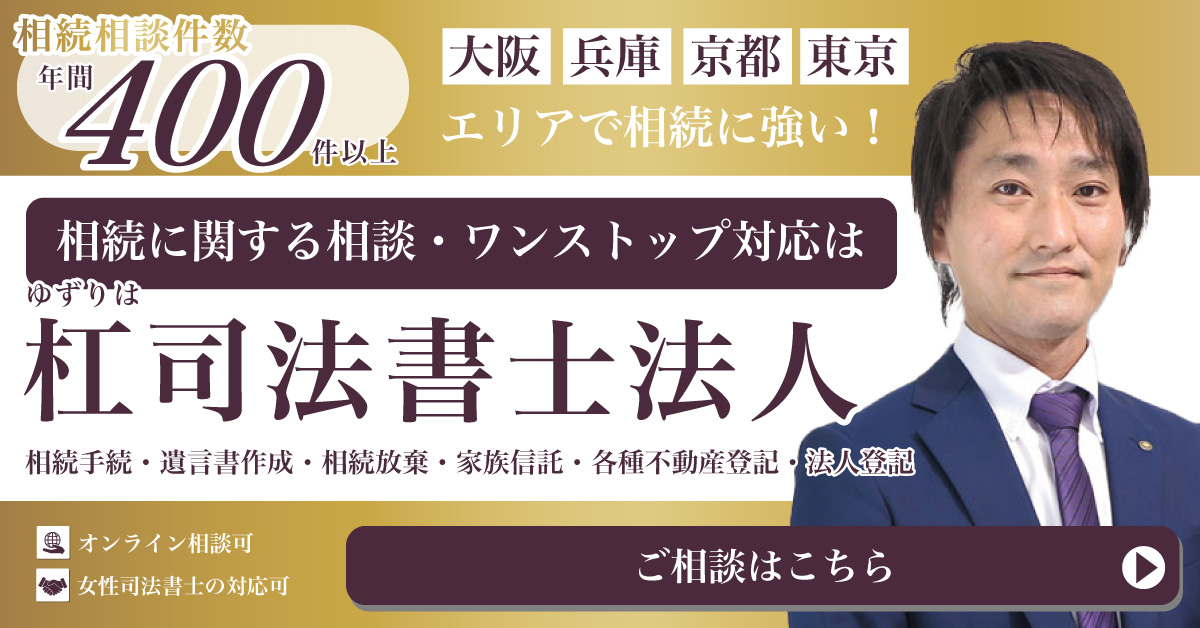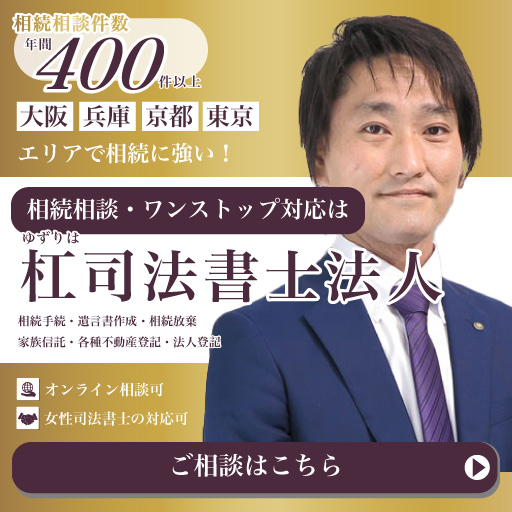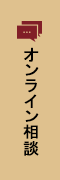遺贈と相続の違いは?流れや司法書士に依頼したほうが良いケースを解説
相続
投稿日:2025.04.28

遺贈(いぞう)とは、亡くなった方が遺言書によって、財産を特定の人や団体に贈る行為のことを指します。
これは、通常の「相続」とは異なり、法定相続人(民法で定められた相続できる方)以外の方にも財産を引き継がせることができる制度です。
遺産を寄付する話や、特定の人に財産を残したいという話を耳にしたことがある方でも、遺贈と相続の違いや、どのような手続きが必要なのかまでは知らないという方も多いのではないでしょうか。
実際に遺贈を行うには、遺言書の正しい作成と内容の明確化が不可欠であり、状況によっては司法書士などの専門家の関与が必要になるケースもあります。
この記事では、遺贈を行う際の基本的な仕組みから手続きの流れ、専門家へ依頼すべき判断ポイントまでを詳しく解説します。
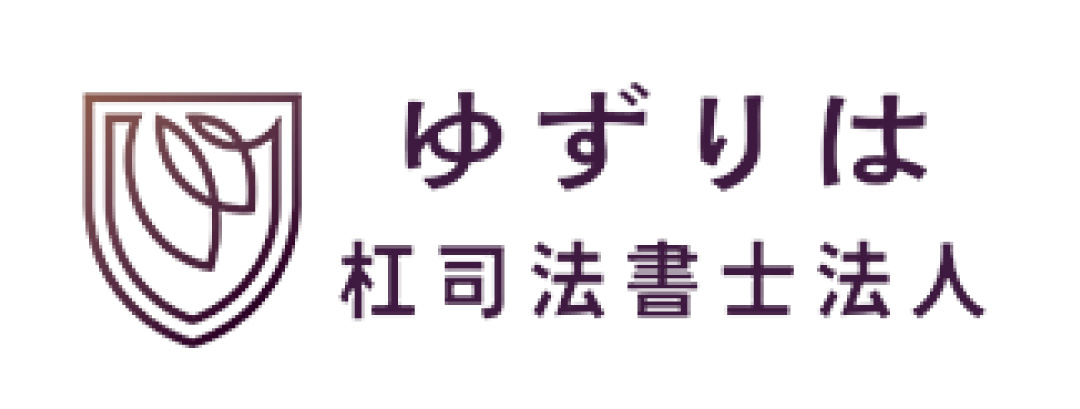
大阪・兵庫・京都・東京を拠点に、相続手続き・遺言書作成・家族信託契約などのサポートから企業法務まで、専門のチームで対応しております。税理士や他業種との連携により、相続問題をワンストップで解決!相続関連の相談件数は年間400件超。
目次
遺贈とは第三者に財産を遺す選択肢
遺贈とは、亡くなった方が遺言書を使って、特定の個人や法人に財産を引き継がせる行為のことです。
財産の全部を遺すことも、一部だけを遺すことも可能です。
通常の相続では、被相続人の財産は、民法で定められた相続人(配偶者・子など)に自動的に引き継がれます。
一方、遺贈は「遺言書に明記された内容に基づいて、特定の人や団体に財産を分配する方法」です。
この遺贈制度を使えば、法定相続人ではない第三者にも遺産を渡すことができます。
なお、法定相続人に対しても「遺言書で指定して財産を贈る」ことは遺贈にあたります。
つまり、遺贈は相続制度の補完的な指定手段として用いることもできるのです。
たとえば、以下のような相手に財産を残したい場合に遺贈が向くでしょう。
- 婚姻届を提出していない内縁のパートナー(法律上の配偶者ではないため、相続権がない)
- 養子縁組をしていない配偶者の連れ子(法定相続人ではない)
- 子どもの配偶者や孫(孫は基本的に相続権がない)
- 福祉団体やNPO法人
- 医療機関や学校
- 地方自治体などの公共団体
このように、法定相続人以外に確実に財産を遺したい場合は、遺言書による遺贈の活用が重要です。
遺言書がない場合、こうした人々や団体は一切遺産を受け取ることができません。
遺贈は包括遺贈と特定遺贈に分けられる
遺贈には大きく分けて以下の2つがあります。
- 包括遺贈
- 特定遺贈
この2つは、「どのような形式で遺産を譲るか」によって区別される方法です。
以下からは、それぞれの内容と違いをわかりやすく解説します。
包括遺贈とは
包括遺贈とは、遺産の内容を具体的に示さず、「全体の割合」だけを指定して遺贈する方法です。
たとえば、次のような指定が包括遺贈にあたります。
- 「すべての財産を母校に贈る」
- 「財産の1/2を孫に、残りの1/2を福祉団体に」
この場合、遺言書にどの財産を渡すのか細かく書かれていなくても、遺贈を受けた側(受遺者=じゅいしゃ)は、その割合に応じて故人のすべての財産を引き継ぐことになります。
重要なポイントは、借金やローンといったマイナスの財産も含まれるという点です。
つまり、包括遺贈の受遺者は、相続人と同じように、故人の債務(借金など)も負担する立場になります。
このため、包括遺贈を受けるかどうかを判断するには、事前に財産の全体像を把握しておく必要があります。
特定遺贈とは
特定遺贈とは、どの財産を誰に渡すかを遺言書の中で明確に指定する方法です。
具体的には、以下のような書き方がなされます。
- 「大阪市の自宅不動産を内縁のパートナーに贈る」
- 「預貯金は孫に渡す」
- 「有価証券は養子縁組をしていない長男に贈る」
特定遺贈の最大の特徴は、渡す財産が明確であることにより、受け取る側が「その財産だけ」を取得できる点です。
そのため、包括遺贈のように借金などの負債を背負う必要は原則としてありません。
このような理由から、福祉団体・NPO法人・病院・学校など、法人が遺贈を受け入れる場合は、ほとんどが特定遺贈として受け入れています。
特定遺贈ならば、あらかじめ指定された不動産や現金のみを対象とするため、管理・処理がしやすく、リスクも低く抑えられるのが特徴です。
遺贈・相続・贈与の違い
財産を他人に譲る手段としてよく挙げられるのが「遺贈・相続・贈与」の3つです。
それぞれ財産を譲るという目的こそ同じですが、タイミング(生前・死後)や方法(契約・遺言・法律)、譲られる対象の範囲、適用される税金などに大きな違いがあります。
それぞれの違いを、以下の表で示しました。
| 遺贈 | 相続 | 贈与 | |
|---|---|---|---|
| 内容 | 遺言書により、故人が生前に指定した内容に従って、死亡後に第三者へ財産を渡す方法 | 民法に基づいて、被相続人(死亡した人)の財産を法定相続人に承継させる方法 | 生前に契約や意思表示によって、自由に財産を渡す方法 |
| 財産を受け取れる方 | 誰でも可能(相続人以外の第三者や法人も可) | 配偶者もしくは一定範囲の親族(配偶者・子・親など) | 誰でも可能(親族でなくても可) |
| 財産の配分 | 遺言書に自由に指定可能。ただし遺留分は保証される | 原則として法定相続分に従うが、遺言書があればその内容が優先される(ただし遺留分は保障) | 自由に決められる(制限なし) |
| 当事者の呼称 | 遺贈者(遺産を贈る方)・受遺者(じゅいしゃ:遺産をもらう方) | 被相続人(亡くなった方)・相続人(遺産を受け取る方) | 贈与者(財産を贈る方)・受贈者(じゅぞうしゃ:財産を受け取る方) |
| 財産を移す時期 | 遺贈者の死亡時 | 被相続人の死亡時 | 随時 |
| 課税される税金 | 相続税 | 相続税 | 贈与税 |
遺贈を行うメリットとデメリット
遺贈は、遺言書によって、相続人以外の人にも財産を引き継がせることができる方法です。
自由度が高い一方で、思わぬトラブルを引き起こす可能性もあります。
ここからは、遺贈を行う際の主なメリットとデメリットについて、具体的に解説します。
遺贈を行うメリット
遺贈を活用することで、法定相続人以外の第三者にも財産を渡すことが可能になります。
たとえば、以下のような方にも財産を遺すことができます。
- 内縁のパートナー(事実上の夫婦関係にあっても、婚姻届を提出していない相手)
- 養子縁組をしていない子ども(再婚相手の連れ子など)
- 孫や兄弟の配偶者
- NPO法人・自治体・病院などの団体
遺贈では、遺贈者自身が「誰に・どの財産を・どれだけ」渡すかを自由に決めることができます。
このため、相続とは異なり、遺贈者の意志を明確に反映した財産の分配が可能です。
また、遺言書の内容は生前には基本的に他人に公開されることはなく、本人の意思で保管できます。
ただし、自筆証書遺言を家庭裁判所で検認する際や、公正証書遺言を開示する段階では相続人に内容が明らかになります。
そのため、生前に家族や親族に知られたくない相手への遺贈も、亡くなるまでは秘密にできることもメリットです。
遺贈を行うデメリット
遺贈には相続人との間にトラブルを生む可能性もあります。
たとえば、内縁関係の相手や特定の孫、友人などに全財産を遺贈した場合、ほかの法定相続人が不満を抱くことがあるためです。
そのような相続人からは、以下のような疑念が向けられてしまう可能性があるでしょう。
- 「本人の真意だったのか?」
- 「誰かに強制されたのではないか?」
- 「遺言書が不正に作られたのではないか?」
こうした疑念が向けられれば、遺言無効を訴える訴訟や、遺留分侵害請求が起こされることもあります。
また、相続人が全員納得していたとしても、遺贈された側(受遺者)が精神的・法律的なプレッシャーを受けるケースもあります。
特に、包括遺贈のように債務(借金など)を含んで引き継いでしまうケースでは、受遺者が損をしてしまうこともあります。
遺贈を行う場合の流れ
遺贈を円滑に実行するためには、あらかじめ適切な準備と手続きが必要です。
遺贈を行う際の基本的な流れは、以下のようになります。
- Step1:遺言書の作成と遺言執行者の指定
- Step2:遺言書の検認
- Step3:財産の引き渡し
- Step4:税金の計算と支払い
ここからは、それぞれのステップを具体的に解説します。
Step1:遺言書作成と遺言執行者の指定
まず、遺贈の内容を記載した遺言書を作成します。
遺言書には主に次の2種類があります。
| 遺言書 | 詳細 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | ・本人が手書きで作成する形式 ・費用はかかりないものの、形式不備や紛失リスクがある |
| 公正証書遺言 | ・公証役場で作成する公文書形式 ・確実性が高く、家庭裁判所の検認も不要 |
遺言の内容を決める前に、所有する財産を一覧化し、おおまかな評価額を把握しておくことが重要です。
加えて、遺言内容を確実に実行してもらうため、「遺言執行者」を指名しておくと安心です。
遺言執行者は、遺言書に基づいて不動産の名義変更や預金の引き出しなどの実務を担う人物のことを指します。
家族や受遺者本人でも選任可能ですが、できるだけ中立性と専門性を備えた司法書士や弁護士などが適任です。
また、相続人以外の人物や団体に財産を遺贈する予定がある場合は、家族への事前説明を検討することで、将来の相続トラブルを未然に防げることもあります。
Step2:遺言書の検認
本人が亡くなった後、遺言執行者や家族は、遺言書の種類に応じて所定の手続きを進めます。
自筆証書遺言を見つけた場合は、勝手に開封せずに家庭裁判所へ「検認の申立て」を行う必要があります。
検認とは、「遺言書が確かに存在していたこと」を裁判所が確認する手続きで、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。
一方、公正証書遺言の場合はこの検認手続きは不要です。
検認にかかる期間は、必要書類の収集も含めて約1〜2か月程度が目安です。
遺言書の検認が完了したら、遺言執行者が受遺者に対して遺言書の写しを提示し、財産の受け取り意思を確認します。
Step3:財産の引き渡し
受遺者が遺贈を受け取る意思を明確にしたら、遺言執行者は実際に財産の引き渡し手続きに進みます。
遺贈の対象が不動産である場合は、名義変更のために「相続登記申請」が必要です。
この手続きは2024年4月より義務化されており、取得を知ってから3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
現金や預貯金、有価証券などの遺贈についても、受け渡しには金融機関や証券会社との手続きが必要です。
Step4:税金の計算と支払い
遺贈によって受け取った財産にも、原則として相続税が課されます。
ただし、遺贈は相続人以外への財産移転となるため、相続人が受け取る相続よりも税負担が重くなるケースがある点に注意が必要です。
また、以下のような税金が発生する可能性があります。
| 税金 | 概要 |
|---|---|
| 相続税 | 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える部分に課税 |
| みなし譲渡所得税 | 遺贈された不動産や有価証券が取得時より値上がりしている場合、課税対象となることがある |
| 登録免許税・不動産取得税 | 不動産の名義変更に伴う税金も発生(相続時より高い率が適用される) |
一般に小規模宅地等の特例は法定相続人に限定されるため、第三者である受遺者には適用されないことが多いです。
しかし、受遺者が法定相続人でもある場合や、一定の要件を満たす場合には、例外的に特例の対象になることがあります。
たとえば、同居していた親族であること、過去に自宅を所有していなかったことなど、細かな条件を満たす必要があります。
そのため、不動産や株式などを遺贈する場合は、事前に税務リスクを想定し、受遺者と情報を共有しておくことが重要です。
遺贈を行う際に注意したいポイント
遺贈は、自分の財産を将来、特定の方や団体に譲りたいと考える際に意義のある手段です。
しかし、法的な手続きや相続税の扱いなど、注意すべき点も以下のように存在します。
- ポイント①:遺贈で取得した不動産にも登記が必要
- ポイント②:税金が高くなるケースがある
- ポイント③:遺贈を放棄される可能性がある
- ポイント④:遺留分を請求されることがある
ここからは、遺贈を行う際に押さえておきたい主な4つのポイントを詳しく解説します。
ポイント①:遺贈で取得した不動産にも登記が必要
2024年4月から相続登記が義務化されたことにより、相続で不動産を取得した場合は、取得を知った日から3年以内に登記手続きを完了させる必要があります。
一方で、遺贈によって取得した不動産にはこの「3年以内」という期限は適用されません。
しかし、登記を行わなければ法的にはその不動産を正式に取得したことにならず、第三者に対して権利を主張できないという問題が生じます。
また、遺贈による登記は通常の相続登記とは異なり、登記申請を受遺者と登記義務者が共同で行う必要があります。
円滑に登記を済ませるためにも、専門家のアドバイスを受けながら、早めの手続きを心がけましょう。
ポイント②:税金が高くなるケースがある
遺贈によって財産を受け取る場合でも、相続税の課税対象となります。
しかし、遺贈には相続よりも不利な税制の扱いがあるため注意が必要です。
たとえば、配偶者や子などの一親等の親族以外の方が遺贈で財産を受け取った場合、相続税額が2割加算されます。
また、相続による死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」まで非課税枠が設けられていますが、遺贈においてはこの非課税枠が適用されません。
したがって、遺贈で得た保険金の全額が相続税の対象です。
こうした税務リスクを避けるには、遺言書の作成時点で税理士に相談し、事前に相続税額のシミュレーションを行うことをおすすめします。
ポイント③:遺贈を放棄される可能性がある
遺贈は故人の想いを遺言書に託して行うものですが、受遺者がその遺贈を辞退(放棄)することも可能です。
たとえば、自身が相続人ではないにもかかわらず遺贈を受けることに抵抗を感じたり、家族間の相続トラブルに巻き込まれることを懸念して辞退するケースもあります。
また、不動産などを遺贈されても、それに伴う管理費や税負担を考慮して放棄する方もいます。
遺贈された不動産には、固定資産税や維持費がかかるため、最終的に受遺者にとって大きな負担となることもあるでしょう。
受遺者にとって負担とならないよう、遺言書の作成前に事前の意思確認を行うか、相続専門家と相談のうえ内容を慎重に練ることが大切です。
ポイント④:遺留分を請求されることがある
遺贈は法定相続分とは異なる配分で、財産を譲ることができます。
しかし、民法では法定相続人が最低限受け取れる相続割合として、「遺留分」が定められています。
法定相続人以外に全財産を譲るという遺言書を作成していたとしても、法定相続人は遺留分を請求する権利を持っているのです。
遺留分の割合は、以下のとおりです。
| 遺留分 | 割合 |
|---|---|
| 配偶者・子が相続人の場合 | 全体の1/2 |
| 親や祖父母など直系尊属のみの場合 | 全体の1/3 |
遺留分を侵害する遺言書を作成したことで紛争に発展し、その後の親族関係にヒビが入ってしまったという事例も少なくありません。
どうしても遺留分を侵害する遺贈を行いたい場合は、事前に専門家に相談して、慎重に遺言書の書き方を工夫するなどの対処を行いましょう。
遺贈の手続きを司法書士に依頼したほうが良いケース
遺贈は、自分の死後に財産を第三者へ渡すための方法であり、必ずしも専門家に依頼しなければならないという決まりはありません。
しかし、次のようなケースでは、専門的な判断や手続きを要する場面が多いため、相続に詳しい司法書士などに相談・依頼することをおすすめします。
- 不動産を遺贈する場合
- 遺留分を侵害する可能性がある場合
- 遺言書の書き方に自信がない場合
以下からは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
不動産を遺贈する場合
遺贈の対象に不動産が含まれている場合は、注意が必要です。
まず、不動産は現金や預貯金と同様に相続税の課税対象になります。
また、相続時の評価額が本人の購入時よりも高くなっていた場合、「みなし譲渡所得税」がかかる可能性があるのです。
さらに、建物や土地を取得すると、その後の管理や修繕、固定資産税の支払いなども発生します。
こうした維持管理の責任を引き受けることは、受遺者にとって大きな負担になる可能性もあります。
どのような遺贈方法であれば、受遺者に負担をかけずに財産を遺せるのかについて、事前に司法書士に相談しておくことで、適切な形での遺贈が可能です。
遺留分を侵害する可能性がある場合
遺留分とは、法定相続人に保障されている、最低限の取り分のことです。
たとえば、子どもや配偶者がいる場合には、たとえ遺言書で「全財産を第三者に渡す」と記載していても、その相続人には遺留分を主張する権利があります。
遺留分を侵害する遺言内容だった場合、法定相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。
この請求によって、受遺者が金銭を支払わなければならなくなることもあり、相続人との間に感情的なしこりを残す結果にもなりかねません。
トラブルを防ぐには、遺留分に配慮した内容を司法書士などの専門家と一緒に設計し、遺言書の記載方法にも細心の注意を払う必要があります。
遺言書の書き方に自信がない場合
遺言書は、一定の法律的な形式を満たしていれば自筆でも有効ですが、実際には以下のような部分に不安を感じる方が多くいます。
- 財産目録の作成方法がわからない
- 契印が不備になりそう
- 必要な記載事項が漏れていないか不安
こうした不備があると、遺言書自体が無効になるリスクや、相続人間での解釈をめぐる争いのもとになることもあります。
公証役場で作成する公正証書遺言であれば形式不備の心配はありませんが、より個別具体的な財産状況に対応したサポートを求める場合には、司法書士への相談がおすすめです。
司法書士に依頼すれば、財産調査から受遺者に配慮した遺贈内容の設計、適切な遺言書の作成、そして本人が亡くなったあとの遺言執行まで、一貫してサポートしてもらえます。
遺贈のご相談は杠(ゆずりは)司法書士法人まで
今回は、遺贈の仕組みや手続きの流れ、司法書士に依頼すべきケースなどについて解説しました。
遺贈とは、亡くなった方が相続人以外の第三者や法人に財産を譲ることを指定する制度です。
たとえば、内縁の配偶者や福祉団体、長年お世話になった知人など、法定相続人以外の方へも財産を託すことが可能になります。
ただし、遺言書の書き方や財産の配分次第では、遺贈を受ける人や相続人に対して思わぬ負担をかけてしまったり、相続トラブルの火種となることもあります。
遺贈に関するトラブルや税務リスクを未然に防ぐためには、相続・遺言に精通した専門家の関与が不可欠です。
杠(ゆずりは)司法書士法人は、相続・遺言の実務に長年携わってきた司法書士が在籍しており、実際の事例に基づいた具体的なサポートが可能です。
「自分の想いを確実に形にしたい」「相続人以外にも感謝の気持ちを遺したい」とお考えの方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
本記事に関する連絡先
TEL: 06-6253-7707
メールでのご相談はこちら >>