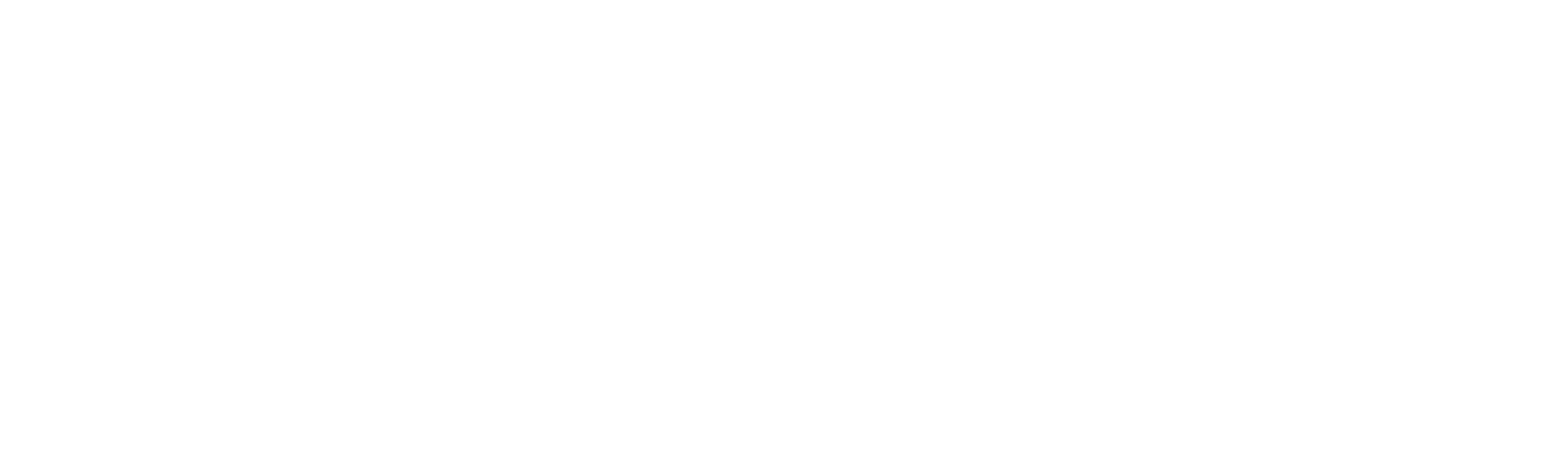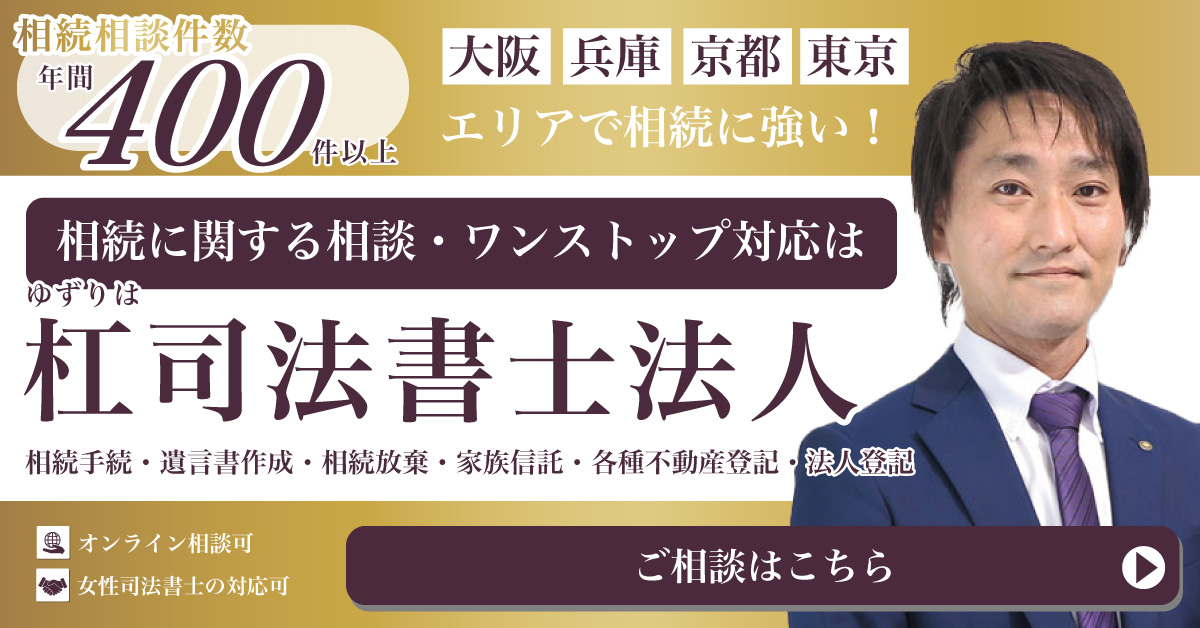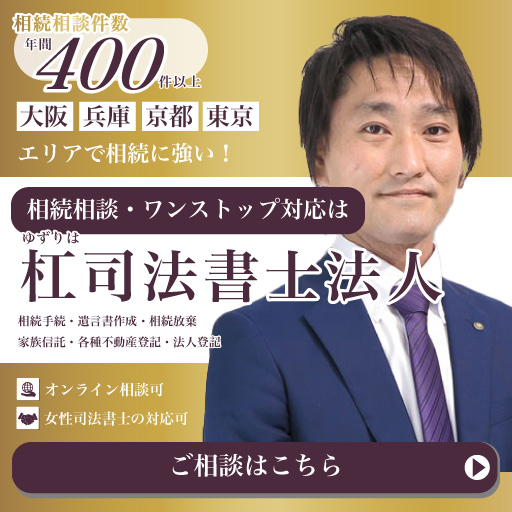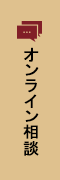相続順位のシミュレーションをしたい方、自分の順位を当てはめて実例を知りたい方
相続
投稿日:2025.02.25
誰がどの割合で遺産を引き継ぐかは、民法で定められています。
相続の際に慌てないように、事前に相続順位をシミュレーションしておくことが重要です。
しかし、家族構成が複雑で、誰に遺産を引き継ぐ権利があるのか判断できない方もいるのではないでしょうか。
この記事では、相続順位について代表的なパターンを示しながらわかりやすく解説します。
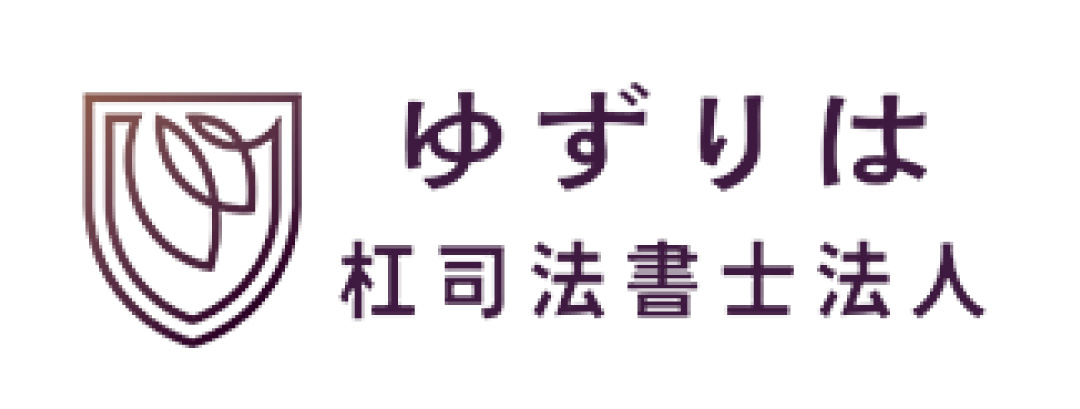
大阪・兵庫・京都・東京を拠点に、相続手続き・遺言書作成・家族信託契約などのサポートから企業法務まで、専門のチームで対応しております。税理士や他業種との連携により、相続問題をワンストップで解決!相続関連の相談件数は年間400件超。
目次
相続順位の決まり方
民法では相続順位(相続人になる順番)や遺産を分ける割合などの相続方法が定められており、これを「法定相続」と呼びます。
まずは、法定相続の基本ルールを解説します。
配偶者は必ず相続人になる
被相続人の配偶者(夫、妻)は必ず法定相続人(民法に基づき相続する権利を持つ人)になります。
離婚すると法定相続人からは外れますが、離婚調停中であれば婚姻関係が継続しているため、法定相続人として扱われます。
配偶者以外の親族は相続順位が決められている
配偶者以外の親族の相続順位は、次のとおりです。
| 相続順位 | 相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子ども(直系卑属) |
| 第2順位 | 親(直系尊属) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(甥姪) |
直系卑属とは、子どもや孫など、自分より後の世代で直通する系統の親族です。
一方で、直系尊属とは、父母や祖父母など、自分より前の世代にあたる直系の親族を指します。
また、相続順位が上位の相続人がいる場合、下位の相続人は法定相続人とはならず、相続権を持ちません。
相続人が亡くなっている場合は代襲相続が発生する
代襲相続とは、法定相続人がすでに亡くなっている場合、代わりにその人の子どもや孫が財産を相続することです。
法定相続人が被相続人の子どもであれば、代襲相続は孫、ひ孫と子孫が続く限り続きます。
しかし、法定相続人が被相続人の兄弟姉妹であるときは、代襲相続は甥と姪の一代までとなる点に注意が必要です。
相続割合も決められている
相続割合は民法で「法定相続分」と呼ばれ、誰がどの割合で遺産を相続できるかが定められています。
法定相続人の組み合わせごとの相続割合は、次のとおりです。
| 相続人 | 配偶者 | 子ども(直系卑属) | 親(直系尊属) | 兄弟姉妹 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子ども | 1/2 | 1/2 | – | – |
| 配偶者+親 | 2/3 | – | 1/3 | – |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | – | – | 1/4 |
同じ相続順位の人が複数人いる場合は、法定相続分を人数で均等に割ります。
具体的な相続割合は、次の相続順位のシミュレーションで解説します。
相続順位のシミュレーション|基本的なパターン5つ
相続人の組み合わせごとに相続順位と相続割合を解説します。
まずは、基本的な5つのパターンから確認しましょう。
パターン1.配偶者と子どもがいる場合
配偶者と子どもが相続する際の相続割合は、配偶者が1/2、子どもが1/2です。
子どもが複数人いれば、人数で割って子ども一人あたりの相続割合を求めます。
たとえば、子どもが3人いる場合は「1/2÷3」なので、子ども一人あたりの相続割合は1/6です。
パターン2.配偶者と親がいる場合
配偶者と親が相続する際の相続割合は、配偶者が2/3、親が1/3です。
両親ともに存命であれば二人で分けることになるため、相続割合はそれぞれ1/6ずつです。
両親が離婚している場合も、父母の両者に相続権が認められます。
被相続人の父母がすでに亡くなっており、祖父母が存命であれば、直系尊属の祖父母が法定相続人となります。
相続割合は父母の場合と変わらず1/3です。
パターン3.配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者と被相続人の兄弟姉妹がいるときの相続割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4です。
兄弟姉妹が複数人いれば、人数で割って一人あたりの相続割合を算出します。
たとえば、被相続人に兄と妹が一人ずついる場合は「1/4÷2」となり、一人あたりの相続割合は1/8になります。
パターン4.相続人が配偶者のみの場合
被相続人に子どもや親、兄弟姉妹が存在せず、相続人が配偶者のみであれば、配偶者が遺産の全てを相続します。
パターン5.配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は、相続順位に従って相続人が決まります。
被相続人に子どもがいるならば、子どもが法定相続人です。
子どもがおらず親がいれば親が法定相続人になり、子どもと親がおらず兄弟姉妹が存在すれば、兄弟姉妹が法定相続人として扱われます。
それぞれのケースで法定相続人が遺産を全て引き継ぎ、同じ順位の相続人が複数いる場合は人数で割ることになります。
相続順位のシミュレーション|複雑なパターン7つ
以下からは、少し複雑な相続のパターンについて解説します。
特殊な条件がある場合の相続順位についても解説するので、該当する際は参考にしてください。
パターン1.子どもは亡くなっているが孫がいる場合
被相続人の子どもが亡くなっているが、その子ども(被相続人の孫)がいる場合は代襲相続の対象となり、孫が法定相続人になります。
代襲相続が適用された場合の相続割合は、本来の相続人の取り分がそのまま引き継がれます。
たとえば、配偶者と孫が遺産を引き継ぐ場合の相続割合は、配偶者が1/2、孫が1/2です。
配偶者がすでに亡くなっていれば、孫が全ての遺産を引き継ぎます。
また、子どもと孫が亡くなり、ひ孫がいる場合では、代襲相続は子孫がいる限り続くため、ひ孫が法定相続人となります。
パターン2.兄弟姉妹は亡くなっているが甥・姪がいる場合
被相続人の兄弟姉妹は亡くなっているが、その子ども(被相続人の甥、姪)がいるケースでは、代襲相続の対象となり甥や姪が法定相続人として扱われます。
配偶者と甥または姪が遺産を引き継ぐ場合の相続割合は、配偶者が3/4 、甥または姪が1/4です。
配偶者がすでに亡くなっていると、甥または姪が全ての遺産を引き継ぐことになります。
ただし、兄弟姉妹で適用される代襲相続は一代限りです。
被相続人の兄弟姉妹と甥や姪が亡くなっていても、甥や姪の子どもは法定相続人に認められないことに注意しましょう。
パターン3.胎児がいる場合
被相続人の配偶者が妊娠している場合は、胎児も被相続人の子どもとして認められるため、法定相続人になれます。
ただし、死産であった場合は相続権が失われることに注意が必要です。
たとえば、被相続人に妊娠中の妻と両親がいるケースでは、妻と胎児が遺産を引き継ぎます。
しかし、子どもが死産の場合は相続権が両親に移り、妻と両親が法定相続人となります。
したがって万が一のことを考慮し、遺産分割協議は出産後に行うほうが良いでしょう。
パターン4.被相続人が再婚していた場合
被相続人が離婚し、再婚していたケースでは、再婚相手の配偶者が法定相続人となります。
したがって、被相続人と再婚相手との間に生まれた子どもも法定相続人です。
再婚相手に連れ子がいた場合、その子どもは被相続人と養子縁組をしていれば、法定相続人として認められます。
しかし、養子縁組していなければ、連れ子には相続権がないことに注意が必要です。
また、離婚した元配偶者に遺産を相続する権利はありません。
ただし、被相続人と離婚した元配偶者の間に生まれた子どもは、被相続人と血縁関係があるため、法定相続人として認められます。
パターン5.内縁の妻と子どもがいる場合
被相続人の内縁の妻は、法定相続人になれません。
法定相続人になれる配偶者は、婚姻届を提出して法的に認められた夫婦に限られるためです。
ただし、内縁の妻との間に生まれた子どもは、認知されている場合に限り、遺産を引き継ぐ権利が認められます。
被相続人に妻と実子、さらに内縁の妻と子どもがいるケースも同様に考えてかまいません。
法律婚をしている妻と実子は、もちろん法定相続人です。
内縁の妻は相続人になれないものの、内縁の妻の子どもは、被相続人に認知されていれば法定相続人として認められます。
この場合、内縁の妻の子どもは実子と同じ相続割合で遺産を引き継ぐことが可能です。
なお、詳しくは後ほど解説しますが、法定相続人が一人もいないケースでは、内縁の妻も「特別縁故者」として遺産を取得できる可能性があります。
パターン6.養子がいる場合
被相続人に養子がいる場合、養子は被相続人の子どもとみなされて法定相続人になります。
養子以外に実子がいても、両者の相続順位は同列で、相続割合も同じです。
たとえば、被相続人に配偶者と実子一人、養子一人がいる場合、配偶者の相続割合は1/2です。
遺産の残り1/2が実子と養子の取り分になりますが、同じ割合で分けるため、実子と養子の相続割合は1/4ずつとなります。
また、被相続人が実子を養子に出していた場合も、その子どもは法定相続人として認められます。
養子に出しても、被相続人と子どもは血縁関係にあるためです。
ただし、実親との関係を解消し、新しい親と親子関係を結ぶ「特別養子縁組」をしている場合、子どもは実親の法定相続人にはなれません。
パターン7.相続人が誰もいない場合
法定相続人にあたる人がいない場合、まずは「特別縁故者」が遺産を引き継ぐ候補に上がります。
特別縁故者とは、被相続人と特別に親しい関係があった人を指し、具体的には次のような人が該当します。
- 内縁の配偶者など、被相続人と生計を共にしていた人
- 被相続人の療養や看護をしていた人
- そのほか被相続人と特別な関係にあった人
上記に当てはまれば、被相続人と血縁関係や婚姻関係にない人でも、遺産を引き継げる可能性があります。
特別縁故者が遺産を取得するには、家庭裁判所への申し立てが必要です。
被相続人に特別縁故者がいない場合、被相続人の遺産は国庫に帰属します。
相続順位に関する注意点
相続順位については、これまで解説してきた内容以外にも押さえておくべきポイントがあります。
相続手続きをスムーズに進めるために、理解しておきましょう。
遺言があればその内容に従う
被相続人の遺言が残されていれば、法定相続よりも遺言の内容が優先されます。
これは、民法で被相続人は自分の財産を自由に扱えると定められているためです。
法定相続とは異なる順位や割合で遺産を引き継ぐように記載されていても、遺言の内容に従って相続が行われます。
遺言がない場合は遺産分割協議を行い、相続人の協議で遺産の分け方を決定します。
遺留分に注意する
遺留分とは、相続人に認められた最低限の相続財産を得る権利のことです。
たとえば、遺言に「子どもAに全ての財産を相続する」と記載されていた場合、配偶者やほかの子どもは遺産を相続できなくなります。
しかし、相続人には遺留分が認められているため、配偶者やほかの子どもは遺留分侵害額請求を行うことで、最低限の財産を相続できるようになります。
全相続財産に対する遺留分の割合は、次のとおりです。
| 相続人 | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 直系尊属のみ(父母、祖父母など) | 1/3 |
| 直系尊属のみ(父母、祖父母など)場合以外 | 1/2 |
被相続人に配偶者と子どもA、Bがおり、遺言にAへ全ての財産を相続すると記載されていた場合でも、遺産の1/2は遺留分侵害額請求の対象です。
対象である遺産の1/2を法定相続割合で分けるため、配偶者は1/4、Bは1/8を取得することが可能です。
ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないことに注意しましょう。
法定相続人でも相続できないケースがある
法定相続人でも、次に該当する人には遺産を相続する権利がありません。
| 遺産を相続する権利がない人 | 概要 |
|---|---|
| 相続欠格 | 詐欺や脅迫により遺言を妨害したり、被相続人を殺害したりした相続人が、遺産を相続する権利を失う制度 |
| 相続廃除 | 被相続人に虐待や侮辱などを行った相続人に対し、被相続人が申し立てを行うことで相続権を失わせる制度 |
| 相続放棄 | 被相続人の遺産を一切引き継がず、相続人が相続権を手放すこと |
上記に該当する人以外に、同順位に相続人がいなければ、相続権は次の順位に移ります。
ただし、代襲相続には注意が必要です。
相続欠格や相続廃除にあたる相続人に子どもや孫がいれば、代襲相続が適用され、その子どもや孫が遺産を引き継ぎます。
一方で、相続放棄をした相続人は、はじめから相続権がなかったものとみなされるため、子どもや孫がいても代襲相続は適用されません。
相続人が行方不明の場合は手続きが必要である
相続人が行方不明である場合は、その人を探し出さなければなりません。
遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければ無効となるためです。
行方不明の相続人を探し出すには、市町村役場でその人の戸籍の附票を取得しましょう。
戸籍の附票には住所の履歴が記載されているので、最新の住所が分かります。
それでも相続人を探し出せなければ、遺産分割協議を進めるための手続きが必要です。
行方不明の期間が7年未満であれば、不在者財産管理人を選任し、不在の相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらいます。
行方不明の期間が7年以上であれば、法律上亡くなったものとして扱われます。
したがって、「失跡宣告」を申し立てれば、行方不明の相続人が不在のまま遺産分割協議を行うことが可能です。
相続順位のシミュレーションは専門家に依頼しよう
スムーズな相続手続きのために、相続順位をシミュレーションして事前に把握しておくことは重要です。
しかし、家族構成は複雑であり、本記事で紹介したパターンに該当しないケースもあるでしょう。
相続順位について詳しくシミュレーションするなら、専門家に依頼するのがおすすめです。
相続に関する疑問や困りごとは、杠(ゆずりは)司法書士法人にお任せください。
杠(ゆずりは)司法書士法人は相続のプロフェッショナルとして、最適な解決策をご提案します。
相続順位のシミュレーションもお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。
本記事に関する連絡先
TEL: 06-6253-7707
メールでのご相談はこちら >>