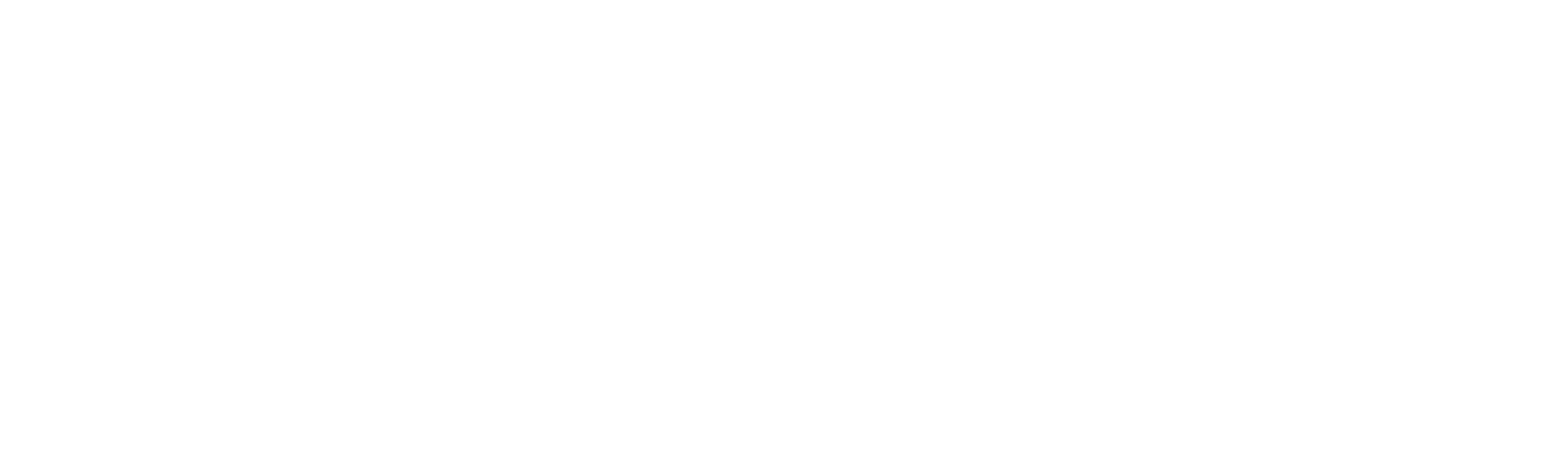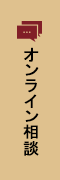話題のドラマ「俺の家の話」を司法書士が解説!(第3話:寿三郎さんの終活)
遺言
|更新日:2022.10.15
投稿日:2021.02.12
目次
宮藤官九郎さん脚本のTBS金曜ドラマ「俺の家の話」。
今回は 第3話 のお話です。
プロレス界のレジェンド、長州さん・蝶野さん・武藤さんの3人が一緒に登場!衝撃の場面に遭遇したさくらさんの表情も、なかなかのものでした。
引退したはずの寿一さんも、怖~い先輩方の提案を受け入れ、スーパー世阿弥マシーンとして再スタートを切ることに。
能で鍛えた体幹を生かした独特の戦い方で、さらなる進化を遂げていたように思います。
今回も、じゅじゅこと観山宗家・寿三郎さんの「遺言状」のエピソードがありましたね。
婚約者?であるさくらさんへ、大量の遺言を渡していることが明らかに。
全財産を婚約者のさくらさんへ渡すといった内容のようですが、実際、こんなに何通も遺言状が出てきたら、どのような取り扱いとなるのでしょうか。
第3話:寿三郎さんの終活 (遺言書・エンディングノートについて)
基本的には、内容の異なる遺言書が複数出てきた場合は、最も新しい日付のものが有効という考え方になります。
全財産を寿一さんに相続させる内容の遺言と、さくらさんに遺贈することにした内容の遺言と、両方が出てきた場合には、どちらか一方の新しいほうが有効になるということです。
ただ、少し気になったのは、画面に映ったじゅじゅの遺言状には、書いた日付の記載がなかったような?
別のページがあるのかもしれませんが、もしかしたら、日付がないので、正式に有効な遺言ではないぞ!という争いになってしまうかもしれませんね。
寿三郎さんのように、自分で遺言書を書きたい場合には、ルールが決められています。
遺言として認められる書式って?
- 全文(自筆する※)
- 日付(自筆する)
- 氏名(自筆する)
- 押印
※①については、最近の法改正で、遺言の対象にする財産のリストの部分(財産目録)の部分は自筆でなくてもいいよ、という例外が設けられました。
今回のように複数の遺言書がある場合、正しい形式、かつ最新の日付のものが優先されるということになりますから、日付とか印鑑とか、細かい話のように思えて、意外と重要だったりします。
もうひとつ気になるのは、寿三郎さんには認知症の診断が出ていたのでは?という点かもしれません。
遺言を書いた時に、自分でものごとをきちんと判断できていたのか。
この「意思能力」の問題は、遺言書でトラブルになりやすい部分でもあるのです。
認知症になったら無効になるの?
これについては、認知症の診断=自動的に遺言は無効、というようなシンプルな判断ではありません。
- 認知症の程度
- 遺言を作ろうとした動機や経緯
- 遺言の内容
- 内容に対する本人の理解力
などによって、総合的に判断されることになります。
寿三郎さんの場合、認知症の進行の段階についての診断の詳細は分かりません。
ですが、自分である程度の判断ができること、完全に忘れてしまっているわけでないこと、本当はさくらさんがどういう立場なのか知っていることなど、いろいろなシーンから推測されますね。
とはいいながら、もしも寿三郎さんを診ていたお医者さんが「本人では判断できる状態にない」という診断を下していたりすると、医療の専門家からの客観的な意見として重視されて、やはり遺言の効力が問題になってしまう可能性もありえます。

エンディングノートとの関係は?
転倒での入院から、退院して復活?を遂げた寿三郎さんの手には、これからのやりたいことがたくさん書かれた「エンディングノート」がありました。
プロレス観戦がしたいとか、家族旅行(消されてましたが)がしたいとか・・・。
(どちらかというと、死ぬまでにしたい○○個のこと、といった「バケットリスト」に近いものでしたが)
エンディングノートのほうは、自分が迎える最期の時間に向けてどのように考えているか、どのように過ごしたいかなどをあらためてまとめてみるもの。
この種のノートは、1990年代~2000年代あたりにかけて、だんだんと注目を集めるようになり、現在でも人気は続いています。
正式な法律文書として書くわけではないので、遺言書のように、亡くなった後の実際の手続きにまで使えるようなものではありません。
ただ、遺言書のほうはどうしても味気なく、無機的なものになってしまいがちです。

遺言書だけではわからない生の情報、自分の願いや気持ちなどを整理するものとして一定の機能を果たしますし、登場から20~30年ほど経ってもすたれていないのは、それだけ手に取る人、支持する人がいるからなのかもしれませんね。
まとめ
第3話になり、登場人物同士の人間関係まで、かなり見えてきました。なんだかんだで協力的な家族と、単純に悪い人ではないように見える婚約者。
最初に思ったより「争族」ではないのかもしれません。それでも、今後どんな展開になるのか、まだまだ目は離せませんね。
これからも、老後の暮らしや、それを支えるご家族へのサポートを行っている専門家として、どんなことに注意すべき なのか、どんな制度が活用できそうなのか など、気づいたポイントをこれからもお届けしていきたいと思います。
第4話も、ひきつづき要注目です!
★ 引き続き 第4話 のコラムを読みたい方は こちら
【 第4話「 芸能界の親子関係とは?! 」 】
★ 老後の心配事を少なくしたい!など、
より詳しく 知りたい方へオンラインセミナーを開催しております。
【 セミナー案内ページ 】
本記事に関する連絡先
TEL: 06-6253-7707
メールでのご相談はこちら >>