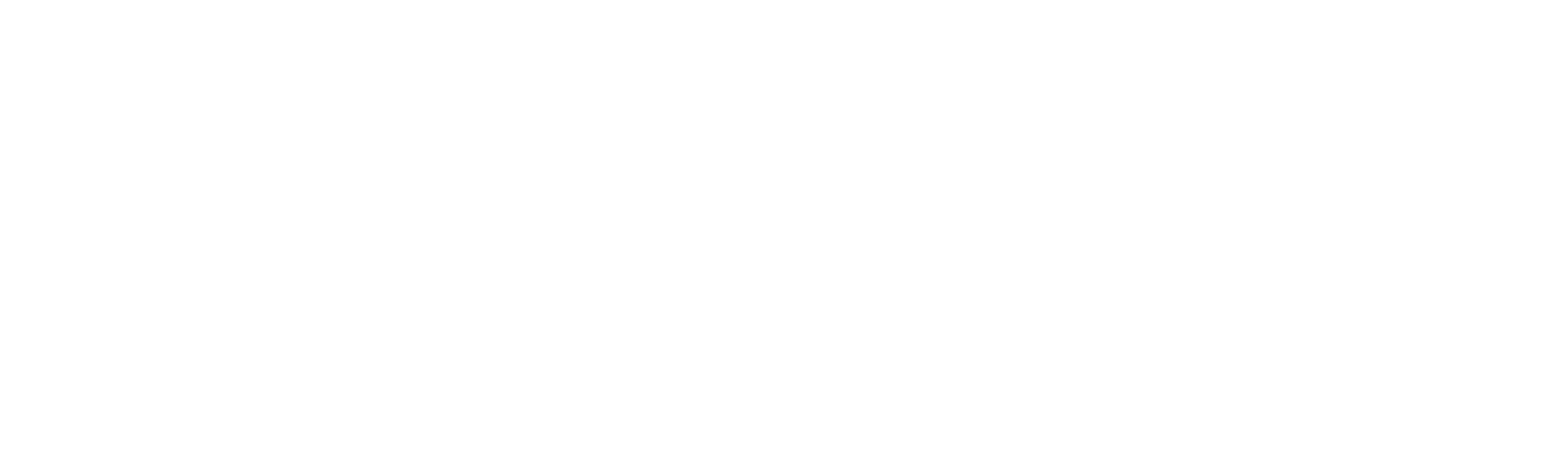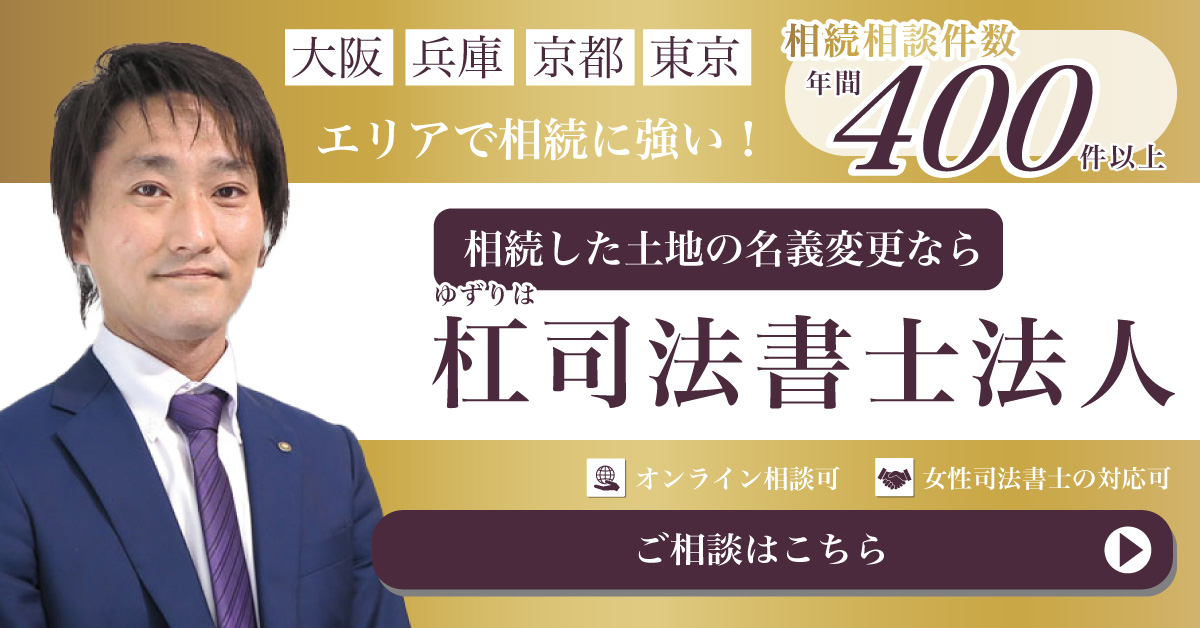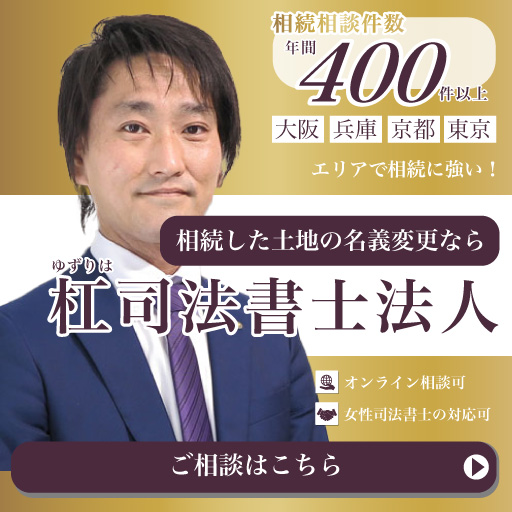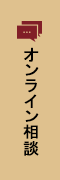土地を相続したらやるべきことは?土地の分け方から相続税の計算方法まで基本を解説
相続
投稿日:2025.03.19

土地の相続は、人生で何度も経験するものではありません。
そのため、いざ土地を相続することになっても、何からすべきかわからない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、土地を相続する際に押さえておきたい基本的なポイントをわかりやすく解説します。
また、トラブルになりにくい土地の分割方法や節税に活用できる制度も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
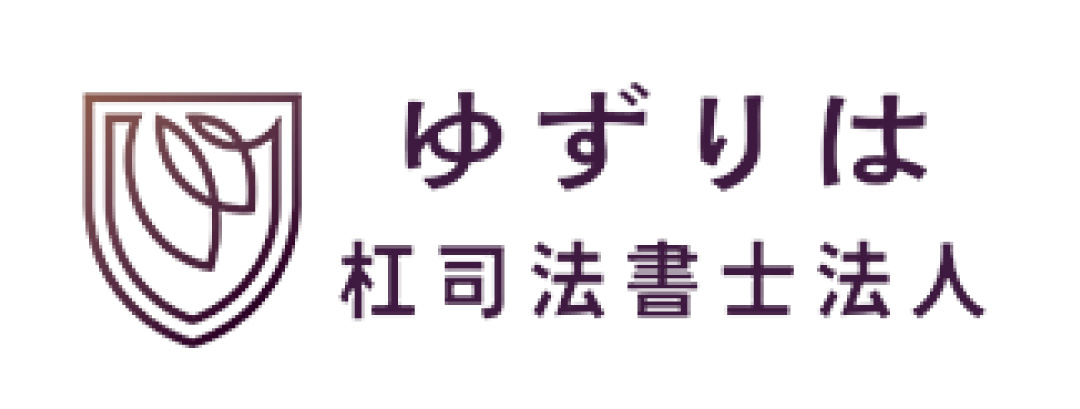
大阪・兵庫・京都・東京を拠点に、相続手続き・遺言書作成・家族信託契約などのサポートから企業法務まで、専門のチームで対応しております。税理士や他業種との連携により、相続問題をワンストップで解決!相続関連の相談件数は年間400件超。
目次
土地の相続で必要な手続きの流れ
相続した財産に土地が含まれていたら、必要なステップを踏んで手続きを済ませなければなりません。
以下では、5つの手続きについて解説します。
STEP1:相続不動産を確認する
まずは、相続する土地の詳細を把握するために、固定資産税課税明細書や名寄帳を確認します。
固定資産税課税明細書は通常、年1回送付されるものですが、見つからない場合は市区町村の役所で取得可能です。
名寄帳も市区町村の役所にて取得できます。
ただし、いずれも確認できるのは、役所が管轄する地域内の土地に限られる点に注意してください。
STEP2:法定相続人を確定させる
遺言書があれば、遺言で指定されている人が土地を相続します。
しかし、遺言書がない場合は法定相続人で遺産分割協議を行わなければなりません。
法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利を持つ、民法で定められた人のことです。
主に被相続人の配偶者・子ども・親・兄弟姉妹が該当します。
法定相続人を調べるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地がある市区町村の役所で取得しましょう。
STEP3:遺産分割協議を行う
遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、土地を引き継ぐ人を決定します。
合意した内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名し、実印を押します。
なお、土地だけでなく、建物や預貯金、株式などの財産も遺産分割協議の対象になるので、協議がスムーズに進まないこともあるかもしれません。
協議が難航する場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けたり、裁判所に遺産分割調停を申し立てたりすることを検討しましょう。
STEP4:相続登記申請する
土地の相続人が決まれば、土地の相続登記を行います。
相続登記とは、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
現在は、相続が発生してから3年以内に相続登記を行うことが義務付けられており、違反すると過料が科される場合があります。
登記に必要な書類を早めに用意し、相続する土地の所在地を管轄する法務局に申請しましょう。
STEP5:相続税を申告する
土地を相続すると相続税を申告し、納付しなければならない場合があります。
相続税の申告と納付の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
この期限を過ぎて申告すると無申告加算税が、納付が遅れると延滞税が課税されます。
ただし、やむを得ない事情で納付が遅れる場合は延滞税が免除されたり、延納(相続税の分割払い)が認められたりするケースもあります。
相続した土地を分ける4つの方法
相続した土地の分け方には、次の4つの方法があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
遺産の分け方によっては後々トラブルに発展する可能性が高まるため、どの方法を選択するかは重要なポイントです。
それぞれの土地の分け方について解説します。
現物分割|土地をそのまま分ける
現物分割とは、土地をそのままの形で引き継ぐ方法です。
具体的には、二つの土地がある場合に一つを長男が、もう一つを次男が相続するといったケースが該当します。
また、一つの土地を分筆(複数に分割)して、それぞれの土地を各相続人が単独で引き継ぐ方法もあります。
現物分割は、土地を相続する方法として最もシンプルな分け方です。
一方で、分筆に必要な測量に手間がかかる点、土地の形状によっては平等に分けることが困難な点がデメリットに挙げられます。
代償分割|土地を相続した人がほかの相続人に金銭を支払う
代償分割とは、土地を引き継いだ人がほかの相続人に対して、相続分を超える金額を金銭で支払う方法です。
たとえば、2,000万円の土地を引き継いだ長男が、次男に1,000万円を支払うケースが代償分割に当たります。
代償分割は、土地を平等に分けることが難しく、現物分割ができない場合の選択肢の一つになるでしょう。
一方で、土地の評価額が高い場合、支払う金銭の負担が大きくなる点がデメリットといえます。
換価分割|土地を現金化して分ける
換価分割とは、土地を売却した代金を相続人で分ける方法です。
たとえば、相続財産である土地を売却して得た代金2,000万円を、長男と次男が1,000万円ずつ受け取るケースが該当します。
このように、換価分割は目に見えて分かりやすい数字で分割するため、公平性が高く不満が生じにくいことがメリットです。
しかし、土地によっては売却に時間がかかったり、土地を手放さなければならなかったりする点がデメリットです。
共有分割|土地を複数人で共有する
共有分割とは、土地を複数の相続人が共有した状態で引き継ぐ方法です。
たとえば、一つの土地を長男が2分の1、次男が2分の1の持分で引き継ぐケースが共有分割に当たります。
共有分割を行うと土地は相続人の共有名義になり、土地の売買には相続人全員の同意が必要になるため、土地の活用が難しくなるでしょう。
加えて、共有している相続人が亡くなるとさらに相続が発生し、持分が複雑化する可能性があります。
トラブルの発生を防ぐために、相続した土地はできる限り共有分割以外の方法で分けることをおすすめします。
土地の相続登記に必要な書類と費用
相続登記は2024年の4月から義務化されており、相続した土地の登記をせずに放置しているとペナルティが科される可能性があります。
以下では、抜け漏れなく手続きを進めまるための相続登記のポイントを解説します。
相続登記の必要書類
相続登記の手続きには、次の3つの書類が必ず必要です。
- 相続登記申請書
- 登記事項証明書
- 固定資産税評価証明書
加えて、遺言書がある場合は次の書類を用意します。
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
- 遺言執行者の選任審判謄本(遺言書で遺言執行者が選任されている場合以外)
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 土地を相続する人の戸籍謄本
- 土地を相続する人の住民票
遺言書がない場合は次の書類を用意してください。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 土地を相続する人の住民票
相続人の人数によってはかなりの数の書類が必要になるため、早めに準備を進めましょう。
相続登記の費用
相続登記には、登録免許税と必要書類の取得費用がかかります。
登録免許税とは、不動産の名義変更を行う際にかかる税金です。
土地の相続登記にかかる登録免許税は、土地の固定資産税評価額の0.4%と定められています。
また、相続登記に必要な書類の取得にかかる費用は次のとおりです。
| 必要書類 | 取得費用 |
|---|---|
| 登記事項証明書 | 600円 |
| 固定資産税評価額 | 300円 |
| 戸籍謄本 | 450円 |
| 印鑑証明書 | 300円 |
| 住民票 | 300円 |
| 住民票の除票、戸籍の附票 | 200〜400円 |
上記は1通あたりの取得費用であるため、相続人が多いほど費用も高額になります。
費用を抑えたい場合は、コンビニエンスストアの交付サービスやオンライン請求を活用してみましょう。
土地を相続する際の評価方法と相続税の概要
土地の場合も、相続が発生すると相続税が課税される可能性があります。
土地の評価方法と相続税の概要を見ていきましょう。
相続税の計算方法
まず、土地を含む相続財産の総額を調べ、基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出できます。
たとえば、法定相続人が3人であれば「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」が基礎控除額です。
この場合、相続財産の総額が4,800万円以下なら相続税は課税されません。
次に、課税遺産総額を法定相続分で分け、それぞれに相続税率を掛けて相続人ごとに税額を求めます。
配偶者が相続人に含まれる場合の法定相続分は、次のとおりです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者+子ども | 配偶者: 2分の1 子ども: 2分の1 |
| 配偶者+被相続人の父母、祖父母 | 配偶者: 3分の2 父母、祖父母: 3分の1 |
| 配偶者+被相続人の兄弟姉妹 | 配偶者: 4分の3 兄弟姉妹: 4分の1 |
たとえば課税遺産総額が8,000万円、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者は4,000万円、子どもはそれぞれ2,000万円ずつ取得することになります。
相続税率は次のように、法定相続分に応じた取得金額により異なります。
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
先ほどのケースであれば、配偶者の税額は「4,000万円×20%−200万円=600万円」、2人の子どもそれぞれの税額は「2,000万円×15%−50万円=250万円」です。
最終的にこれらの税額を合計し、実際に引き継いだ財産の割合で分け、各相続人が相続税を負担します。
相続した土地の評価額の調べ方|相続税路線価を使う
土地の相続税を計算するためには、引き継ぐ土地の評価額を把握する必要があります。
相続した土地の評価額は、基本的に相続税路線価を用いて計算します。
土地の評価額の計算方法は「1㎡あたりの路線価×補正率×土地の面積(㎡)」です。
補正率とは、土地の形状や奥行きなどに問題があり、価値が低くなる土地の評価額を調整するために使用する数値です。
なお、路線価が定められていない土地の場合は、固定資産税評価額に所定の倍率を掛けて評価額を計算します。
相続税を減額できる制度|小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例」という制度を活用すると、土地にかかる相続税を最大80%まで減額できる可能性があります。
小規模宅地等の特例が適用できる土地の種類と上限面積、減額割合は次のとおりです。
| 土地の種類 | 概要 | 上限面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地 | 被相続人の自宅の敷地 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地 | 被相続人の店舗や事務所の敷地 | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地 | 被相続人が経営していた同族会社の事業所がある敷地 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地 | 被相続人が貸していた敷地 | 200㎡ | 50% |
このように、小規模宅地等の特例を用いると大きな節税効果が得られます。
制度の適用には上記以外にも細かな条件があるため、専門家に確認することをおすすめします。
土地の相続は専門家に依頼できる
土地の相続手続きや相続税の計算、相続トラブルの解決は専門家に依頼できます。
ただし、専門家ごとに得意分野が異なるため、依頼内容に応じて適切な相談先を選ぶことが大切です。
税理士|相続税をスムーズに申告できる
相続税の計算や申告で悩んだときは、税理士への相談をおすすめします。
小規模宅地等の特例などの制度の利用には、専門的な知識が必要です。
また、相続税の計算が間違っていたり申告が漏れていたりすると、過少申告加算税や延滞税が課される可能性もあります。
相続税について見識が深い税理士に依頼すれば、煩雑な相続税の計算や申告もスムーズに進められるでしょう。
司法書士|相続登記を安心して任せられる
相続登記に不安があるときは、司法書士に相談しましょう。
相続登記には数多くの書類が必要であり、その収集や内容の確認にはかなりの時間と労力を要します。
また、相続する土地の名義が過去の所有者のまま変更されていなければ、相続登記の手続きも複雑になります。
登記の専門家である司法書士に依頼すれば、相続登記にかかる手間を大幅に軽減できるでしょう。
弁護士|相続トラブルも解決できる
相続人同士でトラブルが発生しそうな場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
相続では、土地の分割方法や売却などについて相続人同士で意見の対立が起こる可能性があります。
当人だけで話し合いを進めて解決させることは簡単ではありません。
弁護士に依頼すれば、専門的な視点から相続トラブルの解決が図られ、遺産分割協議が円滑に進むでしょう。
土地の相続手続きに不安があれば専門家に依頼しよう
相続財産に土地が含まれていると、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、土地の分割方法や相続人を決定する必要があります。
その後も、相続登記を申請したり相続税を申告・納付したりと、多くの手続きが必要です。
相続登記が複雑になる場合や、相続登記にかける時間や労力を軽減したいときは司法書士に依頼しましょう。
杠(ゆずりは)司法書士法人では、相続登記をはじめとした相続に関するさまざまなサポートを行っています。
土地の相続手続きに不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事に関する連絡先
TEL: 06-6253-7707
メールでのご相談はこちら >>