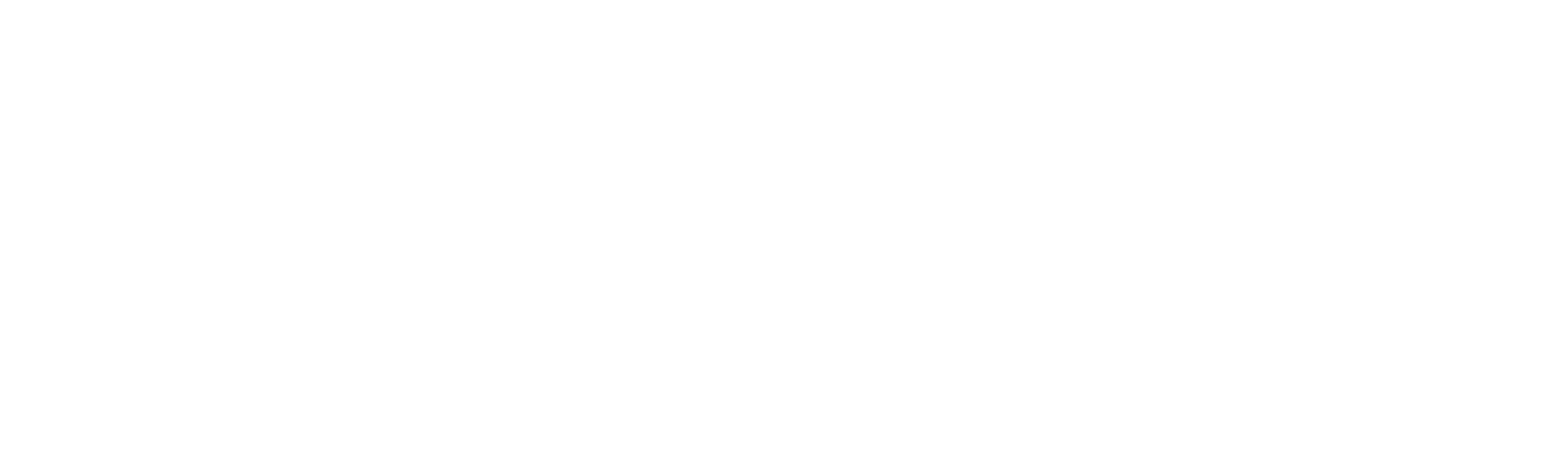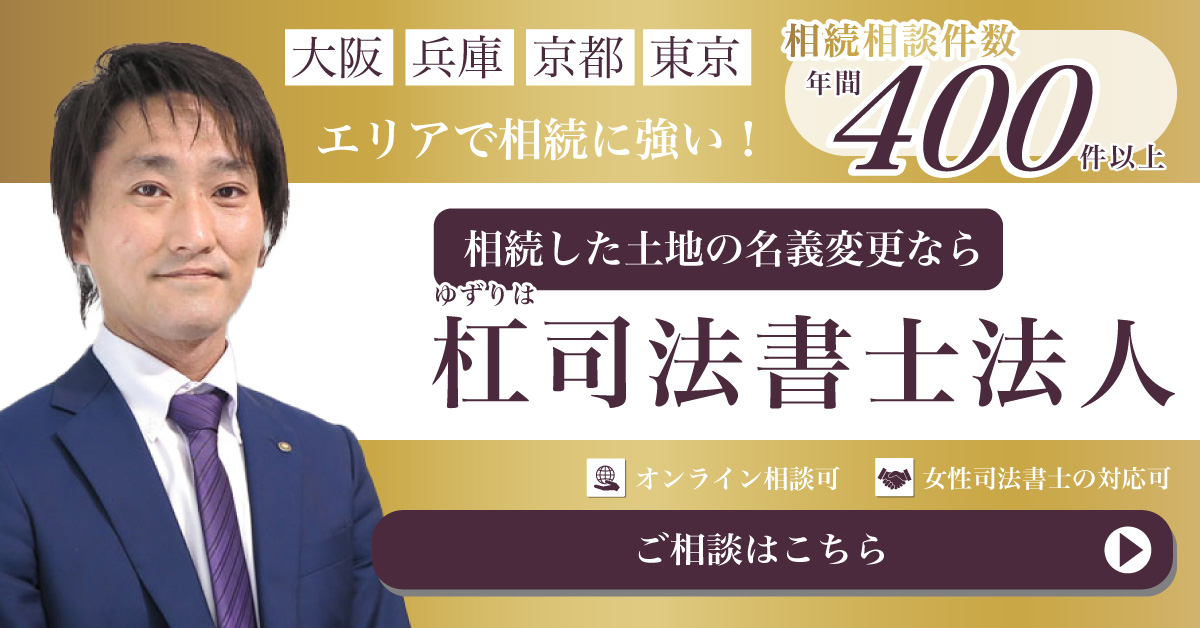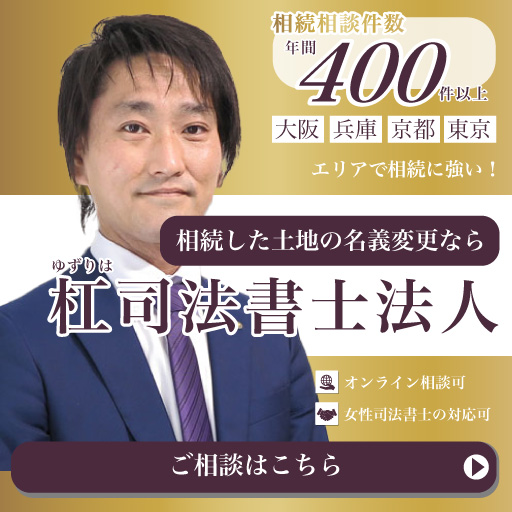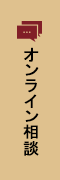相続した土地を現金で分けるには?分割方法や注意すべきポイントも紹介
不動産
投稿日:2025.03.19

「土地を相続したものの、現金化するにはどうしたらいいんだろう」と、相続した不動産の現金化について、どうしたら良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
相続不動産を現金化するには、換価分割と代償分割の2つの方法があります。
この記事では、具体的な分割方法や注意すべきポイントについて紹介します。相続した不動産の現金化を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
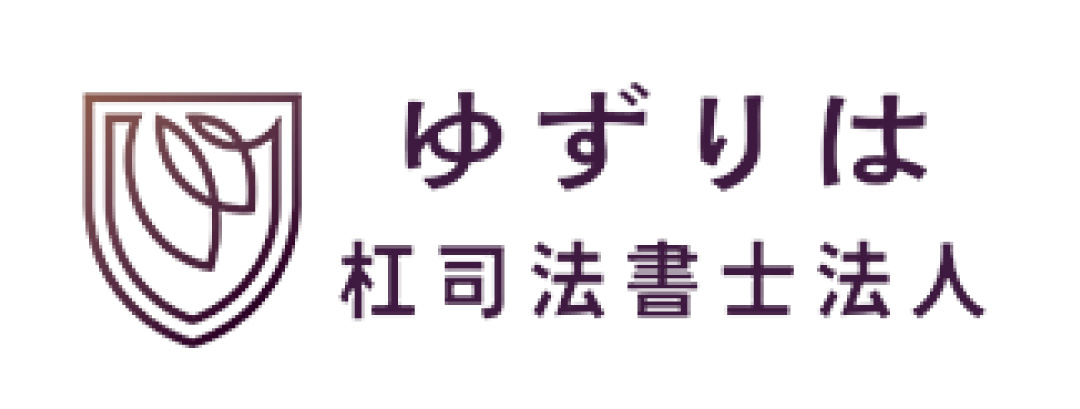
大阪・兵庫・京都・東京を拠点に、相続手続き・遺言書作成・家族信託契約などのサポートから企業法務まで、専門のチームで対応しております。税理士や他業種との連携により、相続問題をワンストップで解決!相続関連の相談件数は年間400件超。
目次
土地の相続はトラブルになりやすい?
土地の相続は、現金の相続に比べるとトラブルの元になりやすいです。
その理由として、以下の2つが挙げられます。
- 相続財産のなかで土地が最もトラブルの割合が大きい
- 不動産は分配方法をめぐって争いが生じやすい
それぞれの理由について解説します。
相続財産のなかで土地が最もトラブルの割合が大きい
国税庁による「相続税の申告事績の概要」によると、相続財産に占める不動産の割合は40%を超えており、預貯金や有価証券よりも大きな金額となっています。
不動産や土地は相続したもののなかでも高額な資産であることが多く、相続の際にトラブルの火種となりやすい特徴です。
金額の大きさとトラブルの割合は比例関係にあると想定されることから、相続を考えるときは不動産や土地の相続について、よく考える必要があります。
不動産は分配方法をめぐって争いが生じやすい
不動産は現金と違い、分配がしにくいことから揉め事に発展するケースが多く見られます。
不動産の評価額と分割方法が揉め事の原因です。
たとえ仲の良い兄弟でも不動産の相続が絡むと、不仲になってしまうケースも見られます。
一度不仲になってしまうと、関係の修復にも時間がかかります。
余計な揉め事を起こさないためにも、しっかりと対策をすることが大切です。
解決方法として現金化が有効
相続した後に不動産を活用しない場合は、売却して現金化しすることで余計な揉め事を回避できる可能性が高まります。
不動産を相続しても活用の道がないことがわかっていれば、現金化してしまうほうが相続人全員の同意が得やすく、揉め事に発展しにくいです。
相続した土地の分割方法
相続した土地は4つの分割方法が用意されています。
- 換価分割
- 代償分割
- 現物分割
- 共有分割
このうち、現金での分割に対応できるのは換価分割と代償分割です。
それぞれの分割方法について、詳細を説明します。
換価分割
換価分割は、相続する土地などを売却して現金化したうえで、それぞれの相続人へ引き継ぐ分割方法です。
換価分割は分割が難しい不動産や動産などの財産を現金にすることで、公平性を維持できるメリットがあります。
一方、売却から現金化までに一定の時間がかかるのがデメリットです。
不動産の場合、売却までに数か月かかる場合もあり、長いと1年以上かかってしまうケースも珍しくありません。
売却先を探している間に相場価格が下がってしまうケースもあるため、注意が必要です。
代償分割
特定の相続人が財産を引き継ぐ代わりに、その相続人がほかの相続人へ現金を支払う分割方法です。
代償分割のメリットは、相続分の代償金をほかの相続人に支払うことで公平性が維持できる点にあります。
引き継ぐ相続人にとってはまとまった現金が必要になるため、状況次第では選択が難しい分割方法でもあります。
代償分割を用いて土地を分ける場合は時価や評価額など、代償金の算出方法で折り合いがつかないこともあるため、注意が必要です。
現物分割
現物分割とは、現金や土地などの財産をそのまま相続人へ引き継ぐ分割方法です。
具体的には、「現金(預貯金)は長男で土地は次男」や「土地Aは妻、土地Bは長男」という具合に、相続財産をそれぞれの相続人へ分割します。
現物分割のメリットは、比較的手間をかけずに公平に分割できる点にあります。
財産に手を加えることなく名義変更手続きだけで完了するため、手続きがシンプルなところが魅力です。
一方で、不公平感が生じやすいデメリットがあります。
たとえば、1,000万円の土地を長男が相続し、現金500万円を次男が相続した場合は、次男が不公平に感じてしまうことも否めません。
そのほかに、土地の分け方次第では用途が限られてしまうため、土地の価値が下落してしまう可能性もあります。
共有分割
相続財産を相続人全員で共有する分割方法です。
公平に財産を分割できない場合やそれぞれの相続人の同意が得られない場合に、共有分割が選択されることがあります。
共有分割は土地などの相続財産をそのまま複数人で共有するため、難しい手続きは必要ありません。
一方で、土地を売却したり建物をリフォームするときには、名義人全員の同意が必要になるというデメリットもあります。
そのほかには相続人が亡くなったり、子どもや孫ができたりすると相続人の数が増えるため、余計に管理が難しくなることもあります。
不動産の共有分割はトラブルに発展しやすいので、よほどの事情がなければ避けたほうが良いでしょう。
土地を相続するときの手続きの流れ
実際に土地の相続手続きを進めていくことになったら、どのような流れで進んでいくのかわからない方も多いのではないでしょうか。
以下では、土地を相続するときの手続きの流れを4つのステップに分けて解説します。
STEP1:遺言書の確認する
最初に遺言書の確認をします。
遺言書が作成されている場合は遺言書の内容に沿って、土地や現金などの遺産を相続人の間で分割します。
遺言書の種類は、次の3種類です。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆遺言書は、遺言者もしくは法務局にて保管されます。
公正証書遺言は公証役場、秘密証書遺言は遺言者が保管します。
遺言書の効力は法定相続よりも優先されます。
遺言書に記された内容が法定相続にのっとっていない場合でも、遺言書の内容は優先されます。
STEP2:相続財産と相続人の確定する
次に専門家に相談して、土地や現金などの相続財産と相続人を特定します。
相続財産と相続人が決まらないと、財産分割を決めることはできません。
土地の評価額を知りたい場合は、次の方法で確認できます。
- 固定資産税課税明細書を確認する
- 役所にて固定資産課税台帳を閲覧する
- 役所で固定資産税評価証明書を発行してもらう
ただし、相続財産は土地や現金のみならず、借金やローンの残債など負債にまで及びます。
調査の結果、負債が多い場合は相続放棄の選択も有効です。
STEP3:遺産分割協議を進める
遺産分割協議とは、相続人全員が納得して相続財産を分配するために、土地や現金などの財産の分配について話し合うことを指します。
土地や現金などの分配方法について相続人全員の合意が得られた後に、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成する際は、全ての相続人の署名と捺印が必要です。
分配について話がうまくまとまらない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判を介して財産の分配方法を決定します。
また、弁護士に依頼して財産の分配方法を確定させる方法もあります。
専門家の手助けがあれば、慣れない手続きと話し合いで神経をすり減らすこともなく、トラブルを未然に防ぐことも可能です。
STEP4:相続登記にて名義変更を行う
財産の分配方法が決まった後は、相続登記に進みます。
相続登記とは名義を相続人へ変更する手続きのことです。
相続登記が行われないと、不動産の売却ができず、融資の担保として不動産を差し入れすることもできません。
不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化されました。
相続の事実を知った日から、3年以内に申請しなければいけません。
登記手続きを怠った場合は、10万円以下の過料が課されることもあるため、注意が必要です。
なお、義務化の前に相続した物件についても義務が課されます。
土地の相続にかかる主な費用
土地の相続にかかる主な費用は、次のとおりです。
- 相続税
- 登録免許税
- 書類取得費用
- 司法書士への報酬
- 固定資産税
それぞれの詳細について説明します。
相続税
相続税は、亡くなった方の財産(相続財産)を相続した人が支払う税金です。
相続財産には、土地や建物、預金、株式など、あらゆる財産が含まれます。
相続税の課税対象は、相続した財産の評価額から借金などを差し引いた金額が、基礎控除額を超えるかどうかで決まります。
基礎控除額は、相続人の数や相続人の間の続柄によってそれぞれです。
相続税の計算は複雑で、専門的な知識が必要です。
相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日から10か月以内と定められています。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の売買や贈与など、不動産に関する登記を行う際にかかる国税のことです。
相続登記のほかには、家を新たに建てて所有権の登記を行う場合や、中古住宅を購入して名義変更をする場合などに発生します。
登録免許税は、登記する不動産の固定資産税評価額に基づいて計算されます。
計算式は、次のとおりです。
固定資産税評価額 × 税率0.4%
一般的に、評価額が高いほど税額も高くなり、登記の種類によっても税率が異なります。
書類取得費用
相続登記に必要な書類は役所で発行してもらえます。
相続登記に必要な書類と発行手数料は、次のとおりです。
| 書類 | 発行手数料 |
|---|---|
| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 1通450円 |
| 除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 1通750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
| 戸籍の附票の写し | 1通300円程度 ※自治体により異なる |
| 住民票の写し(除籍) | 1通200~300円程度 ※自治体により異なる |
| 印鑑証明書 | 1通200~300円程度 ※自治体により異なる |
| 固定資産評価証明書 | 1通200~400円程度 ※自治体により異なる |
1通あたりの発行手数料はそれほど高くはありませんが、相続登記にて必要な書類は1通だけでは済まない点に注意が必要です。
また、被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの全てが必要です。
そのほか、法定相続人それぞれの戸籍謄本も用意しなければいけません。
必要な戸籍謄本の枚数は相続関係にもよるものの、シンプルな相続の場合でも5〜10枚程度必要になるケースが多いです。
被相続人が転籍を繰り返していた場合や、兄弟姉妹が法定相続人になる場合はさらに枚数が増えることとなります。
司法書士への報酬
相続人が全ての相続手続きを自分でできる場合の費用は、登録免許税と必要書類の手数料のみですが、司法書士へ手続きを依頼する場合は、司法書士へ支払う報酬が必要です。
平成30年に日本司法書士連合会が実施した報酬に関するアンケートによる平均報酬は、5万円〜15万円でした。
地域や手続き内容によって価格の違いはあるものの、大まかな目安として捉えておくと良いでしょう。
一般的な報酬の決め方は、基本報酬に相続人の数と不動産の個数を加味して算出されることが多いです。
司法書士の報酬は決められた体系がないため、詳細は司法書士事務所に問い合わせて確認するのが基本です。
固定資産税
固定資産税とは毎年1月1日現在において、土地や建物などの固定資産を所有している人に課される税金です。
その年に不動産を持っている人は、評価額に応じて税金を納めなければいけません。
不動産を相続した後は、毎年固定資産税がかかり続けることになります。
基本的な固定資産税の計算式は、次のとおりです。
固定資産の評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
自治体によっては、標準税率が高いケースもあります。
念のため、自分が住んでいる自治体の標準税率を確認しておくと安心です。
兄弟姉妹で土地を相続するときの注意点
兄弟姉妹で土地を相続するときには気をつけたいポイントがあります。
- 親の判断力が充分あるうちに話し合いをしておく
- 分割方法を十分に検討する
- 共有分割は選択肢から除外しておく
それぞれの注意点について解説します。
親の判断力が充分あるうちに話し合いをしておく
万が一のことを考えて、相続について親の判断力がある間に話し合いをしておいたほうが良いでしょう。
遺言書があれば問題ないですが、遺言書を作成する前に判断力を失ってしまう可能性もゼロではありません。
相続の揉め事は大きな財産がある場合だけと勘違いしてしまいがちですが、それほど財産が多くない場合でも相続の揉め事は発生するため、注意が必要です。
大きな相続の発生が見込まれる場合は、早めの対策がなされるため、案外揉め事は多くありません。
相続財産が少なく、事前の対策がなされていないケースで揉め事が発生するパターンが多く見られます。
分割方法を十分に検討する
相続財産の分割方法は、換価分割・代償分割・現物分割・共有分割の4つです。
土地の分割では現物分割は適しておらず、共有分割は扱いにくいため、換価分割か代償分割が選択されるケースが多くなります。
それぞれに適したケースがあるので、状況とそれぞれの分割方法の特徴をよく把握しておきましょう。
共有分割は選択肢から除外しておく
共有分割は、相続人全員で土地や不動産を共有する分割方法です。
一見すると穏便で公平な分割方法に見えるかもしれませんが、実際には将来的なトラブルの原因となる可能性があります。
共有分割の問題点は、売却や建物の改修などの重要な決定を行う際に、相続人全員の合意が必要になることです。
手続きが煩雑になるだけでなく、時間が経つにつれて予期せぬ共有関係が生まれることから、将来的に権利関係が複雑になり、手がつけられなくなるおそれもあります。
共有分割は、特別な事情がない限りは、選択肢から外しておくことをお勧めします。
土地の相続でよくある質問
ここまで、相続した土地の分割方法や手続きの流れなどを解説してきました。
ここでは、土地の相続でよくある質問を4つピックアップしたので、回答します。
「土地はいらないけど現金はほしい」という場合、どの分け方が良い?
不動産を売却して得たお金を相続人で分配する「換価分割」と、「代償分割」にて土地相当の現金をもらう方法があります。
換価分割は相続人全員の同意を得たうえで、不動産を売却します。
売り手が見つかって売却が完了するまでに、一年程度の長い時間がかかる可能性があります。
一方で代償分割は1人の相続人が不動産を取得する代わりに、ほかの相続人へ不動産相当額の金額を分配する方法です。
換価分割ほど時間はかかりませんが、遺産分割協議が整う必要があります。
遺言書がない場合はどのように手続きを進めたら良い?
遺言書がない場合は法定相続の決まりに従うか、相続人全員で話し合って相続財産の分け方を決める「遺産分割協議」を行います。
相続財産に不動産や有価証券が含まれている場合は、相続人全員が署名・実印を押した「遺産分割協議書」が必要になる場合があります。
相続人全員の承認が得られれば、法定相続の決まりに従うことなく、自由に分割しても問題ありません。
代償分割と換価分割はどちらが良い?
代償分割と換価分割にはそれぞれに適しているケースがあります。
代償分割に適しているケースは、次のとおりです。
- 被相続人と同居していた相続人がそのまま家に住み続けたい場合
- 居住していた不動産を売却したい場合
換価分割には、次のケースが適しています。
- 相続しても活用できない不動産の場合
- 代償分割に必要な現金を用意できない場合
- 所得税と相続税を支払うための現金が必要な場合
不動産を引き継ぐか否かによって、換価分割と代償分割の使い分けが決まります。
土地の相続は杠(ゆずりは)司法書士法人まで
相続した土地の分割方法は4つ用意されていますが、現金化を考えている場合は換価分割と代償分割の2つの方法から選ぶことになります。
相続後に不動産を活用しない場合は換価分割、活用の見込みがある場合は代償分割が選ばれるケースが多く見られます。
土地の相続では分割方法の決定や必要書類の用意、遺産分割協議の進め方など、専門的な知識を必要とするケースが多いです。
そのため、無理に自分で対処しようとすると余計に時間がかかってしまいます。
杠(ゆずりは)司法書士法人では、これまでに数多くの土地の相続手続きをサポートしてきました。
土地の相続について、わからない点があればお気軽にご相談ください。
専門家として適切なアドバイスを提案させていただきます。
本記事に関する連絡先
TEL: 06-6253-7707
メールでのご相談はこちら >>